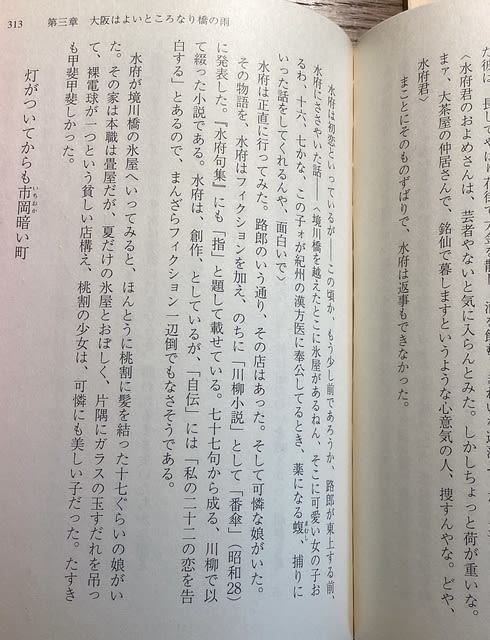タイトルに関して田辺聖子さんは、以下ように言われています。
内容に関して感想など記すのは後にして、該当ページをアップしておきます。
 反戦作家で官憲に虐殺された小林多喜二の名はみな人によく知られているが、同じく反戦川柳作家で、思想犯として検挙され獄死した鶴彬は、多喜二ほど知られていない。川柳という文学ジャンルに、日が当らないためであろうか。啄木に擬せられる早熟の天才なのだが。
反戦作家で官憲に虐殺された小林多喜二の名はみな人によく知られているが、同じく反戦川柳作家で、思想犯として検挙され獄死した鶴彬は、多喜二ほど知られていない。川柳という文学ジャンルに、日が当らないためであろうか。啄木に擬せられる早熟の天才なのだが。
評論もよくした。鶴が二十九歳という若さで歿したため、志なかば、という観もあるが、それでも質量ともに堂々たる川柳論となっている。みずからの短命を予知するかのごとく、書きに書いた。短い生涯にどんどん人間的成長を遂げている。プロレタリア柳人といっても決してあたまでっかちの、固陋な教条主義者ではなく、はじめは卑賤視していた古川柳(柳樽ほか)も見直し、「そのすぐれた遺産を新しい川柳創造の上に血肉化してゆく」べく、古川柳評価の境地まで到達する(「蒼空」 昭和11.3〝古川柳から何を学ぶべきかん〟)。
そして川柳を文学の一ジャンルとして文壇に認識せしめようとプロレタリアの立場から奮闘した。
よき川柳作家でありながら、 文才にも長けている(ことに評論分野で) 川柳人は少いものだが、鶴彬はその点でも、稀有な、双頭の鷲であった。 川柳文学が矮小視されることに抵抗し、緻密な川柳理論や句評を展開する。
尤も、川柳の文壇進出、つまり文学のままっ子扱いにされている川柳に正当な評価を、というのは水府の長年の悲願であった。 鶴彬よりずっと前から訴えつづけてきたことである。 「番傘」誌上で、あるいは僚誌 「きやり」などでも書いて川柳作家の奮起を促し、文壇にも川柳を俳句に劣らぬ文芸であると鼓吹してきた。その点は鶴彬と同じ立場である。しかし鶴は、「番傘」あたりの程度の作品じゃ文壇に相手にされないだろう、と、気鋭新進の作家らしく辛辣に切り捨てている(「川柳と自由」 昭和11・3〝川上三太郎と岸本水府にききたいこと〟)。
鶴の川柳的出発は田中五呂八の「氷原」で、新興川柳派の五呂八が「番傘」及び水府を〈無自覚な伝統派〉と罵倒し黙殺したことは、すでにのべた。
鶴の対「番傘」観もこれに同調している。
「くだらない通俗生活の断片におもしろさや、皮肉さの着物をきせた川柳では文壇に相手にされないだろう。むしろ落語家あたりが喜ぶにすぎない」
「僕たちにとつて川柳が文壇や詩壇に進出するといふことは、ブルジョワ新聞の隅つこへもぐりこんだり、「キング」あたりに下劣なお笑ひを一席やるために割り込んだりすることではない」
「僕は「番傘」あたりの作品を詩として呼ぶことが出来るかどうかうたがはしいと思ってる」(同)
 「キング」というのは戦前(戦後も昭和三十三年まであったが)、講談社が出していた大衆娯楽雑誌である。
「キング」というのは戦前(戦後も昭和三十三年まであったが)、講談社が出していた大衆娯楽雑誌である。
——くだらない通俗生活の断片におもしろさや、皮肉さの着物をきせた川柳・・・・・・これが本当はどんなに困難な文学的大事業であるか。
鶴が、搾取される労働大衆の自由と復権のために戦うのも、「番傘」作家が日々押しよせる〈通俗〉の波にさらわれそうになりながら、なおかつ、こまやかな情感の真実や、詩性を求めて戦うのも、同じことなのだが。
鶴彬にそれを、わかってほしかったなあ、と思う。 鶴をもっと生かせておいて、老いさせ、歳月の波に鞣させ、やがて「番傘」の句の、 醇乎たるよさに開眼させたかったなあ、というかえらぬ嘆きがある。私の直感では五呂八は無理だろうが、鶴彬は、やがてはある時期に至れば「番傘」の佳什を嘉してくれる日がきたかもしれないと悼惜する。
すでに「古川柳」の貴むべきに気付いている鶴のことだし、また前記の文章の中にも、
「『番傘』『川柳雑誌』 の中の作品を注意して見ると、従来の通俗趣味から、真剣な現実生活のうたひあげへかけ上らうとする意欲や気配を感じることが不可能ではなくなつてゐる」とも、柔軟な見方をしている。
鶏の作品は、
「手と足をもいだ丸太にしてかへし」 以下、鶴彬や、
「血を喀いて坑をあがれば首を馘り」
などのプロレタリア川柳が人に知られているが、伝統派的手法もよくこなし、昭和九年の 〈河北郡川柳聯盟結成記念川柳大会〉ではみずからも選者を務めているが、他の選者、たとえば「北国新聞」 柳壇の窪田銀波楼、もと石川県の名門柳誌「百万石」の安川久流美らによってよく抜かれている。
「国境になるとは知らぬ河の水」 以下、鶴彬(兼題「河」)
「繭の値の安さも言ふて村の朝」(兼題「村の朝」)
「さびしくも男嫌ひの薄化粧」 (兼題 「化粧」)
「器用」といふ兼題では人位二句天位一句抜けた。
「跳ねさせておいて鱗を削ぐ手際」
「口笛を吹いて出前は交叉点」
「風船屋危機一髪で息をとめ」
など、「番傘」ばりの好句が揃っている。
——老熟の鶴彬はどんなになっていたろう、とこれらの句で想像するのだが、いろんな可能性を示唆したまま夭折したところが、鶴の魅力でもあろうか。