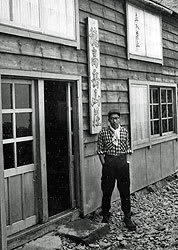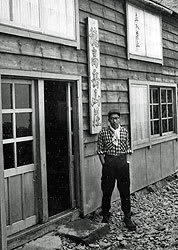 ** 46年前(1959) ** 穂高岳<♂24>
** 46年前(1959) ** 穂高岳<♂24>
大学の同級生と4人で、初めての槍・穂高へ。12日、激しい雨の中、槍沢を
下りましたが、あきらめられず涸沢入り。
前日(13日)は台風が北アを縦断。一日中、涸沢小屋で沈殿。
この日は快晴になり、ザイテングラードから奥穂に登り、前穂を経て岳沢を
下りました。
上高地からのバスは何カ所か路線が寸断していて、その間は徒歩連絡でした。
 ** 42年前(1963) ** 薬師岳(前列左端♂28)
** 42年前(1963) ** 薬師岳(前列左端♂28)
勤務先の高校山岳部夏合宿。前の日、この年の7月にも通った有峰からの道
を登り、薬師峠で幕営。14日、頂上往復後、カベッケ原に下りました。
その後、槍までの縦走を予定していましたが、雨にたたられ雲の平、三俣蓮華、
を経て18 日、小池新道から新穂高へ下山しました。
** 41年前(1964) ** 教え子たちと五竜小屋前で幕営していました
後立山縦走途中です。11日、平岩から入山。蓮華温泉~白馬岳~五竜岳~
鹿島槍~爺岳~扇沢出合 と5泊6日の合宿。当時の高校生は頑張ったものです。
** 35年前(1970) ** 蝶ヶ岳の稜線のテントで雨宿りしていました
リーダーをしていた社会人山岳会の15周年行事で槍ヶ岳集中登山を試みました。
東西南北と大滝~常念~大天井経由の5パーティ。穂先で落ち合う約束でした
が、またまた台風の襲来で失敗。
当時はケイタイがなくトランシーバーでしたが、弟のいる北鎌尾根隊との連絡が
取れず、はらはらしました。(結局、このパーティは台風の中、ビバーグして
槍に到達しました)
**29年前(1976) ** 子供達と大台が原にいました
近くの友人家族と雲一つない快晴の東大台を周遊したあと、大迫ダム近くの
吉野川畔にテントを張り、水遊び、バーベキューや花火を楽しみました。
 ** 27年前 (1978) ** 燕 岳
赤い帽子♀ペン(38)、左後ろ美穂(12)、右後ろ岳志(9)
** 27年前 (1978) ** 燕 岳
赤い帽子♀ペン(38)、左後ろ美穂(12)、右後ろ岳志(9)
上(大台ヶ原)の友人家族とは、毎年のように北アなどに一緒に登っていました。
この年は中房温泉から燕岳~常念岳~蝶ヶ岳と歩きました。
14日は燕山草で朝食後、山頂へ。槍から立山までの稜線をはじめ、富士山まで
見える大展望でした。こどもたちも、よく歩きました。
前回の「過去の今日」