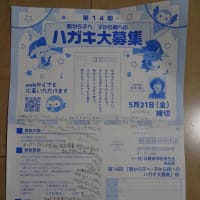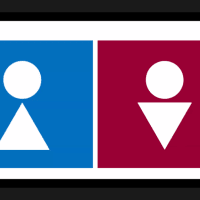友の会のおせち料理講習会に行って来た。
昨年度までは基礎講習という連続物でしていたらしいけど、年々教えられる人が少なくなって来て、今年は生活講習という形で単発でやっていってるそう。基礎講習の時は、生活団と重なって参加できない時があるので申し込めなかったけど、単発だと参加しやすい。
子どもの時から、冷めた料理は好きでないとおせち料理が特に好きではない。
今までもおせち料理ってかまぼこと黒豆を少し用意するくらい。
ベルメゾンでプーさんのおせち料理を買った事もあったな。
おせち料理作って、子どもに日本の伝統を伝えたいという人を見て、そんな発想なかったな、素敵と。私も少し興味が芽生えてたところに、こんな機会が。
説明聞いて、皆で実習。
だしは濁らせないってどういう意味ですか?
→もったいないからと絞り出さない (これ、やってた)
お雑煮の下に大根を敷いて、お椀にお餅がつかないように
お祝いの料理だから、飾り切りにして小さい野菜が出るのは、きんぴらやちらし寿司、豚汁に
お祝いの料理だから、飾り切りにして小さい野菜が出るのは、きんぴらやちらし寿司、豚汁に
ちょっとしたコツを教えてもらえるのも生の実習ならでは。
そしてそんなコツの中に、日本の文化の考え方が垣間見える。
料理を教わる事が、日本の文化をよりよく知るきっかけになる。
レシピだけでなく、おせち料理を作る段取りや、年末の「家事暦」を教えてもらえたのも大収穫です。
写真整理、冷蔵庫掃除、タオル新調、年末だからとやった事ない。仕事終わったら年末ぎりぎりに年賀状始めて、大掃除は時間があれば、タオルは使えるまで使い切るという習慣だった私には目からうろこが落ちまくりでした。
こんな講習受けたら、おせち頑張らないといけないのかと意気込みがちな私に、全て頑張る必要はないと伝えてくれるのも、さすが主婦の先輩。
全部すると気が狂いそう、いや気が遠くなりそうなので、一品でも増やせたらと思います。
一足早くおせち料理のランチ。
素敵過ぎなひと時。
#おせち料理講習会
#家事ごよみ
#世のできる主婦はこうやって段取りするのか
#全部やる必要ない
#全部頑張るのをやめてどこに集中するか
#メリハリをつける
#全部頑張るのをやめてどこに集中するか
#メリハリをつける
(12/9FBに投稿した物を一部編集)