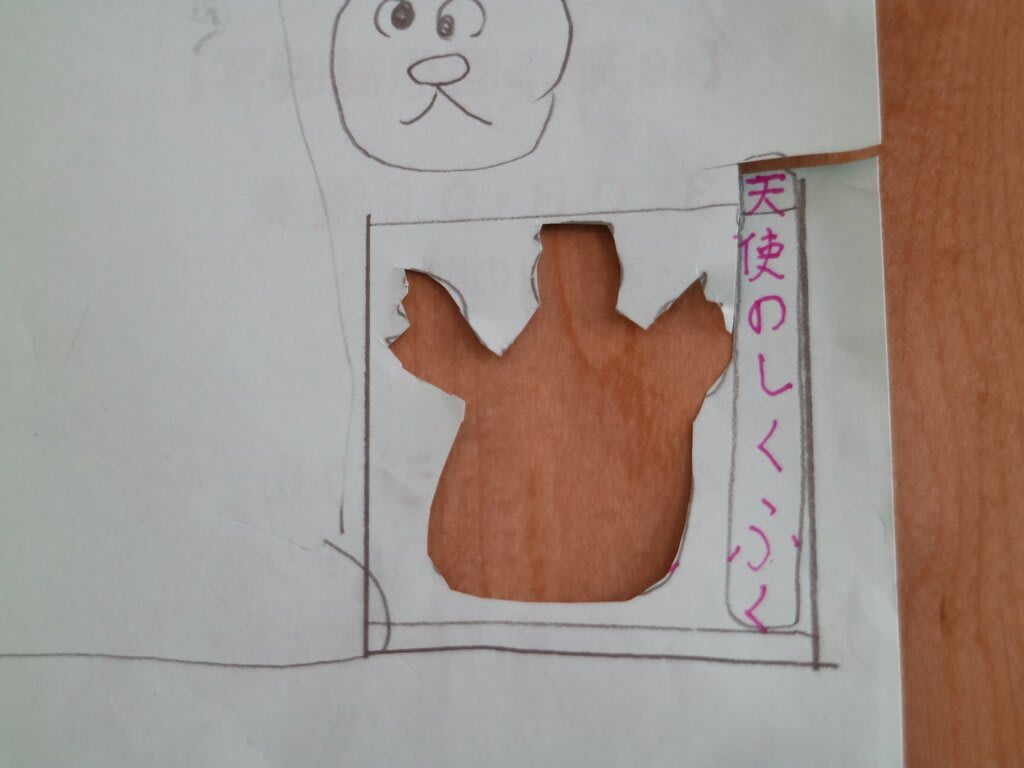赤ちゃんを別室で泣かせっぱなしで良しとする考えもあるけど、私は違和感あり。こういう風に説明されるとしっくりくる。
私も助け求めるの苦手だから、踏ん張ってしまう方だけど。
せつ
抱っこの練習会・交流会を主催しています (2005–現在)執筆者は204件の回答を行い、38.7万回閲覧されています
とても気になる質問でした。
「いつも世話をしたりなだめてくれる人がいて当然と、子どもが思わないようにしたい」
これを言い換えると「いつも世話をしたりなだめてくれる人がいなくて当然と、子どもに思わせたい」ということになります。
そしてこれはおそらく、「SOSを発信しても、誰も助けてくれる人がいなくて当然」と、あなた自身が、思っているから ではないですか?
今まで自分は助けてもらえなかったから、
今、助けてくれる人がいないから、
あるいは、「助けてほしい」と、言ったことがないから。
ではないですか?
この質問からは、泣かせっぱなしには本当はしたくない、でももう耐えられない、助けてくれる人もいない、このまま、同じ部屋にいたら、子どもを虐待してしまうかもしれない、といった、追い詰められ、切羽詰まった悲鳴が聞こえてくるようです。
赤ちゃんが泣き続けるのは、本当につらいです。
なんとか泣きやませようと、おっぱいをあげたり、オムツを調べたり、抱っこをしたり、一生懸命いろいろやってみるけど、泣きやまない、寝てくれない、
自分も全然寝させてもらえない、夜通し抱っこしたままウロウロと歩き回り、腕も肩も、腰も痛む・・・・それでも子どもはまだ泣いている・・・・
もういい加減にして!!泣きたいのはこっちだ!!と、子どもを壁に向かって投げつけたい衝動にかられたことが、私にもありました。
でも・・・・・赤ちゃんは、親を困らせたくて泣いているわけではありません。
何か困ったことがあって、でも自分ではどうにもできないから、訴えているんです。何かを伝えたいけど、まだ言葉が話せないから、「泣く」という表現しかできないんです。
一生懸命、がんばって伝えたのに、来てくれない、何もしてくれない・・・が積み重なれば、赤ちゃんは、そのうち、あきらめるかもしれません。
大成功!
あなたは子どもに「あきらめること」を教えました。
不信を教えました。
「助けて」と言っても無駄だ、誰も助けてなんかくれないよ!ということを教えました。
こんなふうに「あきらめ」を学んでしまった子が、将来、例えば、学校でいじめられた時や、何か悩みを抱えた時、親に、あるいは周りの誰かに「助けて」が言えるでしょうか?
もしかすると・・・・・質問者さんも、そういう子どもだったのかもしれませんね。
(追記)親が愛情いっぱいに育てても、いつしか、そういう感覚を身につけてしまうことは多いと思います。
それは、今の社会が、そういう空気だから…。自己責任、勝ち組、負け組、マウント、などなど。
でもだからこそ、せめて親だけは……と思うのです。(追記終わり)
昨年書かれた質問なので、今どうされているか、とても心配ですが、同じ悩みを抱えている方は、たくさんたくさんおられると思います。
「あきらめ」という呪いを解いて、どうか、周囲の人に「助けて」「もう自分は限界なんだ」と伝えてください。
子どもの大半が、周囲には理由もわからず、予兆もなく、「突然死ぬ」。
これについて奥田さんは、「助けてが言えない」ことを指摘する。それはなぜか。「大人が『助けて』を言わないからです」
元ホームレスで作る『生笑一座』の語りから見えたこと01 -「助けて」が言えない社会|矢嶋 桃子|note
東大の小児科医でご自身も脳性麻痺に罹患している熊谷晋一郎先生の言葉でもう一つ忘れられないものがあります。
それは「自立とは依存先を増やすことだ」という言葉です。
それを熊谷さんから聞いた時に、ハッとしたんですね。
僕ら自身も依存症の治療をやっていますが、治るということは依存しないことだとつい思ってしまいがちです。
でも、そうじゃなくて、たくさんの人に依存させることが一番いいと僕は思っているんです。この言葉を聞いたときに、そうなんだよな、そうだった、そうだったと思って。
歯を食いしばって、誰にも泣き言を言わずに一人で頑張ることが自立ではない。そんな人は脆くてすぐにポキッと折れちゃうんです。
できるだけサポーターをたくさん作ることこそが本当の自立なんです。
そして、最大の自傷行為は何かというと、「助けを求めないこと」なんです。
自立とは依存しないことではなく、依存先を増やすことだ | 文春オンライン
助産師さんや保健師さんに相談したり、地域の子育てサークルに行ってみるのも良いかもしれません。
自分だけで抱え込んだり、幸せそうなインスタ写真で取り繕わないで、どうか、今の状況を誰かに伝えてみてくださいね。
誰かに愚痴って気持ちを吐き出すだけでも、きっと心が軽くなりますから。