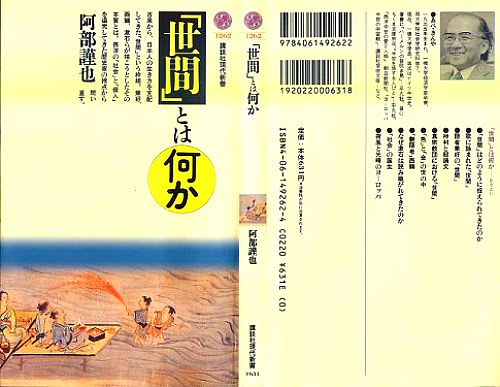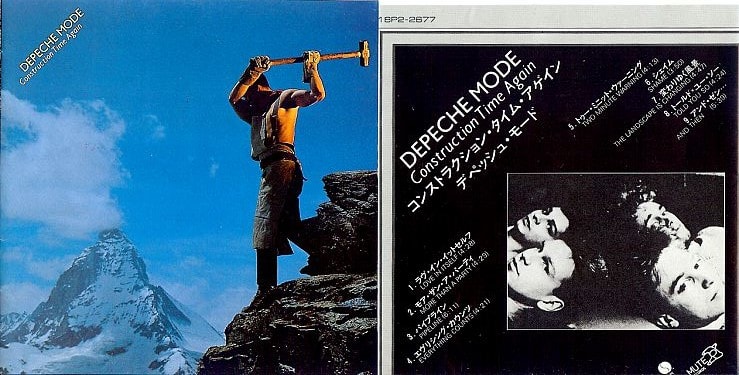秋のさわやかな空。そんな昨日の昼下がり。
FMラジオからは、交通情報お姉さんの声。
言葉を噛みながら「マンジュシャゲ公園に向かう車で混んでいます。」と恥ずかしそうにしゃべっている。
ポツリポツリ、と雨が降る中、昨夜帰る。
TBSラジオからは竹中直人さんの「月夜の蟹」。番組秘書の堀井美香さんのエロティックな声。その後、小雨はスコールに変わる。
この土曜も日曜も歩いた。秋のお彼岸。
歩けば、たくさんの艶やかな彼岸花に出会う。
 ■Virginia Astley 「From Gardens Where We Feel Secure」1983■
■Virginia Astley 「From Gardens Where We Feel Secure」1983■
 ヴァージニア・アストレイ
ヴァージニア・アストレイ
近時、腰痛が強い。それは歩いている最中のときだったりもする。
我も忘れて歩いているうちに、唐突に腰痛が舞い降りる。足がそこから前に進まなくなることがある。
携帯電話に入った歩数計を見て、その数字の多さに驚き、近くの道端で休む。その気は無いのに、歩くうちにそうなってしまう。
腰痛は寝ている間にもやってくる。
こちらを痛みで揺り起こし、その時間から眠れなくして、いたずらな妖精は去っていく。
初めは「適当なものをしいて、ござの上に寝ているから痛くなるのだ」と思っていたが、この休みに自ら腰周りをさわって驚いたのが、ホネホネになっていて肉が付いていない。
指に伝わってくるように、そりゃあ、痛いだろう。
食はちゃんと摂っているが、インナーマッスルが落ちていく速度に間に合わない。勝手な診断。


昨日、外に出て感じたのが、夏が終わったなどと言っている余裕もなく、秋を味わわないとすぐに季節は冬になってしまう。
それくらいに、この20日程度で、あっという間に陽が沈む時間が短くなり、17時前には赤い夕陽と空となる。
昨日も目的ない歩みだったが、午後になって外を歩くと、日の傾きはすぐにやってきて焦る。
そんな空には、ピカッ・・・ピカッ・・・と数秒おきに点滅する清掃工場の塔があって、どうせすぐに夜が来るなら、またあの塔の近くまで行こうと、直線距離を歩きだした。
もう落ち葉や紅葉の始まりを見た。
歩むに伴い、近くに次第に迫ってくる塔。
空塔の下でぽかんとクチを半開き、間の抜けた顔の集団を見るのは容易だが、この塔の下には誰もいない。



江戸川区との境界線である、川沿いのその場所は、エアスポットとして異質な空気を漂わせている。
この空気感は、幼い頃に、三ノ輪近所にあった空気。日本堤・千束・吉原・千住・小塚原・・・。
塔を巡って歩いたのち、東墨田に入る。妙に懐かしい思いと共に、切ないなあ、という街の後ろ姿が見えた。三ノ輪・千住方向には街工場が多くあり、遠くや近く、煙突の風景、機械の動く音、油の匂いがした。
自分の家の真裏にあった幼稚園の隣に、当時あったレンズ工場を思い出していた。
まだ背の低い子供の自分は、背伸びして窓から工場の中を覗いた。
機械の音が延々とし続けるその工場。トタンで出来た外塀は、グレイの色で統一されていた。
外に漏れる音以上の騒音が中を占めて、マスクをしたおばさんたちが並んでレンズの検品をしていた。


東墨田は町工場(まちこうば)が密集したマチ。
今でも仕事でこんな工場の現場に入るから、見慣れた風景でもあるが、これだけもの工場が並ぶと壮観である。
ジュースやビールのビンを作る工場の立派な看板に書かれた「製壜所」という文字、その背後に聞こえるカラカラという音。
それは、ビン同士が乗ったコンベアラインから、微妙な振動にこすれた音。プシューッと空気が抜ける音。
工場が並んだ場所を徘徊していると、YMO「テクノデリック」やビートニクス「出口主義」の音が聞こえてくる。
旧中川沿いに抜け出る。歩いていると、ランニングやウォーキング、あるいは散歩の人とすれ違う。
しかし、それも夜に向かってどっぷりと暮れていくと、ひとけの無い道となっていく。
旧中川はまるで三日月湖そのもので、蛇行しているため、方向音痴の自分は東西南北が分からなくなる。葉を落とした合間から見える建物、川面を可愛く鳴きながらつがいで遊ぶカモ、それらを見上げた、その組み合わせの水場のシーン。逢魔ヶ時。
北欧のフラ・リッポ・リッピのジャケット写真を思い出す。

ずいぶんと遠回りをしながら、荒川脇に出るが、一帯には次第に闇が降り、工場の合間を縫っていく。
その果てしなく寂しげな道を歩くと、歴史的な名残りを残した地の痕跡。
ひたすらの暗がりをてくてく歩いて、やっとのことで電車が荒川の鉄橋を渡っていくのが見える。
川堤の内側の長くまっすぐ進む道と鉄橋が交差する所は、短いトンネルになっていて、灯りを放っている。その灯りを目指し、周囲に感ずる視界にシャッターを切りつつ進む。

道を通り過ぎてから、はっとして振り返り、数m戻る。
家と家の間に空地があり、大荒地野菊らが暴れ咲く中、一つの石碑があり、両脇に花束が置かれていた。小旅の中でどうにも引っかかる風景に出会うことは多い。
近付いてひざまづくと石碑には、関東大震災で亡くなった中国人や朝鮮人の方々への鎮魂が記されていた。夜の墓地も神社も平気な自分だが、誰もいない道の暗がりで、そこは特異な時空の磁場を放つ。分からないながらも、ひざを付いて碑に記された文字を読み、シャッターを切り、黙した。
赤線・玉ノ井のことや荷風先生のことは知りながらも、無知の自分はこの碑が何を意味しているのかは分からなかった。帰って調べて、その碑が意味しているものを知った。単なる震災で亡くなった方への碑では無かった。
本当の事実はもはや確認しようもないが、関東大震災があった1923年にここで起きた、と言われている事件への慰霊碑だった。
2014年、改めて戦時中の占領地での事件が議論になる昨今。
そこと繋がるかのような景色が、経緯を知らぬ自分の目の前に現れるというのには、何かがあるのだろう。
事実がどうあれ、いずれにしても不幸であり、不毛に感じる。
国家と国家、というはざまで市井に生きた人が、押し潰されていったと言われる風景は、他人事ではなく、自分と地続きであることを、今一度思ってみる。
■フィル・コリンズ(コーラス:スティング)「ロング・ロング・ウェイ・トゥ・ゴー」1985■