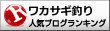吾妻渓谷の自然観察会で新たに見つけた虫えい(虫こぶ)の二つ目はアサマヒゴタイツボミフクレフシ(仮称)・・・キリ番の当ブログ掲載150種類目!
吾妻渓谷自然観察会でアサマヒゴタイ(キク科トウヒレン属)が数株咲き始めていた!
その中に、蕾の形が本来の紡錘形でなく、少し扁平の球形になっているものが有ることに気が付いた!

よ~く見るとかなり肥大化している・・・

「あれ、もしかしたら虫えい(虫こぶ)かも?」と思って観察会参加者そっちのけで切断・・・案の定、虫えい室があって乳白色の幼虫が見られた!

気になって、二日後に再度調査に行ったら広範囲に相当数の株で寄生が見られたので九州大の湯川名誉教授に送って解剖検鏡をしていただいた・・・
湯川先生から最初に戴いたコメントは・・・「タマバエによって、キク科トウヒレン属の植物に虫えいが形成されたという記録は、私の知る限り、まったくありません。 初めてのご報告だと思います。 大変珍しい虫えい発見のご報告、誠に有難うございました。 アサマヒゴタイツボミフクレフシ D-1170 として、記録しておきたいと存じます。 このご報告で、トウヒレン属の他の植物でも虫えいが見つかる事と期待しています。」・・・とのことで大変珍しいらしい! 私的に新種9種目になった!
その数日後、軽井沢で虫えい(虫こぶ)探しをしていたら、そこにもアサマヒゴタイが・・・そして、同じような虫えい(虫こぶ)が見つかった!

彼方此方に有るんだね・・・そういう目で見ていないから見つけられなかったのだろうな!
家に持ち帰って切断した・・・

吾妻渓谷のものと同じく乳白色の幼虫が見られた!

拡大画像・・・

そして、検鏡して戴いた湯川先生から結果のコメントが来た!
「虫えい内には、乳白色のハチの終齢幼虫が入っていました。もし寄生蜂だとすれば外部寄生蜂だと思います。 ご投稿の幼虫の写真と同じものです。 虫えい内には、複数の楕円体の幼虫室があり、幼虫室の周りの壁は黒く、硬くなっていました。 空の幼虫室は少なく、ほとんどの幼虫室にハチの幼虫が入っており、タマバエの幼虫は見つかりませんでした。 タマバエのゴールで、これほど硬い幼虫室はあまりなく、ひょっとして、ハチが形成したゴールかも知れませんので、今後の観察が必要です。 ハチの幼虫は、専門家に見てもらいます。」
・・・ということで、虫えい(虫こぶ)の形成主はハチ(タマバチ?)、または寄生蜂のようだね!
二つのブログランキング(それぞれ3カテゴリー)に参加しています。 (↓)のバナーをクリックして応援よろしくお願いします! (4377話目)
 |
日本原色虫えい図鑑 |
| 湯川 淳一,桝田 長 | |
| 全国農村教育協会 |