朝日新聞の記事を読んだら,ちょっとわかった。
----引用
ゲートバーのないタイプを導入する方針を明らかにした。時速20キロ以下の制限も緩め、一定速度で走りながら通過可能にする。来年度末以降の開通区間から始め、既存のものは改修時などに更新する。車載器はそのまま使えるという。
----
ということで,車載器はそのまま使えるということは通信方式のバージョンアップ等ではなく,単にゲートの仕様を変えるだけのようだ。
本来,ETCの通信能力は時速80キロ程度までOKだったと記憶する。(エラー率は多少上がってくるだろうが)
現在20キロに制限しているのは,読み取れないからじゃなくて,バーが閉まった時に止まれないから。
前にもこのブロクで主張したように,そもそも「ノンストップ」「だけど不正通行はバーを閉める」というやり方に無理があったのだ。カード挿し忘れや車載器の不調などでゲードが開かない場合,運転者は予測していないからパニックブレーキになる。
これによる後続車の追突も発生する。
バーを閉めるなら,全車一旦停止,もしくは区間を長くして,かつその中に2台以上侵入できない仕組みが必要だったのだ。
私は,ETCゲートで発生する事故はすべてその仕組の設計に起因してると思っている。
だから,今回ゲートを閉めなくするのは2.0なんて大仰な冠をつける話ではなく,当然されるべき改善というレベルの事だろう。
ポイントは故意,善意にかかわらず発生する不正通行の事後処理をどうするか。
これについても昔何回も書いたが,カメラでナンバーを撮影しているんだから登録住所に通知を出し,期日内に支払えば罰則なし,その後倍々ゲームのような延滞金を課すようにして,最終的には車両差し押さえなどができるような制度を作ればいい。あと,WEBSITEで簡単に支払える仕組みは絶対に必要。
車載器を付けず,ナンバープレートも細工して通過する車両に対しては打つ手が無いけど,ゼロリスクを求めてたらなんにもできないからね。
----引用
ゲートバーのないタイプを導入する方針を明らかにした。時速20キロ以下の制限も緩め、一定速度で走りながら通過可能にする。来年度末以降の開通区間から始め、既存のものは改修時などに更新する。車載器はそのまま使えるという。
----
ということで,車載器はそのまま使えるということは通信方式のバージョンアップ等ではなく,単にゲートの仕様を変えるだけのようだ。
本来,ETCの通信能力は時速80キロ程度までOKだったと記憶する。(エラー率は多少上がってくるだろうが)
現在20キロに制限しているのは,読み取れないからじゃなくて,バーが閉まった時に止まれないから。
前にもこのブロクで主張したように,そもそも「ノンストップ」「だけど不正通行はバーを閉める」というやり方に無理があったのだ。カード挿し忘れや車載器の不調などでゲードが開かない場合,運転者は予測していないからパニックブレーキになる。
これによる後続車の追突も発生する。
バーを閉めるなら,全車一旦停止,もしくは区間を長くして,かつその中に2台以上侵入できない仕組みが必要だったのだ。
私は,ETCゲートで発生する事故はすべてその仕組の設計に起因してると思っている。
だから,今回ゲートを閉めなくするのは2.0なんて大仰な冠をつける話ではなく,当然されるべき改善というレベルの事だろう。
ポイントは故意,善意にかかわらず発生する不正通行の事後処理をどうするか。
これについても昔何回も書いたが,カメラでナンバーを撮影しているんだから登録住所に通知を出し,期日内に支払えば罰則なし,その後倍々ゲームのような延滞金を課すようにして,最終的には車両差し押さえなどができるような制度を作ればいい。あと,WEBSITEで簡単に支払える仕組みは絶対に必要。
車載器を付けず,ナンバープレートも細工して通過する車両に対しては打つ手が無いけど,ゼロリスクを求めてたらなんにもできないからね。
















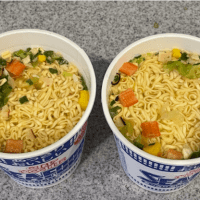
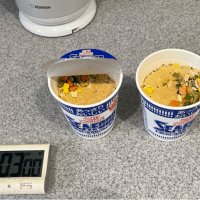


実際に、H10年の運用直後は、平均40㎞/H程度だった侵入速度が、1年も立たないうちに一部に料金所で78㎞/Hを記録しました。
その為、ゲートの反応速度を0.4/sから0.5/sに変更されたのです。
ICカード未挿入のケースが減った為、通信異常が起こるケースが少なくなった為、今回の様な構想となったようですが、料金所の設計上、80㎞/Hでの侵入が許容できる料金所は少ないです。
ところで、ETC2.0というのは、ゲートをなくすのが本来の目的ではなく、ケチがついたDSRC車載器のブランド名変更が本質の様です。世間受けをよくするために、速度規制を撤廃というオブラートにくるんだというところです。
NEXCO等の道路事業者が国交省の方針に従うかは、不明です。
バーの狙いは進入速度を規制するため,というのは確かにそうでしょう。バーがあっても徐行しない車が増えたので開くタイミングを遅らせた経緯は私も覚えています。
バーがなければ全くスピードを緩めないで通過するのが当然でしょうね。
最後の「オブラート」の部分,なるほどです。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19990329ryoukinntyousyuu.pdf#Page=9
首都高など、機器の配置に制限があるところでは、この基準を満たせていませんでした。
逆に東北道の浦和本線料金所などでは、120km/h程度でも通行できていました。
バーが開くタイミングを遅らせる対策が行われたのは、通行車両と収受員さんの接触による死亡事故が発生したために、通過速度を抑制するためと聞いています。
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_old/index.php?id=113
http://www.w-nexco.co.jp/newly/h21/1002/
http://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/kanto/h20/1111/
ITS車載器/ITSスポットを使って走行経路情報を収集することで、時間帯や走行したルートを特定することで料金判定に使おうというというアイディア。
すでに出回っているITS車載器で再セットアップが必要なのは、ナンバー情報などの車両特定情報が車側からアップできないので、再セットアップでソフトウェア改修を行い、車両特定情報を取得できるようにしようということです。
ETC2.0車については、車両と走行経路がセットで収集できるようになるので…(以下略
料金所に関しては、今までの設計は現金受け渡し車が一定数いる前提だったのが、高速を走行する車両の9割近くETC車になったので、車線幅を広げてバーなしの料金所を作ろうということみたいです。ETC自体は、規格上80km/hでの通行は問題ないですし、実際に首都高のフリーフローはそのくらいでバンバン通過していますし。
既存のETC車も通行可能なので、ETC2.0だから何か変わるというものではなく、打ち出しのタイミングが重なっただけのオマケみたいなものですね。
えっ?本当なんですかー?
http://www.mlit.go.jp/common/001046643.pdf#Page=23
はっきりと通行不可のイメージ図なんですが?
国土交通省の誤りですかねー?
そうですね~。今のETCでも通れるんだけど、車両固有情報をアップリンクしてないから不正通行の場合は取り締まりができないので、建前上は2.0専用ということにする、なんてのが落ちじゃないのかな。
2.0 普及目的があるのかなー?
従来のETC利用者が故意に・誤っての、
2.0 進入対策は、やはり 2.0 にも
ゲート設置かなー? 笑
カード作動(装着・有効期限)
その他、機器不良
これらの、レスポンスは
ゲートの表示板だけなろうか?
やっぱし、ゲート・バー等で阻止かな?
不正通行対策は…どうするんだろう?