飛鳥にお城などあったっけ? 頂いた資料を読む間もなく出発。
古代の遺跡も見つつ、中世の城跡巡り。
先ずは厩坂寺跡(うまやさかでらあと)

それは周囲の田畑より少し高台になったところ。
今は栗畑になっているが、この土壇の上に何かあったんだなと想像できる。
「厩坂寺」は、藤原鎌足の夫人「鏡の大王」が、夫の病気平癒を願い創建した「山階寺」が起源。
壬申の乱の後、「山階寺」は藤原京に移り、地名をとって「厩坂寺」になり、平城遷都で平城京左京の現在地に移転して「興福寺」と名付けられた。
そして、藤原氏の私寺「興福寺」は国家の手で造営が進められるようになる。
奈良「興福寺」の前身がこんな身近にあるとは知らなかった。
いつも通る道を少し入ったところなのに全く気付かなかった。
石川池・剣池

池の向こうの小山は孝元天皇陵とされている。
石川池と言ったり、剣池と言ったりしているが、石川池と剣池は本来は別だという。
よく見れば、池の中に杭が並んでいる。
そこから向こうが「剣池」、手前は剣池を拡張して作られた溜池「石川池」
奈良盆地は雨が少なくて水不足を補う溜池が多い。
右)水鳥はカルガモばかりだった。
この池には流れ込む川がない。どこから水がきているのか?
今から行く和田池と地下でつながっているのではないかとのこと。
しばらく歩いたところに和田池がある。

昔、植村藩がトンネルを作って飛鳥川の水を引いて作ったという溜池「和田池」
東北の角に水の流入口があって、水が流れ込んでいた。
この和田池が、先ほどの石川池と地下でつながっているのではというのだ。
この道の下が暗渠になって飛鳥川から水が引かれているらしい。
飛鳥川は近いとはいっても少し離れている。昔のトンネル工事は大変だったろう。
豊浦ヒブリ
そこから近い竹藪の丘、これが「豊浦ヒブリ」とか「火振山」と言われている所だそうだ。
飛鳥を取り囲むように、ヒブリ山・火振塚・張山・フグリ山などの地名が点在するそうで、それらは中世の「烽火台」であったのではとのこと。
敵の襲来などを知らせたのか。
甘樫坐神社
甘樫坐神社では毎年「盟神探湯(くがたち)神事」が行われる。
盟神探湯というのは、熱湯の中の石を拾わせ、火傷の有無で真偽を決めるという古代の裁判。
ひどい!火傷するにきまってるやん。
裁判には「熱湯」の他に「焼けた鉄棒を握る」というものもあったそうだ。
盟神探湯は一旦行われなくなるが、室町時代に復活し、それぞれ、湯起請(ゆぎしょう)・鉄起請と呼ばれたらしい。
初めて聞く言葉で説明された時は聞き取れなかった。
甘樫坐神社で行われる盟神探湯神事、一度見たいと思っている。
「難波の堀江」(難波池)
推古天皇の「豊浦の宮」とも呼ばれる「向原寺」そこにある小さな池は「難波の堀江」と言われる。
欽明天皇の頃、百済の声明王から贈られた「仏典と金銅の釈迦仏」 廃仏派の物部氏が仏像を投げ込んだという池。
後年、通りかかった本田善光が仏像を拾いあげ信濃に持ち帰り祀ったのが善光寺。
今もその金銅仏は善光寺の秘仏となっているとか。
近くには拾いあげた仏像を洗ったという「すすぎの滝」もある。(水は流れていなかった)
午後、雨の中を出発。
甘樫丘の名の由来は何でしょう?と問われた。
橿原神宮・白橿など「カシ」の名の地名が近くにあるので・・カシの木が多いところだったからかな?
飛鳥川を渡る。
カーブして流れる飛鳥川
この「曲がった瀬」→曲瀬(まがせ)が語源かも?との説に、そうかもしれないと納得できる流れだった。
雷城(いかづちじょう) (雷というのは地名)

海抜110m 短い登りだが勾配は急だ。丘の上はクヌギやコナラと落葉
右)凹みのあるところは薬研堀(断面がV字形になった堀)の跡とか。
丘の上では同期で歴史に詳しいUさんが待っていてくださった。
中世にはここは城跡(砦)だったらしい。廓や堀などの遺構が残る。
古代の石室や埴輪なども出土している。飛鳥 神南備の旧社地の候補地でもある。
(神南備巡りで訪れたこともある)飛鳥坐神社は元はここにあったのではとの説もあるらしい。
昔、木が燃料として利用されていたころは丘の上に木は全くなかったそうだ。
北側の斜面は切り立っていて、砦にはよい地形だったのだろう。
雷の丘には雄略天皇と雷を捕まえた小子部栖軽(ちいさこべすがる)の説話も残る。
昭和32年に入江泰吉氏が撮られた甘樫丘から北方面の写真を見せてくださった。
向こうの山まで建物は見えない。
雷の丘はなじみの場所であるが、城跡とは知らなかった。
ここから北への道は車で通る。
田んぼの中にポコポコと見える丘は古墳かなあと気になりながら通っていた。
その一つに立ち寄る。
「ギヲン」という丘

田んぼのあぜ道を進むとギヲンの丘 西側はなだらかで雨でなかったら登れそう。
その北にある「 雷 ギヲ山城 」
中世の山城として「日本城郭体系」にも記載があるという。
郭や空堀があるらしいが、詳細不明
中世 多武峰と興福寺の対立で飛鳥も戦いの場になったところがあったという。
先ほどの「ギヲン」より大きいが見渡せない。説明がなければただの竹藪だ。
小山集落に入る。
杵築神社 同名の神社は多い。牛頭天皇を祀る。
この神社に拝殿はなく、奥の山は円墳だそうだ。
小山城
先ほどのギヲ山城から北西、橿原市との境、小山 字 西山 にある丘。
今迄見た城跡と違い、竹藪はフェンスで囲まれ、説明板もある。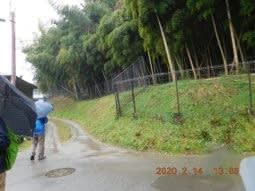

「この丘陵は西山と呼ばれ、中世(15世紀頃)戦国時代、南大和の豪族 越智氏の出城として一族の小山氏が築いた砦。
この奥に空堀が現存しており、家城周辺を環濠で囲み、外敵に対していたようである」
堀の痕は道路になっているところもある。
「家城」の意味がよくわからなかった。
山だけが砦というのではなく、堀を巡らせた平地部分も含めた砦だったということかな?
この丘の上には小さい平石が多数あるという。
上から近づく敵に投げつけるために運び入れたのではないかとのこと。

鍵を預かって開けてくださり、フェンスの中へ1歩入ってみたが、笹が繁り雨もあって踏み込めず。
せっかくの機会だったのに残念だった。頂上にあるという石礫見たかった。
昔は貝吹山で吹いたほら貝の音がここでも聞こえたそうだ。
一休みして、
紀寺跡のそばを通る。
小山廃寺ともいわれる紀寺跡。(紀寺は地名 大字小山 字紀寺)
発掘調査で金堂。講堂・中門・回廊・南大門・大垣の跡などが確認されている。
ここも平城遷都で平城京に移った。
藤原京 朱雀大路跡
朱雀門跡から北に広がる藤原宮跡 向こうは耳成山
元薬師寺

ホテイアオイもすっかり枯れた。田んぼを東塔跡へ。
右)塔の心礎や周りの礎石がたくさん残っている。立派だっただろうなあ。

西塔の跡 近くへ行かなかった。
右)金堂跡に建つ小さなお堂の前には、礎石がたくさん残っていた。
西ノ京にある薬師寺の前身にあたる寺の跡
畝傍御陵前駅で解散














