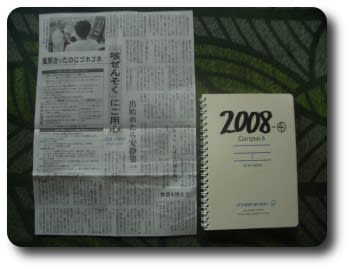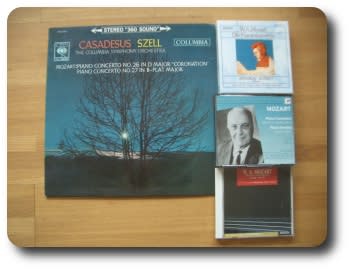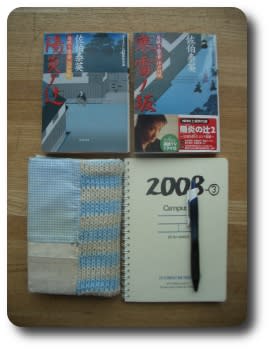このシリーズ、NHK-TVで土曜時代劇として放送中ですが、私が読んでいるのは、実は前回放送シリーズ「陽炎ノ辻」のようで、今の番組はずっと先の方をドラマ化しているらしいです。それなら下手に見ない方が、などと思案しているうちに、もうすぐ放送も終了するらしい。ちょいと残念。
さて、佐伯泰英著『居眠り磐音江戸双紙』シリーズの第7巻、『狐火ノ杜』を読みました。
第1章「紅葉狩海晏寺」。今津屋のお内儀お艶の葬儀も終え、おこんの骨休めを計画した磐音は、品川柳次郎、中川淳庵のほかに幸吉、おそめを連れて、紅葉狩に出かけます。このあたり、なぜ中川淳庵?と不思議です。名医の淳庵さん、そんな暇があったのでしょうか。案の定、乱暴旗本の金森右京の仮病騒動です。むしろ、国元で物産プロジェクトに奔走する中居半蔵の手紙が、良いですねえ。
第2章「越中島賭博船」。竹村武左衛門が、人足作業で怪我をしたといいます。武左衛門らしく、あまりに仕事が辛いので酒を飲んでの失態。品川柳次郎は、武左衛門の家族の窮状を見かねて、代わりに働くと申し出ます。そんなわけで、ついでに磐音も一緒に人足稼業。でも本命は、第4巻の金沢で知り合った三味線職人・鶴吉の仇討ちです。漁夫の利を得たのが南町奉行所の笹塚孫一さんです。この人、いいところで顔を出しますね。作者のお気に入りのキャラクターなのでしょう、きっと。
第3章「行徳浜雨千鳥」。南町奉行所から、200両の褒美が出ますが、磐音は鶴吉が江戸に戻ったときの開業資金として今津屋に預けます。老分の由蔵は、磐音のあまりの人のよさに不満顔。でも、主題は中川淳庵の恩人が隠居する行徳まで、蘭学を目の敵にする狂信的国粋主義者血覚上人の一派の襲撃を防ぐ話です。いつの時代も、狂信的な人というのはいるもので、それを作者は描きたかったのか。
ところで、金兵衛長屋から今津屋への帰り道、おこんが「刀を捨てて町人になるのなら、おこんがお嫁に行ってあげるわ」と告白する場面がありますが、この後の描写で磐音が「おこんの背を呆然と見つめていた」とあるのはおかしい。おこんの気持ちはそれまでも十分に感じているはずなので、「呆然」というのは違うでしょう。
第4章「櫓下裾継見世」。こんどは、今津屋の老分の由蔵が、能登屋という風呂屋の用心棒を世話します。2階でひそひそ話をしていたのは、上杉家の七家騒動の余波でした。でも物語はそっちではなくて、品川柳次郎が近所の御家人の未亡人に同情し、やむにやまれず刀を抜く話です。うーむ。この物語では、生活が苦しくなるとすぐ身売りに走ってしまうのですね。義弟の思慕と最後も悲劇的です。
第5章「極月王子稲荷」。前章の悲劇的なトーンをやわらげるためか、なんと76頁を費やして、落ちは駄洒落です!おこんさんに狐がついて、その父親が金兵衛で、「おこん金々おこんこん」、思わず「こんこん」と咳をしたというのですから、やれやれです。作者には、伝統的駄洒落保存会への入会をお勧めしたいところです。
最後の駄洒落で終わるのには思わずずっこけてしまいましたが、本巻は要するに奈緒と磐音とおこんの間の微妙なバランスが、おこんの側に一歩傾き、「おこん、ついに告白!」という小見出しが躍る、そういうストーリーでした。たぶん、次回は奈緒の側に揺り戻す思わせぶりなお話が登場するんじゃないかな。なんとなく、予想できそうです(^o^)/
さて、佐伯泰英著『居眠り磐音江戸双紙』シリーズの第7巻、『狐火ノ杜』を読みました。
第1章「紅葉狩海晏寺」。今津屋のお内儀お艶の葬儀も終え、おこんの骨休めを計画した磐音は、品川柳次郎、中川淳庵のほかに幸吉、おそめを連れて、紅葉狩に出かけます。このあたり、なぜ中川淳庵?と不思議です。名医の淳庵さん、そんな暇があったのでしょうか。案の定、乱暴旗本の金森右京の仮病騒動です。むしろ、国元で物産プロジェクトに奔走する中居半蔵の手紙が、良いですねえ。
第2章「越中島賭博船」。竹村武左衛門が、人足作業で怪我をしたといいます。武左衛門らしく、あまりに仕事が辛いので酒を飲んでの失態。品川柳次郎は、武左衛門の家族の窮状を見かねて、代わりに働くと申し出ます。そんなわけで、ついでに磐音も一緒に人足稼業。でも本命は、第4巻の金沢で知り合った三味線職人・鶴吉の仇討ちです。漁夫の利を得たのが南町奉行所の笹塚孫一さんです。この人、いいところで顔を出しますね。作者のお気に入りのキャラクターなのでしょう、きっと。
第3章「行徳浜雨千鳥」。南町奉行所から、200両の褒美が出ますが、磐音は鶴吉が江戸に戻ったときの開業資金として今津屋に預けます。老分の由蔵は、磐音のあまりの人のよさに不満顔。でも、主題は中川淳庵の恩人が隠居する行徳まで、蘭学を目の敵にする狂信的国粋主義者血覚上人の一派の襲撃を防ぐ話です。いつの時代も、狂信的な人というのはいるもので、それを作者は描きたかったのか。
ところで、金兵衛長屋から今津屋への帰り道、おこんが「刀を捨てて町人になるのなら、おこんがお嫁に行ってあげるわ」と告白する場面がありますが、この後の描写で磐音が「おこんの背を呆然と見つめていた」とあるのはおかしい。おこんの気持ちはそれまでも十分に感じているはずなので、「呆然」というのは違うでしょう。
第4章「櫓下裾継見世」。こんどは、今津屋の老分の由蔵が、能登屋という風呂屋の用心棒を世話します。2階でひそひそ話をしていたのは、上杉家の七家騒動の余波でした。でも物語はそっちではなくて、品川柳次郎が近所の御家人の未亡人に同情し、やむにやまれず刀を抜く話です。うーむ。この物語では、生活が苦しくなるとすぐ身売りに走ってしまうのですね。義弟の思慕と最後も悲劇的です。
第5章「極月王子稲荷」。前章の悲劇的なトーンをやわらげるためか、なんと76頁を費やして、落ちは駄洒落です!おこんさんに狐がついて、その父親が金兵衛で、「おこん金々おこんこん」、思わず「こんこん」と咳をしたというのですから、やれやれです。作者には、伝統的駄洒落保存会への入会をお勧めしたいところです。
最後の駄洒落で終わるのには思わずずっこけてしまいましたが、本巻は要するに奈緒と磐音とおこんの間の微妙なバランスが、おこんの側に一歩傾き、「おこん、ついに告白!」という小見出しが躍る、そういうストーリーでした。たぶん、次回は奈緒の側に揺り戻す思わせぶりなお話が登場するんじゃないかな。なんとなく、予想できそうです(^o^)/