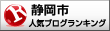私如き、サッカーの素人が、
偉そうにサッカーを語るのも烏滸がましいが、(おこがましいが)
ある意味、
天国(ワールドカップ優勝)から地獄とは言わないけれど、
転落して、出口が今は見えない?状況の中、
高倉監督に全て?を託したなでしこ。
もし男子チームの監督であれば、
なかなか結果の出ない新監督に対する風当たりは、
もう少しハードであってもおかしくないのだが、
現状は、世間の目が優しいというよりは、
無関心?という気がするのは私だけだろうか?
正直誰が監督となろうとも、
なでしこの成績が良くなれば、
それでいいとは思うのだが。
高倉監督の方針で、
私が一番気に入っているのは、
彼女のスタイルというか、
選考の基準が、隅々まで行き届いている?
ように見えることも素晴らしいのだが、
一つのポジションに甘えさせることなく、
色々なポジションに挑戦させるそのフレキシブルさ。
それは彼女の最大の長所だと思っている。
下に引用した記事からも読み取れるのだが、
(長すぎて読む気がない方はもちろんそれで結構ですが)
チームのレベルを上げるために、
できる限りの事を試してくれる監督。
例えば、
いつも同じ選手を使い、戦術も同じ。
それで結果が出なくて監督を変えてお茶を濁す。
過去の日本代表にありがちだった状況。
でも、高倉監督はきめ細やかな?で斬新な選考。
もちろんすべてのファンに納得の選考などできるわけではなく、
だからこそ、監督の方針に一本芯が通っていれば、
落選の選手も納得?できるし、
選ばれた選手も責任感が出るし、
あるいは入れ替えが明確なことで、
頑張れるのでは?
そして何より、
印象的なのが、選手のポジションのコンバート。
選手の力を最大限に発揮させ、
チームを機能させ、
そしてレベルを上げることを目標としたコンバート。
FIFA U-17女子ワールドカップで優勝した時のメンバーの、
柔軟性?
U-17女子W杯で決勝進出…“リトルなでしこ”快進撃の理由
文/池田敏明
コスタリカで開催されているU-17女子ワールドカップにおいて、U-17日本女子代表が決勝進出を果たした。ここまで5試合を戦い全勝で、21得点1失点と圧倒的な実力を発揮している。彼女ら“リトルなでしこ”の試合を見ると、他国と比べて2ランク程上のレベルでプレーをしているような印象を受ける。強さの要因として浮かび上がってくるのは、“柔軟性”というキーワード。リトルなでしこの選手たちは、あらゆる側面において柔軟性を備えているのだ。
まず、複数のポジションをこなせる選手が多いことが挙げられる。準決勝のベネズエラ戦では、後半に左SBの北川ひかるが相手との接触で負傷するアクシデントに見舞われた。通常なら同じポジションの選手を投入する場面だが、高倉麻子監督が切ったカードは、FWの齋原みず稀。彼女をワントップに入れると、FWで出場していた小林里歌子を左SH、宮川麻都を一列下げて左SBに入れた。小林はチームのエースストライカーだが、サイドでの起点作りやドリブルからのチャンスメークもできるため、SHでも十分に機能する。宮川も機動力と体幹の強さを生かして相手の強力アタッカー陣に対応し、守備力の高さを示した。
他にも、今大会で右SHと左SBをこなしている松原志歩や、FW登録ながらCBとしてプレーする大熊良奈と、ポリバレント性を備えた選手が揃う。フォーメーション変更や不測の事態にも、柔軟に対応できる強みを持つ。
以下略
これが日本の強みとする監督の采配。
これがトップチームでも発揮できれば、
復活の日は近いと思う。
だからこそ、2年くらいは我慢の日でも、
私は待っていられるのだが。
「攻守で噛み合わず…」スウェーデンに完敗のなでしこ 高倉監督の試行錯誤は続くのか
Football ZONE web 7月22日(金)6時40分配信
試行錯誤の続く高倉ジャパンの初勝利はお預けになった。現地時間21日になでしこジャパンは、リオデジャネイロ五輪に出場する強豪スウェーデンとアウェーで国際親善試合に臨み、後半に3点を奪われて0-3の力負けを喫した。
高倉麻子監督は「新しいことにチャレンジするなかで、自分たちが想像したような試合運びにはならなかった。一人一人の判断やテクニックはまだまだ上げなくてはいけないと感じた。走られてもいたし、サイドでも起点を作られた。全体にうまくいった試合展開ではなかった」と振り返った。
その言葉を裏付けるように、就任から3試合目での試行錯誤の痕跡はいくつも見えた。これまで不動のセンターバックだったDF熊谷紗希(リヨン)を中盤の底に配置し、ボランチが本職のMF川村優里(仙台)をセンターバックに配置してスタート。4-1-4-1システムの左の2列目にFW永里優季(フランクフルト)を起用し、1トップには小柄だが機動力のある増矢理花(INAC)を配置した。
しかし、序盤に主導権を握られると新システムは頓挫。2列目に入っていたMF阪口夢穂(日テレ)を下げたダブルボランチにしてゲームを落ち着かせた。その後は主導権を奪い返したもののゴールは奪えなかった。逆に後半に入ると全体的にチグハグなプレーも目立ち、同31分から立て続けの3失点で完敗となった。
「個人個人を試さなければいけない難しさ」
「チーム全体としての守備も攻撃もいろいろなところで噛み合っていない。個人個人を試しながらいかなくてはいけない難しさもあるが、下を向かずに良いところと悪いところを見ながらやっていきたい」
高倉監督は苦悩の胸の内をこう語った。2011年ドイツ女子ワールドカップ優勝メンバーからの世代交代が一つの課題とされるなかで、選手選考を進めつつ高倉イズムを植え付けていくという壁にぶつかっている。6月のアメリカ遠征2試合に続き、敵地で強豪との戦いを経験し、MF佐々木繭(仙台)ら新戦力も台頭している。チームの形を探りながら、まずは初勝利に向けて進んでいきたい。
フットボールゾーンウェブ編集部●文 text by Football ZONE web
スウェーデン遠征2試合目。クラブチームとのトレーニングマッチを通じてなでしこジャパンがトライしたこと
松原渓 | スポーツジャーナリスト 2016年7月26日 1時39分配信
【なでしこジャパン初勝利】
21日にスウェーデン女子代表との試合を終えたなでしこジャパンは、中2日で第2戦を迎えた。
毎日暑い日が続いているが、この日のキックオフは14時。炎天下のコンディションの中で試合は行われた。
第2戦の相手は、スウェーデン女子サッカー1部リーグ(ダームアルスヴェンスカン)に所属するクリシャンスタッドDFF。15歳~32歳まで、学生と社会人が混在したセミプロチームである。本来ならスウェーデン女子代表と2試合を組めれば理想的だったのだが、リオデジャネイロ五輪を間近に控えるスウェーデン側の事情もあり、クラブチームとの練習試合が組まれることとなった。
クリシャンスタッドDFFはクラブチームで、スウェーデン女子代表よりも個々のレベルは当然落ちる。だが、3人目の動きで裏に走らせるカウンター攻撃など、戦い方ははっきりしており、その点は日本にとって、スウェーデン戦の反省を生かす良い機会だったと言える。
日本のスタメンは、GK山根恵理奈、DFは左から國澤志乃、高木ひかり、村松智子、有吉佐織。ダブルボランチに熊谷紗希(キャプテン)と佐々木繭を置き、MFは左に田中美南、右に永里優季、トップ下に阪口夢穂、1トップに横山久美をおく4-2-3-1。
スウェーデン戦では縦に長いロングボールを蹴ってくる相手に対し、ボランチに下りてゲームを作る場面が多かった阪口だが、この試合の前半は高い位置で攻撃の最終局面の仕事に集中していた。
裏のスペースを狙い続けた阪口裏のスペースを狙い続けた阪口
だが、阪口が上がったことで、マイボールにした後にボールを落ち着かせるポイントがなかなか作れない。その結果、序盤は落ち着かない展開となった。スウェーデン戦で課題として上がっていた選手間の距離感は改善されたようにも見えたが、出し手と受け手のイメージが合わず、パスの精度も欠いてしまう。
35分には左サイドの連携から横山のボレーシュートが枠の左隅を捉え、44分には阪口、永里、横山とテンポ良く回して飛び出した阪口が決定機を迎えたが、いずれもGKの飛び出しとファインセーブに阻まれゴールならず。最終ラインから一発で裏を狙ったパスから決定機を迎える場面もあったが、すべてオフサイドにかかり、スコアレスで後半を迎えた。
攻撃の質が上がらない理由について、指揮官は、個々の状況判断とテクニックの物足りなさを口にした。
「前半は特に、動きを止めて足元で受けてしまっていました。相手もあることなんですが、あれぐらいのプレッシャーの間で自由にプレーができないとなると、どんな相手にも点は取れないと思います。もうちょっとテクニックの部分を上げていかないと、狙っているサッカーを実現するのは難しいと感じます」(高倉監督)
テクニックと言っても、足元の技術だけではない。駆け引きで相手を外す動きや、屈強な相手に寄せられた時に簡単に倒れないのも必要なテクニックだ。それは、連携以前の問題と言えるのかもしれない。
ハーフタイムには田中に代えて左サイドにMF中里優を投入し、CBの村松に代えてFW増矢理花をワントップに投入。熊谷と阪口を一列ずつ下げて、これまでなでしこジャパンがベースとしてきた4-4-2にすると、一気に安定感が増した。クリシャンスタッドは前半に飛ばしすぎたのか、後半は動きが止まり、日本が押し込む時間が続く。
機動力のある中里と増矢が積極的にボールに絡みながら、攻撃にアクセントを与えていく。中盤では阪口がゲームをコントロールし、ボランチを組む佐々木も積極的に攻撃に絡めるようになった。CBでは熊谷とともに、2回目の招集となった高木ひかりが安定したラインコントロールを見せた。
そして50分、阪口のパスを受けた中里が左サイドでターンすると、鋭く右足を振り抜き、ゴール右上に技ありのゴールを決める。
ゴールを決めて祝福を受ける(中里は背番号24)ゴールを決めて祝福を受ける(中里は背番号24)
ガッツポーズを見せる中里に、周囲の選手たちが走り寄って祝福を浴びせた。その後、後半の早い段階で永里に代えて右サイドに千葉園子を投入し、横山に代えて有町紗央里を投入。千葉が持ち味の運動量を生かして前線から追い、高い位置でボールを奪ったところから佐々木のミドルシュートがゴールをかすめるシーンもあった。
追加点は75分。左サイドで有町が仕掛けて打ったシュートがバーに弾かれるが、こぼれ球を千葉が頭で押し込んで2-0と引き離す。プレッシャーから解放されたように、千葉の笑顔が弾けた。
さらに、佐々木や増矢も積極的にシュートを放つなど、追加点が生まれそうな気配も漂う。終盤には左サイドバックに京川舞(←國澤)、ボランチに川村優理(←佐々木)を投入し、積極的な選手起用をしたなでしこジャパンが2-0で勝利を飾った。
【アメリカとスウェーデン、2つの遠征を通じて見えたもの】
なでしこジャパンはスウェーデン遠征を1勝1敗で終えた。
クリシャンスタッド戦の後半、慣れたポジションとシステムに変えてからはバランスが良くなり、日本の一方的なペースになった。だが、それは予測できたことでもあった。同じ4-4-2のシステムとポジションでスウェーデン女子代表戦に臨んでいたら、あるいは結果ももう少し変わっていたのかもしれないが、それでは未来への成長はありえない。
もちろん、代表チームにとって負けて良い試合は一つもないし、実際、高倉監督は常に勝負に対する強いこだわりを見せてもいる。だが、その中で「安定」は求めていない。今は選手個々の能力を見極めながら、3年後のW杯、4年後の五輪に向けて、若手にもベテランにも刺激を与えて成長を促し、チームの枠組みを作っていく時期でもあるからだ。
そして、6月のアメリカ遠征と今月のスウェーデン遠征でチームとして積み上げられたこともあれば、新たな課題も浮き彫りとなった。様々なチャレンジをする中で、個人とチームの「現在地」が明確になった分、やらなければならないことはさらに山積みになった感じもある。
まず、指揮官が先に挙げた個々の技術面での成長は継続的なテーマとなるだろう。
「形を決めてやっているわけではないので、変わりうる状況の中で、いろんなアイデアを持ちながら、相手の変化に対して自分のアイデアも変化させていける、そういう柔軟性を選手には求めていきたい。無難に止めて、とられないようにして、つないで、ということはやってくれているんだけど、もっと動きのあるサッカーを目指しています」(高倉監督)
芝の重さや、対戦相手の身体の大きさやスピードなど、国内では体験できないこともある。それは頭で分かっていても、実際にピッチで対戦してみないと分からないものでもある。今回の遠征に参加した新たな選手たちは、貴重な経験を日々のトレーニングにも生かしてくれることを期待したい。
また、多くの選手が普段やっていないポジションで起用された。それは、その選手がプレーの幅を広げるチャンスを与えると同時に、与えられた場所で何ができるかということを、見極めるテストでもあった。
「いろんな状況の中で何を判断して、何を描くかということが大切で、ポジションは関係ないと思うんです。持っているものが高く、いろいろなことを表現できる選手を集めてチームを作っていきたいと思っています。新しく呼んでいる選手の中で数名は計算できて、ある程度やっていけることが分かりましたし、1ヶ月前のアメリカ戦よりも成長していると感じた選手もいました」(高倉監督)
【新戦力の選手たちが見せた可能性】
新しい選手たちの成長は、今回の遠征の最大の収穫とも言えるだろう。
まず、2試合目で先制ゴールを決めた中里。アメリカ戦ではボランチでプレーしたが、今回はサイドハーフとトップ下でプレーした。ボランチとしては守備面の球際の強さが持ち味だが、今遠征の2試合では攻撃面で、日本のアクセントにもなっていた。
攻撃のアクセントになった中里攻撃のアクセントになった中里
「ボールを持ったら積極的にゴールに向かって仕掛けようと思っていました。スウェーデン代表戦で似たような形があって外してしまったので、今回は決められて、結果を出せて良かったです。課題はたくさんありますが、今後は苦しい試合展開の中で違いを出せるような選手になりたいです。私はスピードとパワーがないし、個で打開できるようなタイプではないので、機動力と運動量を生かして相手が嫌がるようなプレーをしていきたいです」(中里)
2点目を決めた千葉は、ゴールについて「ほとんど(有町)紗央里さんのゴール」と感謝したが、限られた時間でいくつかの決定機に絡んだ。
「大切な試合の前の日は緊張して眠れない」というほど、常に緊張と戦っている千葉だが、遠征の中で様々な貴重なアドバイスを受け、自らの殻を破りつつある。
殻を破りつつある千葉殻を破りつつある千葉
「高倉監督と大部コーチとお話していて、1つシュートを決めることで自分の自信につながるし、クロスを仲間が決めてくれたらそれが自分自身の自信になるから、と。今日のゴールが自信になったかはまだ分からないですけれど、ちょっとだけ見えたかなと思います。私はなんでも全力でがむしゃらにやってしまうんですけど、全部を全速力でやるから周りが見えていないことも分かりました。(阪口)夢穂さんから、『うちやったら、50%、50%でターンしている。それがうちのあかんところかもしれないけど、そういう余裕を持った方がいいんちゃう?』と言われて。ほんまやー!と。自分にもっと余裕を持たないといけないですね」(千葉)
また、今回の遠征で最も成長を感じさせたのが佐々木だ。アメリカ遠征ではボランチとサイドバック。今回の遠征では、サイドハーフとサイドバックとボランチの3カ所で起用された。
「佐々木はテクニックがあって賢く、状況判断がいいんです。サッカーの理解度が高いからどのポジションをやってもできる」と、高倉監督もその能力の高さをはっきりと認めている。
本人は、アメリカと今回の遠征の手応えについてこう話す。
最も多くのポジションで起用された佐々木最も多くのポジションで起用された佐々木
「周りとの距離感がよくなったこととポジショニングがよくなったこと。攻撃でも守備でも周りの位置を確認して、相手の位置も見えてからボールを受けられるようになりました。今後は最後のスルーパスの質、パスの精度を上げていきたい。球際も強くなりたいし、走力もつけたいです」(佐々木)
一方、初めてのポジションで奮闘したのが、左サイドバックの國澤だ。
前半こそポジショニングに戸惑う場面もあったが、高木のサポートも受け、相手選手との競り合いでは球際の強さも見せた。
初めてのポジション(左サイドバック)で奮闘した國澤初めてのポジション(左サイドバック)で奮闘した國澤
「サイドバックの仕事について周りの選手からいろいろと教えてもらっていたんですが、頭がパンパンで。それを1こずつ、オフの時間から整理しながらゲームに入りました。スピードがある相手だったので裏のケアをして、自分のマークも見ながらラインも揃えないといけないので、そこが難しかったです。日本代表のユニフォームを着ているので、恥ずかしいプレーはできないなと思いました。課題ばっかりで楽しむ余裕はなかったんですけれど、自分が今やれることを精一杯やれたかなと思います」(國澤)
若手だけではない。経験のある阪口、熊谷、永里、川村も、アメリカ遠征とは違う新たなポジションに挑戦し、新境地を拓いた。右サイドバックの有吉はポジションこそ一定だったが、サイドハーフやボランチなど、周囲のメンバーが変わる中でも柔軟に対応した。
柔軟な対応を見せた有吉柔軟な対応を見せた有吉
【本当の競争はこれから】
今回の遠征で選ばれたメンバー中、唯一試合に出場しなかったのがGK平尾知佳だが、平尾はU-20日本女子代表のメンバー候補でもあり、本当の意味で代表入りを狙うチャンスは、アンダーカテゴリーを卒業する来年以降十分にあるはずだ。
高倉監督が指揮を兼任するU-20日本女子代表には、10代の前半から高倉監督の指導を受け、その高倉サッカーの「イズム」をよく理解した選手たちが多い。そう考えると、11月のU-20女子W杯以降にこの年代がなでしこジャパンに登用される可能性はある。本当の競争はそこから始まると言ってもいい。
チームは生き物のようなものだ。
今のなでしこジャパンは、試行錯誤の中で様々な変化を受け入れながら、その内部では大きな地殻変動が始まっている。
松原渓 スポーツジャーナリスト
偉そうにサッカーを語るのも烏滸がましいが、(おこがましいが)
ある意味、
天国(ワールドカップ優勝)から地獄とは言わないけれど、
転落して、出口が今は見えない?状況の中、
高倉監督に全て?を託したなでしこ。
もし男子チームの監督であれば、
なかなか結果の出ない新監督に対する風当たりは、
もう少しハードであってもおかしくないのだが、
現状は、世間の目が優しいというよりは、
無関心?という気がするのは私だけだろうか?
正直誰が監督となろうとも、
なでしこの成績が良くなれば、
それでいいとは思うのだが。
高倉監督の方針で、
私が一番気に入っているのは、
彼女のスタイルというか、
選考の基準が、隅々まで行き届いている?
ように見えることも素晴らしいのだが、
一つのポジションに甘えさせることなく、
色々なポジションに挑戦させるそのフレキシブルさ。
それは彼女の最大の長所だと思っている。
下に引用した記事からも読み取れるのだが、
(長すぎて読む気がない方はもちろんそれで結構ですが)
チームのレベルを上げるために、
できる限りの事を試してくれる監督。
例えば、
いつも同じ選手を使い、戦術も同じ。
それで結果が出なくて監督を変えてお茶を濁す。
過去の日本代表にありがちだった状況。
でも、高倉監督はきめ細やかな?で斬新な選考。
もちろんすべてのファンに納得の選考などできるわけではなく、
だからこそ、監督の方針に一本芯が通っていれば、
落選の選手も納得?できるし、
選ばれた選手も責任感が出るし、
あるいは入れ替えが明確なことで、
頑張れるのでは?
そして何より、
印象的なのが、選手のポジションのコンバート。
選手の力を最大限に発揮させ、
チームを機能させ、
そしてレベルを上げることを目標としたコンバート。
FIFA U-17女子ワールドカップで優勝した時のメンバーの、
柔軟性?
U-17女子W杯で決勝進出…“リトルなでしこ”快進撃の理由
文/池田敏明
コスタリカで開催されているU-17女子ワールドカップにおいて、U-17日本女子代表が決勝進出を果たした。ここまで5試合を戦い全勝で、21得点1失点と圧倒的な実力を発揮している。彼女ら“リトルなでしこ”の試合を見ると、他国と比べて2ランク程上のレベルでプレーをしているような印象を受ける。強さの要因として浮かび上がってくるのは、“柔軟性”というキーワード。リトルなでしこの選手たちは、あらゆる側面において柔軟性を備えているのだ。
まず、複数のポジションをこなせる選手が多いことが挙げられる。準決勝のベネズエラ戦では、後半に左SBの北川ひかるが相手との接触で負傷するアクシデントに見舞われた。通常なら同じポジションの選手を投入する場面だが、高倉麻子監督が切ったカードは、FWの齋原みず稀。彼女をワントップに入れると、FWで出場していた小林里歌子を左SH、宮川麻都を一列下げて左SBに入れた。小林はチームのエースストライカーだが、サイドでの起点作りやドリブルからのチャンスメークもできるため、SHでも十分に機能する。宮川も機動力と体幹の強さを生かして相手の強力アタッカー陣に対応し、守備力の高さを示した。
他にも、今大会で右SHと左SBをこなしている松原志歩や、FW登録ながらCBとしてプレーする大熊良奈と、ポリバレント性を備えた選手が揃う。フォーメーション変更や不測の事態にも、柔軟に対応できる強みを持つ。
以下略
これが日本の強みとする監督の采配。
これがトップチームでも発揮できれば、
復活の日は近いと思う。
だからこそ、2年くらいは我慢の日でも、
私は待っていられるのだが。
「攻守で噛み合わず…」スウェーデンに完敗のなでしこ 高倉監督の試行錯誤は続くのか
Football ZONE web 7月22日(金)6時40分配信
試行錯誤の続く高倉ジャパンの初勝利はお預けになった。現地時間21日になでしこジャパンは、リオデジャネイロ五輪に出場する強豪スウェーデンとアウェーで国際親善試合に臨み、後半に3点を奪われて0-3の力負けを喫した。
高倉麻子監督は「新しいことにチャレンジするなかで、自分たちが想像したような試合運びにはならなかった。一人一人の判断やテクニックはまだまだ上げなくてはいけないと感じた。走られてもいたし、サイドでも起点を作られた。全体にうまくいった試合展開ではなかった」と振り返った。
その言葉を裏付けるように、就任から3試合目での試行錯誤の痕跡はいくつも見えた。これまで不動のセンターバックだったDF熊谷紗希(リヨン)を中盤の底に配置し、ボランチが本職のMF川村優里(仙台)をセンターバックに配置してスタート。4-1-4-1システムの左の2列目にFW永里優季(フランクフルト)を起用し、1トップには小柄だが機動力のある増矢理花(INAC)を配置した。
しかし、序盤に主導権を握られると新システムは頓挫。2列目に入っていたMF阪口夢穂(日テレ)を下げたダブルボランチにしてゲームを落ち着かせた。その後は主導権を奪い返したもののゴールは奪えなかった。逆に後半に入ると全体的にチグハグなプレーも目立ち、同31分から立て続けの3失点で完敗となった。
「個人個人を試さなければいけない難しさ」
「チーム全体としての守備も攻撃もいろいろなところで噛み合っていない。個人個人を試しながらいかなくてはいけない難しさもあるが、下を向かずに良いところと悪いところを見ながらやっていきたい」
高倉監督は苦悩の胸の内をこう語った。2011年ドイツ女子ワールドカップ優勝メンバーからの世代交代が一つの課題とされるなかで、選手選考を進めつつ高倉イズムを植え付けていくという壁にぶつかっている。6月のアメリカ遠征2試合に続き、敵地で強豪との戦いを経験し、MF佐々木繭(仙台)ら新戦力も台頭している。チームの形を探りながら、まずは初勝利に向けて進んでいきたい。
フットボールゾーンウェブ編集部●文 text by Football ZONE web
スウェーデン遠征2試合目。クラブチームとのトレーニングマッチを通じてなでしこジャパンがトライしたこと
松原渓 | スポーツジャーナリスト 2016年7月26日 1時39分配信
【なでしこジャパン初勝利】
21日にスウェーデン女子代表との試合を終えたなでしこジャパンは、中2日で第2戦を迎えた。
毎日暑い日が続いているが、この日のキックオフは14時。炎天下のコンディションの中で試合は行われた。
第2戦の相手は、スウェーデン女子サッカー1部リーグ(ダームアルスヴェンスカン)に所属するクリシャンスタッドDFF。15歳~32歳まで、学生と社会人が混在したセミプロチームである。本来ならスウェーデン女子代表と2試合を組めれば理想的だったのだが、リオデジャネイロ五輪を間近に控えるスウェーデン側の事情もあり、クラブチームとの練習試合が組まれることとなった。
クリシャンスタッドDFFはクラブチームで、スウェーデン女子代表よりも個々のレベルは当然落ちる。だが、3人目の動きで裏に走らせるカウンター攻撃など、戦い方ははっきりしており、その点は日本にとって、スウェーデン戦の反省を生かす良い機会だったと言える。
日本のスタメンは、GK山根恵理奈、DFは左から國澤志乃、高木ひかり、村松智子、有吉佐織。ダブルボランチに熊谷紗希(キャプテン)と佐々木繭を置き、MFは左に田中美南、右に永里優季、トップ下に阪口夢穂、1トップに横山久美をおく4-2-3-1。
スウェーデン戦では縦に長いロングボールを蹴ってくる相手に対し、ボランチに下りてゲームを作る場面が多かった阪口だが、この試合の前半は高い位置で攻撃の最終局面の仕事に集中していた。
裏のスペースを狙い続けた阪口裏のスペースを狙い続けた阪口
だが、阪口が上がったことで、マイボールにした後にボールを落ち着かせるポイントがなかなか作れない。その結果、序盤は落ち着かない展開となった。スウェーデン戦で課題として上がっていた選手間の距離感は改善されたようにも見えたが、出し手と受け手のイメージが合わず、パスの精度も欠いてしまう。
35分には左サイドの連携から横山のボレーシュートが枠の左隅を捉え、44分には阪口、永里、横山とテンポ良く回して飛び出した阪口が決定機を迎えたが、いずれもGKの飛び出しとファインセーブに阻まれゴールならず。最終ラインから一発で裏を狙ったパスから決定機を迎える場面もあったが、すべてオフサイドにかかり、スコアレスで後半を迎えた。
攻撃の質が上がらない理由について、指揮官は、個々の状況判断とテクニックの物足りなさを口にした。
「前半は特に、動きを止めて足元で受けてしまっていました。相手もあることなんですが、あれぐらいのプレッシャーの間で自由にプレーができないとなると、どんな相手にも点は取れないと思います。もうちょっとテクニックの部分を上げていかないと、狙っているサッカーを実現するのは難しいと感じます」(高倉監督)
テクニックと言っても、足元の技術だけではない。駆け引きで相手を外す動きや、屈強な相手に寄せられた時に簡単に倒れないのも必要なテクニックだ。それは、連携以前の問題と言えるのかもしれない。
ハーフタイムには田中に代えて左サイドにMF中里優を投入し、CBの村松に代えてFW増矢理花をワントップに投入。熊谷と阪口を一列ずつ下げて、これまでなでしこジャパンがベースとしてきた4-4-2にすると、一気に安定感が増した。クリシャンスタッドは前半に飛ばしすぎたのか、後半は動きが止まり、日本が押し込む時間が続く。
機動力のある中里と増矢が積極的にボールに絡みながら、攻撃にアクセントを与えていく。中盤では阪口がゲームをコントロールし、ボランチを組む佐々木も積極的に攻撃に絡めるようになった。CBでは熊谷とともに、2回目の招集となった高木ひかりが安定したラインコントロールを見せた。
そして50分、阪口のパスを受けた中里が左サイドでターンすると、鋭く右足を振り抜き、ゴール右上に技ありのゴールを決める。
ゴールを決めて祝福を受ける(中里は背番号24)ゴールを決めて祝福を受ける(中里は背番号24)
ガッツポーズを見せる中里に、周囲の選手たちが走り寄って祝福を浴びせた。その後、後半の早い段階で永里に代えて右サイドに千葉園子を投入し、横山に代えて有町紗央里を投入。千葉が持ち味の運動量を生かして前線から追い、高い位置でボールを奪ったところから佐々木のミドルシュートがゴールをかすめるシーンもあった。
追加点は75分。左サイドで有町が仕掛けて打ったシュートがバーに弾かれるが、こぼれ球を千葉が頭で押し込んで2-0と引き離す。プレッシャーから解放されたように、千葉の笑顔が弾けた。
さらに、佐々木や増矢も積極的にシュートを放つなど、追加点が生まれそうな気配も漂う。終盤には左サイドバックに京川舞(←國澤)、ボランチに川村優理(←佐々木)を投入し、積極的な選手起用をしたなでしこジャパンが2-0で勝利を飾った。
【アメリカとスウェーデン、2つの遠征を通じて見えたもの】
なでしこジャパンはスウェーデン遠征を1勝1敗で終えた。
クリシャンスタッド戦の後半、慣れたポジションとシステムに変えてからはバランスが良くなり、日本の一方的なペースになった。だが、それは予測できたことでもあった。同じ4-4-2のシステムとポジションでスウェーデン女子代表戦に臨んでいたら、あるいは結果ももう少し変わっていたのかもしれないが、それでは未来への成長はありえない。
もちろん、代表チームにとって負けて良い試合は一つもないし、実際、高倉監督は常に勝負に対する強いこだわりを見せてもいる。だが、その中で「安定」は求めていない。今は選手個々の能力を見極めながら、3年後のW杯、4年後の五輪に向けて、若手にもベテランにも刺激を与えて成長を促し、チームの枠組みを作っていく時期でもあるからだ。
そして、6月のアメリカ遠征と今月のスウェーデン遠征でチームとして積み上げられたこともあれば、新たな課題も浮き彫りとなった。様々なチャレンジをする中で、個人とチームの「現在地」が明確になった分、やらなければならないことはさらに山積みになった感じもある。
まず、指揮官が先に挙げた個々の技術面での成長は継続的なテーマとなるだろう。
「形を決めてやっているわけではないので、変わりうる状況の中で、いろんなアイデアを持ちながら、相手の変化に対して自分のアイデアも変化させていける、そういう柔軟性を選手には求めていきたい。無難に止めて、とられないようにして、つないで、ということはやってくれているんだけど、もっと動きのあるサッカーを目指しています」(高倉監督)
芝の重さや、対戦相手の身体の大きさやスピードなど、国内では体験できないこともある。それは頭で分かっていても、実際にピッチで対戦してみないと分からないものでもある。今回の遠征に参加した新たな選手たちは、貴重な経験を日々のトレーニングにも生かしてくれることを期待したい。
また、多くの選手が普段やっていないポジションで起用された。それは、その選手がプレーの幅を広げるチャンスを与えると同時に、与えられた場所で何ができるかということを、見極めるテストでもあった。
「いろんな状況の中で何を判断して、何を描くかということが大切で、ポジションは関係ないと思うんです。持っているものが高く、いろいろなことを表現できる選手を集めてチームを作っていきたいと思っています。新しく呼んでいる選手の中で数名は計算できて、ある程度やっていけることが分かりましたし、1ヶ月前のアメリカ戦よりも成長していると感じた選手もいました」(高倉監督)
【新戦力の選手たちが見せた可能性】
新しい選手たちの成長は、今回の遠征の最大の収穫とも言えるだろう。
まず、2試合目で先制ゴールを決めた中里。アメリカ戦ではボランチでプレーしたが、今回はサイドハーフとトップ下でプレーした。ボランチとしては守備面の球際の強さが持ち味だが、今遠征の2試合では攻撃面で、日本のアクセントにもなっていた。
攻撃のアクセントになった中里攻撃のアクセントになった中里
「ボールを持ったら積極的にゴールに向かって仕掛けようと思っていました。スウェーデン代表戦で似たような形があって外してしまったので、今回は決められて、結果を出せて良かったです。課題はたくさんありますが、今後は苦しい試合展開の中で違いを出せるような選手になりたいです。私はスピードとパワーがないし、個で打開できるようなタイプではないので、機動力と運動量を生かして相手が嫌がるようなプレーをしていきたいです」(中里)
2点目を決めた千葉は、ゴールについて「ほとんど(有町)紗央里さんのゴール」と感謝したが、限られた時間でいくつかの決定機に絡んだ。
「大切な試合の前の日は緊張して眠れない」というほど、常に緊張と戦っている千葉だが、遠征の中で様々な貴重なアドバイスを受け、自らの殻を破りつつある。
殻を破りつつある千葉殻を破りつつある千葉
「高倉監督と大部コーチとお話していて、1つシュートを決めることで自分の自信につながるし、クロスを仲間が決めてくれたらそれが自分自身の自信になるから、と。今日のゴールが自信になったかはまだ分からないですけれど、ちょっとだけ見えたかなと思います。私はなんでも全力でがむしゃらにやってしまうんですけど、全部を全速力でやるから周りが見えていないことも分かりました。(阪口)夢穂さんから、『うちやったら、50%、50%でターンしている。それがうちのあかんところかもしれないけど、そういう余裕を持った方がいいんちゃう?』と言われて。ほんまやー!と。自分にもっと余裕を持たないといけないですね」(千葉)
また、今回の遠征で最も成長を感じさせたのが佐々木だ。アメリカ遠征ではボランチとサイドバック。今回の遠征では、サイドハーフとサイドバックとボランチの3カ所で起用された。
「佐々木はテクニックがあって賢く、状況判断がいいんです。サッカーの理解度が高いからどのポジションをやってもできる」と、高倉監督もその能力の高さをはっきりと認めている。
本人は、アメリカと今回の遠征の手応えについてこう話す。
最も多くのポジションで起用された佐々木最も多くのポジションで起用された佐々木
「周りとの距離感がよくなったこととポジショニングがよくなったこと。攻撃でも守備でも周りの位置を確認して、相手の位置も見えてからボールを受けられるようになりました。今後は最後のスルーパスの質、パスの精度を上げていきたい。球際も強くなりたいし、走力もつけたいです」(佐々木)
一方、初めてのポジションで奮闘したのが、左サイドバックの國澤だ。
前半こそポジショニングに戸惑う場面もあったが、高木のサポートも受け、相手選手との競り合いでは球際の強さも見せた。
初めてのポジション(左サイドバック)で奮闘した國澤初めてのポジション(左サイドバック)で奮闘した國澤
「サイドバックの仕事について周りの選手からいろいろと教えてもらっていたんですが、頭がパンパンで。それを1こずつ、オフの時間から整理しながらゲームに入りました。スピードがある相手だったので裏のケアをして、自分のマークも見ながらラインも揃えないといけないので、そこが難しかったです。日本代表のユニフォームを着ているので、恥ずかしいプレーはできないなと思いました。課題ばっかりで楽しむ余裕はなかったんですけれど、自分が今やれることを精一杯やれたかなと思います」(國澤)
若手だけではない。経験のある阪口、熊谷、永里、川村も、アメリカ遠征とは違う新たなポジションに挑戦し、新境地を拓いた。右サイドバックの有吉はポジションこそ一定だったが、サイドハーフやボランチなど、周囲のメンバーが変わる中でも柔軟に対応した。
柔軟な対応を見せた有吉柔軟な対応を見せた有吉
【本当の競争はこれから】
今回の遠征で選ばれたメンバー中、唯一試合に出場しなかったのがGK平尾知佳だが、平尾はU-20日本女子代表のメンバー候補でもあり、本当の意味で代表入りを狙うチャンスは、アンダーカテゴリーを卒業する来年以降十分にあるはずだ。
高倉監督が指揮を兼任するU-20日本女子代表には、10代の前半から高倉監督の指導を受け、その高倉サッカーの「イズム」をよく理解した選手たちが多い。そう考えると、11月のU-20女子W杯以降にこの年代がなでしこジャパンに登用される可能性はある。本当の競争はそこから始まると言ってもいい。
チームは生き物のようなものだ。
今のなでしこジャパンは、試行錯誤の中で様々な変化を受け入れながら、その内部では大きな地殻変動が始まっている。
松原渓 スポーツジャーナリスト