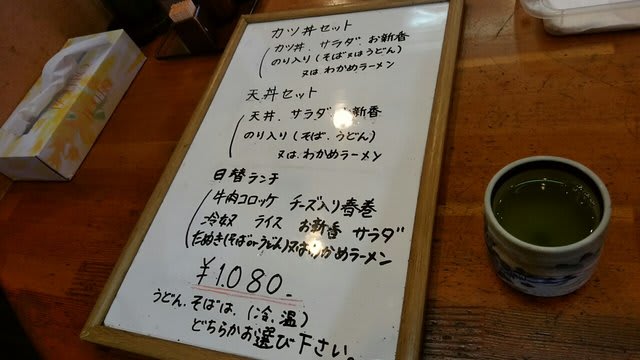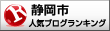高校総体女子サッカーにおいて、藤枝順心高校は初戦敗退となってしまった。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190729-00000033-at_s-socc女子サッカーの場合、そもそも、女子サッカー部がある学校自体が少なく、従って、高校総体であっても、16校しか出場していない。昔ほど、得点差がつかなくなったけれど、それでも今年も7-0と言う試合はあった。そこだけ注目する気はないけれど、まだまだ底辺の広がりが不足している女子サッカー。男子と同じように各県代表がそろう状況になって欲しい。
スポーツ庁が2018年10月に実施した調査によると、主に高校を管轄する都道府県では、16都道府県(34.0%)が活動時間を、14都道府県(29.8%)が休養日を、国のガイドラインよりもゆるく設定していた(『毎日新聞』東京夕刊、2019年2月28日)
と言うような記事を見つけた。
そもそもガイドラインには法的な拘束力はなく、また違反した場合に何らかのペナルティが課されるわけでもない。したがって、国や自治体がいかなるガイドラインや方針を示そうとも、個々の学校や部活動がそれに従うとは限らない。
名前の通り、スポーツ長が示した指針であり、
法律ではないので、従う義務はない。
そこで以下のような実態が報告されているようだ。
ガイドライン破りの実例
(1) 闇部活
・早朝や土日の練習を自主的な活動とみなす
・保護者会等が活動を管理する(看板の掛け替え)
(2)「大会」の活用
・大会前の特例を利用する
・多くの大会に参加したり、大会を新たにつくったりする
(3) その他
・準備や後片付けは、活動時間外として取り扱う
・一年間で調整する
ここで考えなければいけないことが部活の意義である。
「中体連が終わり、改めてR中の選手へ」
大人の見栄?自己満足のために部活を利用していること。
自分の学校が強くなれば、
校長をはじめとする先生方の評価が上がり、
選手たちのためと言う隠れ蓑を利用して、
自分たちの自己満足を押し付けている?
相当過激なことをわざと言っているが。
前のブログにも書いたが、
目指すもの、目標を達成させることが成功で、
未達成を失敗と考える指導者が多い。
例えば、県大会、全国大会へ連れていってあげたいと言う目標が、
いつしか連れていってやるに変わり、
俺の言うことを聞けに変わってしまう。
練習が不足して上の大会にいけなければ、
自分の評価が下がってしまう?
そう思っているかのように、
無理やりいい選手を集めたり、
一杯練習させて、思うような練習をしない選手はは怒って、
無理に練習させる。
大義名分はお前のために怒ると言うが、
実態は良い成績をあげて自分の評価をあげるためである。
もちろんすべての指導者がそうだとは思っていない。
ほんの一部の指導者なのはわかっている。
熱心と無謀は紙一重である。
以前ある県外の遠征してきた選手に聞いた時、
休みは正月の3が日だけで、
全ての休みの日は、練習か試合か遠征だと言っていた。
もちろん顧問の先生の大変さは想像以上だろうが、
それを先生はどう考えて実行しているのか?
だからこそ、このガイドラインが生まれたのだが。
先日、R中も出場した県大会。
中体連としての県大会は初めて観戦したので、
比較ができないけれど、
私が予想したレベルから考えると、
ガイドライン実行に伴う到達レベルは、
かなり下がっているように感じた。
それがいけないとは思わない。
平等であれば問題はないと思う。
ただ、自分で頑張りたい選手が、
自主的に練習をしようとするとき、
当然参加するであろう、クラブチームでの練習が、
どこまで許容されるのか?
中学生の本業はあくまでも勉強であり、
社会生活のルール習得や、基礎的学力の習得。
もっともっといろいろあるでしょうが、
大人になる準備が一番のはずなのですが。
まだまだ始まったばかりのガイドライン。
更に進化していくのでしょう。
私の考えが絶対正しいとは思わないが、
ずっと見守っていかなくてはいけない事ではあるでしょう。
「部活のガイドラインの現状?について」
「部活の状況」
「部活動について」
「部活ガイドラインの抜け道「闇部活」と「自主練習」の違いは何か。
内田良先生の発表を参考に
https://news.yahoo.co.jp/byline/kiyokotaniguchi/20190730-00136249/」