エネルギー価格の上昇と温暖化問題の顕在化によって原子力発電の人気が高まってきました。米国が新設を再開するなど、世界的に拡大の方向が見られます。反原発運動の「教祖」であったドイツでも従来の全廃方針を見直す動きがあるそうです。原発のリスクに比べ必要度が高ければ、導入しようという合理的な判断でしょう。
一方、日本では次のような事情が生まれています。
『経産省の調査によると、1994年度に1739人と最多を数えた国立大学の原子力関係学科の学生数は、2006年度に137人と、10分の1以下にまで落ち込んだ。学科再編で学科名から「原子力」が消えて統計から抜け落ちた影響もあるものの、人材供給の先細り傾向は既に「危機的な状況」(資源エネルギー庁幹部)にある』(1/6北海道新聞)
不人気の背景には日本特有の「原子力アレルギー」、そして「原子力は危険」との印象をばら撒いてきた主要マスメディアの不断の努力があります。
反原発報道は原発を止めることはできませんでしたが、学生の意欲を殺いで、人材の供給を止めるという長期的な成果を勝ち取ることができたというわけです。
原発の是非は徹底的に技術的なリスク評価をした上で、議論すべき問題ですが、現状の反対論はそうではありません。例えば、朝日新聞07/03/17のトップ記事には、99年の志賀原発の制御棒落下事故のメカニズムの図解がありますが、その図は高校理科レベルの知識もない人が描いたと思われるもので、理解不能なものです(参考)。
日本を代表する新聞が、この程度ですから、原発反対の運動は多分に情緒的なものだと思われます。最近の例では、柏崎刈羽原発の地震被害の誇張された報道の結果、危険だとしてイタリアのサッカーチームの来日は中止されました。ところが仏の左派系高級紙ルモンドは強い地震によく耐えたと、肯定的に報道したそうです。
ノーベル物理学賞を受けたソ連のP・カピツァは、チェルノブイリ事故の前、ソ連での原発に慎重論を唱え、原発を安心して任せられるのは几帳面な日本人とドイツ人だけだと述べたそうです。不幸にしてこの予言は的中しました。
日本人の原発管理能力が認められたのですが、優れた人材があってこその話です。人材不足によって管理能力が低下すれば、事故の起きる可能性は高くなります。大事故が起きたとき、原発反対を推し進めた人たちは、自分たちの行為が原発技術者の人材不足を招いたことを忘れ、「それ見たことか」と胸を張るのでしょうか。
一方、日本では次のような事情が生まれています。
『経産省の調査によると、1994年度に1739人と最多を数えた国立大学の原子力関係学科の学生数は、2006年度に137人と、10分の1以下にまで落ち込んだ。学科再編で学科名から「原子力」が消えて統計から抜け落ちた影響もあるものの、人材供給の先細り傾向は既に「危機的な状況」(資源エネルギー庁幹部)にある』(1/6北海道新聞)
不人気の背景には日本特有の「原子力アレルギー」、そして「原子力は危険」との印象をばら撒いてきた主要マスメディアの不断の努力があります。
反原発報道は原発を止めることはできませんでしたが、学生の意欲を殺いで、人材の供給を止めるという長期的な成果を勝ち取ることができたというわけです。
原発の是非は徹底的に技術的なリスク評価をした上で、議論すべき問題ですが、現状の反対論はそうではありません。例えば、朝日新聞07/03/17のトップ記事には、99年の志賀原発の制御棒落下事故のメカニズムの図解がありますが、その図は高校理科レベルの知識もない人が描いたと思われるもので、理解不能なものです(参考)。
日本を代表する新聞が、この程度ですから、原発反対の運動は多分に情緒的なものだと思われます。最近の例では、柏崎刈羽原発の地震被害の誇張された報道の結果、危険だとしてイタリアのサッカーチームの来日は中止されました。ところが仏の左派系高級紙ルモンドは強い地震によく耐えたと、肯定的に報道したそうです。
ノーベル物理学賞を受けたソ連のP・カピツァは、チェルノブイリ事故の前、ソ連での原発に慎重論を唱え、原発を安心して任せられるのは几帳面な日本人とドイツ人だけだと述べたそうです。不幸にしてこの予言は的中しました。
日本人の原発管理能力が認められたのですが、優れた人材があってこその話です。人材不足によって管理能力が低下すれば、事故の起きる可能性は高くなります。大事故が起きたとき、原発反対を推し進めた人たちは、自分たちの行為が原発技術者の人材不足を招いたことを忘れ、「それ見たことか」と胸を張るのでしょうか。










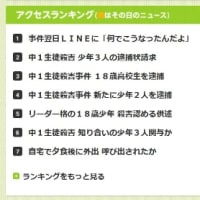

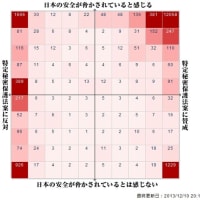
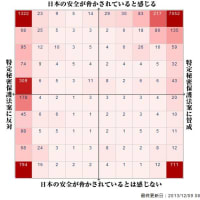
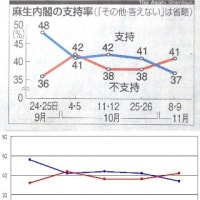
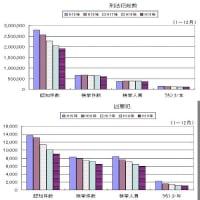
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます