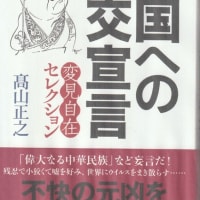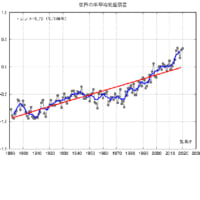「古代史の謎は『海路』で解ける」(長野正孝著 PHP新書 2015年1月刊行)は古代史ファンにとって非常に面白い。中でも私が最も興味深く読んだ部分を紹介する。
古事記・日本書紀(記紀)によれば、神武天皇は日向から何年もかけて図のようなルートを辿って大和に到着したことになっている。

ところが、長野氏は雄略天皇(5世紀)の時代までは、日本に存在したのは手漕ぎの刳り舟(丸木舟)であって、それでは瀬戸内海を渡れないと主張する。すなわち、
(1)瀬戸内海は穏やかな海のように見えるが、潮流の流れが速い。その速度は人間が漕ぐ速度の何倍もあり、潮に逆らって進むことはできない。手漕ぎ舟ではせいぜい時速4-5キロだが、潮流の速度は関門海峡で時速17キロ、明石海峡で12キロである。
(2)何日もかけての旅だから、途中で水や食料を補給する必要があるし、荒天ならば陸地で待たなければならない。しかし、当時はそのような施設つまり港は瀬戸内海には存在しなかった。
(3)陸地に近づけば沿岸の住民から攻撃されるし、沿岸には岩礁もあり、水先案内人が必要である。
記紀には神武の一行の人数に関する記述はないが、近畿に到着してから、ニギハヤヒの命と戦ったとあり、神武の軍勢は少なくとも数百人はいたであろう。そんな多人数で(1)(2)(3)の難題を解決することはできない。
したがって、神武東征は四―五世紀の出来事ということになり、それでは神武天皇の存在そのものが疑問になる(とまでは長野氏は言っていないが)。
記紀の編纂者(八世紀)は瀬戸内海の航路が整備されたのちの姿しか知らなかったために、現実にはありえないストーリーを創作したのである。
では瀬戸内海の海路は誰がいつ開発したのか。長野氏は、その人物は雄略天皇で吉備の乱(463年)の時に、その地域の地方勢力を制圧してからだと推測している。古事記によれば、神武天皇は安芸の国で7年、吉備の国で8年過ごしたとあり、長野氏は海路開発にはその位の時間がかかるから、日本書紀を編纂した舎人親王はその故事を神武天皇に重ね合わせたと推測している。
しかし、それでは雄略天皇以前の各天皇はどうやって九州から大和に移住したのかという疑問が生じて、わけがわからなくなる。長野説はそれ自体に矛盾があるのではないか。