
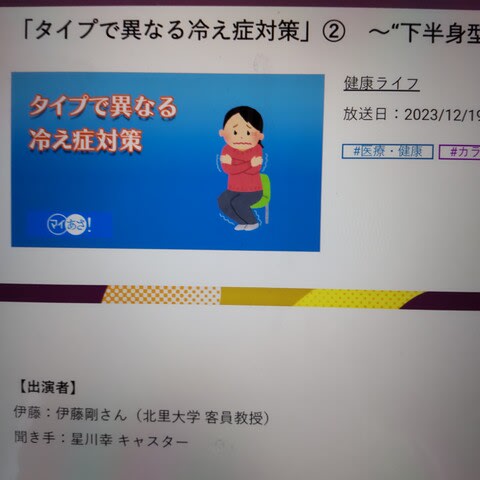
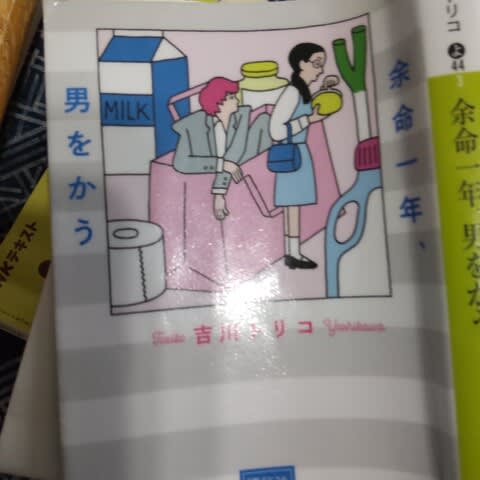

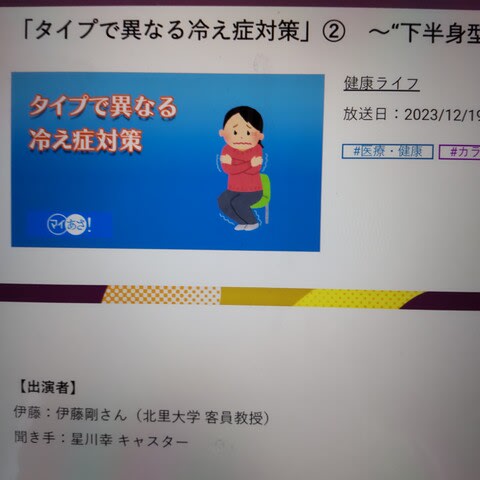
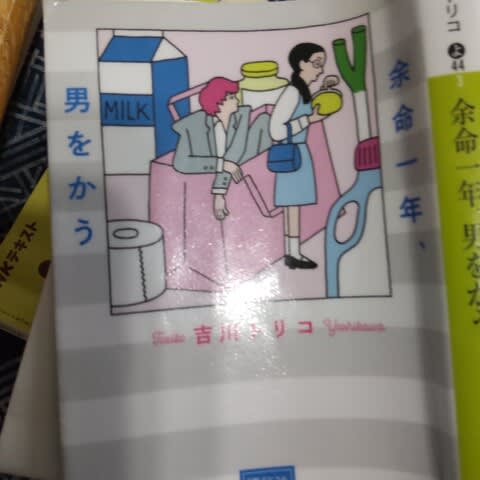
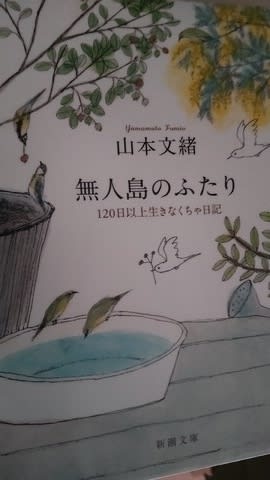

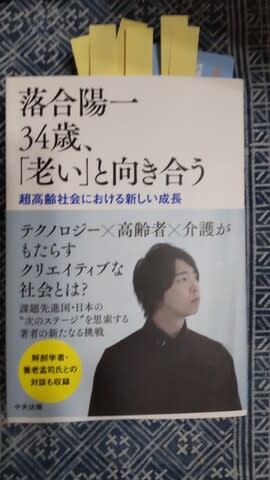
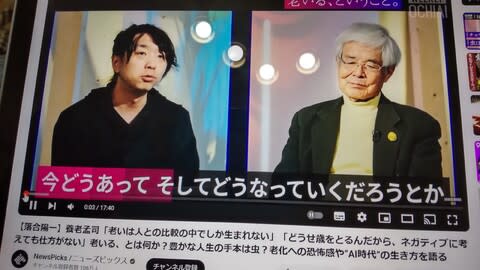
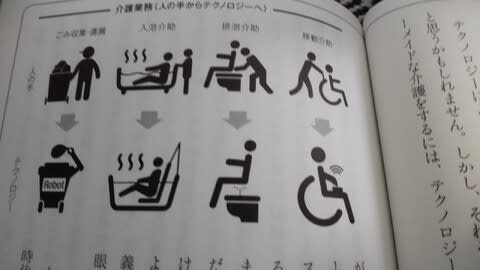




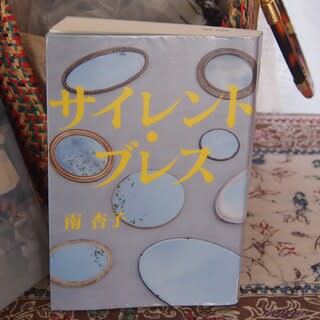
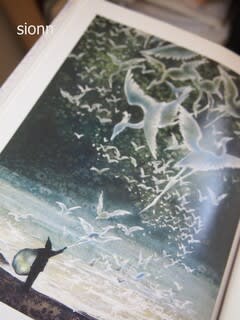


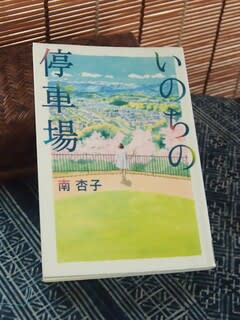
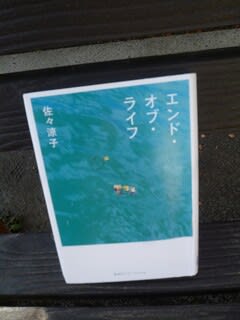


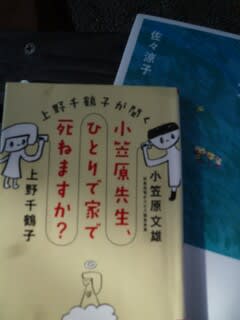
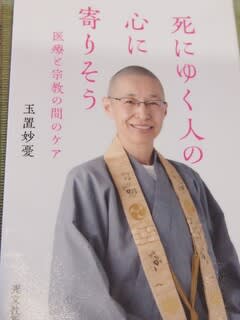






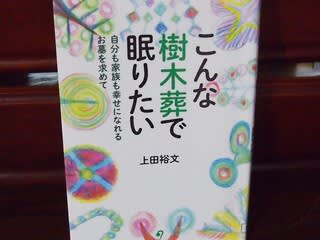




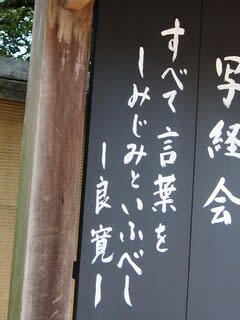











「人生が二度あれば」という
井上陽水の歌があります。
「~~今年の二月で父は64~~♪」
72年の作品だから、私はまだ21歳。
64歳の人のことなど、
想像もできませんでした。
それ以上に、父親や母親のことを
この歌のようにいたわる気持ちさえ
抱いていませんでした(
そんな私も、歌の父親の年齢をはるかに
超えて68、「今年の0月で69♪」
とても面白い本を読みました。

「リプレイ」(ケン・グリムウッド・新潮文庫)
43歳のある日あるとき、
心臓発作で突然死。
目が覚めてみると、
1963年、18歳の時に戻っている。
これを繰り返すこと4回。
よくあるタイムスリップものではありますが、
毎回、前の人生で後悔したり、
やりたかったことを次々と実現していく。
この繰り返しのデティールがなんとも
正確で、興味深い。
ケネディの暗殺、国家間の軋轢~~。
と書くと硬い内容のように見えますが、
メインテーマは愛、
セックスシーンもふんだんで、
これも真実味がありますよ。

私も文庫版の表紙を真似て作ってみました。
ワタクシのタイムトリップは、
大盤振る舞いして48年!
目覚めると20歳!
時を超えるBABA~~♪
小説の主人公は、60年代に戻ると、
その時代の競馬やらフットボールの賭けで、
莫大なお金を得る。
結果をすでに知っているので、
間違いはない~^。
その上に、アップルとか将来伸びる会社の
株をどんどん買うわけです。
これでどんな人生でもお金の心配は
なくなる~~。
お金の心配がなくなった上で、
人は、この人生で何を成すのか~~。
が、テーマかな
それにしても、
何度も43歳になって、
その都度、再び18歳。
前の時代に生きた記憶はあるけど、
妻も娘もそのたびに失う。
喪失することの無量の悲哀~~。
ちょっと哲学的な課題になっていくところが
それがほかのタイムトリップものと違う。

この小説、前にも読んでいるのですが、
今回改めて読んで深く、深く感情移入。
私は、何度生き直したいだろうか。
でも一回きりの人生を生きる
ワタシたちだって何度も生まれ変わる。
耐えがたい苦痛や悲しみを経験すると、
人は一度「死ぬ」のだと思います。
一度死んで、また生き返って、
次の人生に向かって歩いていく。
だから人は本当は何度も生まれ変われる
はずなんですね。
で、今回の私は、20歳くらいに勝手に
生き返ることにしました。
この本を読んで、ぐっすり寝ます。
目が覚めたら、20代!
上京したばかりの頃の部屋は四畳半一間。
今目覚めると~~、
なんと、当時の部屋より部屋が広い!
ラッキー!!
これからは20代のつもりで
子どもを産むまでの14年間を
一人暮らし、します!
楽しみだああ。
主人公のジェフは、’45年生まれだから、
現在74歳、生きていたらどんなシニアに
なっているんでしょうね。
応援ポチ
ありがとうございます。
励みになります。