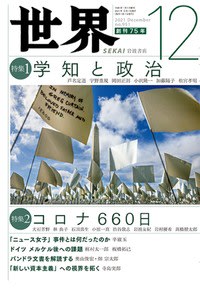小岩の『世界』11月例会の報告
11月18日(木)、午後7時より、小岩の『世界』を読む会・11月例会がzoomのオンラインで開催されました。4名の参加でした。
在宅でゆったりやりたいだけやる会で、今回も11時までの長丁場。この会では早い方です。
という訳で、たっぷり話したいだけ話す会で、楽しく深い(?)ものですが、記録をして起こすのはしんどいので、頭に残ったことだけ記録させていただきます。
■ 今月のテーマは
・「対テロ戦争の時代を超えて」 栗田禎子
・「対テロ戦争とは何だったのか」 谷山博史
・「9・11から二〇年」 中村 佑
・「タリバン復権とアフガニスタンのゆくえ」 山本忠通
・「平等と公平はどう違うのか」 新村 聡
・「関西生コン弾圧と産業労働運動、そしてジャーナリスト・ユニオン」
花田達朗
でした。
・アフガンの戦争に至る冷戦後のアメリカの仕掛けた戦争は、アメリカの3000万人に関わるという軍産複合体、2000万人の退役軍人という構図から、次々と「敵を探す」必要の文脈の中で起きていることだ。
今度は中国だから、アフガンからさらば。
・9.11については、様々な陰謀論があって、怪しい? 旅客機が突っ込まなかった第三のビル崩壊? 現地への攻撃を仕掛けるのには通常六カ月は要するのに、わずか一カ月で行なわれた(準備していた?)。等々。まだ、解明の取り組みは続けられているのだろうか。
・このことで、「誰が儲かったのか?」という見方が本質をあぶり出す。
・戦争には、それで儲かる者が存在する。
・イスラムの女性差別が問題にされるが、遅れた社会では多かれ少なかれ女性差別はあるものだ。
・土本典昭「もう一つのアフガニスタン」という記録映画は、1985年のカブールを撮影しているが、イスラムが抑圧しているというふうではない。
・マスコミの論調は、「失敗した」「上手くいかなかった」というもので「違法な戦争」だったのだとは言っていない。
・軍事兵器の実験場としての戦争、軍事援助の中身はお金ではなく、アメリカの兵器を渡すという実態で、そこには賄賂が絡んで当地の政府の腐敗を招く構造がある。
他にも、いっぱい、話したのですが、頭とノートに残ったのは、アフガニスタンに関することばかりでした。
産業別労働組合が必要なのですが、それを作るというのは、「革命」に近い難しい課題だという話もありました。
次回は、櫻井さんが宮古島支援行動から帰った翌日の開催となるので、お土産の現地報告を楽しみしています。
11月号のお薦めは
■ 大塩 ・「東芝調査報告書と企業社会の危機」 上村達男
・「越境する世界史家(上)」 三宅芳夫
でした。
◎ 小岩の『世界』を読む会、12月例会 の予定
●日 時 12月16日(木) 午後7時
●zoomによるオンライン開催
※ 参加希望者は連絡下さい。
●持ち物 雑誌『世界』12月号
○共通テーマ
・「「ニュース女子」事件とは何だったのか」 辛淑玉
・「日本における学術と政治」 岡田正則
・「メルケルとは何者だったのか」 板橋拓己
● 連絡先 須山
suyaman50@gmail.com