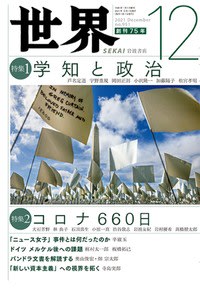富岡『世界』を読む会・11月例会の報告
富岡の会11月例会は、6人の参加で開催されました。
会場の西部コミュ・センターは暖房の効きが悪く、参加者は寒さ対策をしての参加でした。
今回のテーマは『世界』11月号から、特集1「反平等−新自由主義日本の病理」の酒井隆史、新村聡、大沢真理三氏の論考と、国谷裕子さんの内橋克人・追悼文を取り上げました。
この4つの論考と追悼文に共通しているのは、「オルタナティブ(もう一つの世界)を構想する」という筆者たちの強い意志だと思います。
1.酒井隆史『反平等という想念』について
(1)「オメラス」の寓話からオルタナティブ論議を展開した、刺激的で印象深い、説得力のある論考だと評価されました。また、深い哲学的思索のようだ、との指摘もありました。一方、寓話や物語を使って社会科学現象を説明することに、違和感を覚
(2)「オメラス」の寓話から何を読み取れるかについて、酒井氏の解釈にうなずきつつも、次のような疑問が提起されました。
①「このような状況は許せない」と反旗を翻す人=革命家が何故登場しないのか?
②「歩み去る人」=世界を変える、のアレゴリー。世界を変える人が何故、「去る・家出」というネガティブな表現なのか。「オメラスは最早、救い難い社会」という絶望感があるのだろうか。オメラス(日本)から脱出したのでは、何も変わらない。
③いや、去った人々は、オルタナティブ・オメラスを志向するということではないか。
この寓話が短く単純な物語だけに、余計に読者の想像力を刺激してくれます。
(3)ソンピ化したネオリベラリズムのおぞましさが、「見慣れた風景」として描かれている。ブロガーの「オメラス」論、「メンタリストDaiGo」、進化政治学・伊藤隆太助教などの事例。そして、日本のパンデミック対策で日本の新自由主義のおぞましく、倒錯した姿が鋭く指摘されている、と感想が述べられました。「人々の健康を守る制度」の現状維持のために、人々の健康を犠牲にするという倒錯。このことは、「いまある世界以外の世界は不可能」という前提、オルタナティブ拒絶の思想が貫徹されています。
2.新村聡『平等と公平はどう違うのか』について
(1)平等・公平に関する言葉(「数の平等」「比例的平等」、「貢献原則」「必要原則」)が丁寧に整理されており、参加者は一同にこの論考を歓迎しました。
(2)これらの語彙を使って、新自由主義から福祉国家へ転換していく道筋が示され、その具体性・現実性に好感が持たれました。
(3)「図1 雇用形態、性、年齢階級別賃金」の図を見て、性別と正規・非正規での格差の大きさに、思わず嘆息を漏らしました。
(4)生涯賃金格差2億円、1億円の端的な指摘に強く納得し、かつ格差1億円分(教育費・住居費・老後生活費)を社会保障でカバーする、という福祉国家構想に、私たちのオルタナティブの方向性を示されたものとして、受け止めました。
3.大沢真理『生き延びるためのジェンダー平等』について
(1)「災害では女性の死亡が多い」との指摘に、コロナ禍での女性自死者の増加ということともあわせ、ショックを受けたとの感想が述べられました。
(2)コロナ対策が「男性稼ぎ主」型世帯を前提になされたとの指摘に納得、筆者の言う通り、日本の生活保障システムそのものが、まさに「男性稼ぎ主」型システムであることの証拠であることを、私たちは今体験しているのだと思いました。
4.国谷裕子『人が人らしく生きていける社会を‐内橋克人さんが伝えてきた言葉』について
(1)オルタナティブとしての「FEC自給圏」構想が既に、90年代中ごろから提唱され始めていたことに、内橋克人さんの先見性を見出します。
(2)内橋さんがクローズアップ現代に、20年余で46回も出演していたことに、一同驚きました。国谷さんとNHKの踏ん張りに拍手喝采を送りたい気持ちです。国谷さんの「クローズアップ現代」中止、NHK追放の直接のきっかけが、安保法制違憲質問であったとしても、内橋さんの度重なる番組出演は、自公政権にとっては苦々しい日々だったことを想像させます。権力に嫌われる、敬遠される人こそ、真のジャーナリスト。
(3)内橋克人さんの後を継ぐ経済ジャーナリストは誰だろう、との問いかけに、みんな沈黙しました。
(4)衆院選で統一野党はオルタナティブを提起できたのか、との議論がされました。例えば、気候変動問題については、野党の共通公約に対して、与党もメディアも無視するなかで争点化からエスケープされた、との指摘がありました。また、日本社会のなかに、現状の枠組みの中で自分の幸せを求めるという風潮がまん延しているのではないか、との感想がありました。
◎ 富岡の雑誌『世界』を読む会、12月例会 の予定
(2)辛淑玉『「ニュース女子」事件とは何だったのか』