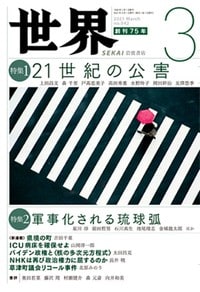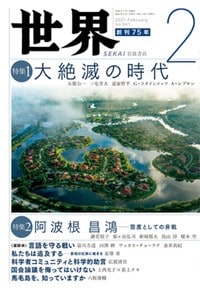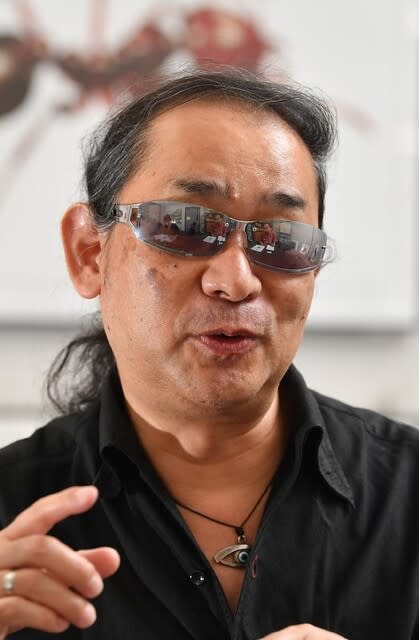2月18日(木)、午後7時から、小岩の『世界』を読む会・2月例会がzoomでのオンライン開催で行われました。体調不良の方が重なり、参加者は3名というコンパクトな会になりましたが、zoomの威力はなかなかで、中身は充実、11時を超えて、「おお、もうこんな時間だ」という4時間になんなんという会でした。
特集1の「大絶滅の時代」の論稿は、『世界』では珍しい自然科学系のもので面白いという感想でした。参加者の実は理科系という方のお陰で、これらの論稿にある考察は珍しいものではなく、DNAの発見以後の教育では一般に伝えられている説ではないかということでした。果たして、日本の高等教育を受けた若者世代は、この認識に立っているだろうか? スウェーデンのグレタと日本の若者の動きを比べると疑問がわきますが。
進化のメカニズムが遺伝子などでのコピーのミスが原因になっての変化、それが多様性を生むという話。「ミス」の効能というか、平板な進歩概念、目的論てきな思考が、反省させられました。
コロナ禍を経た世界が、次の新しい状態に進むのかについて、ITなど技術的な革新ということはあっても大量消費や利便性の追求、欲望の拡大については「戻りたがる」という人間の性がものを言うのではないかという、ちょっと暗い見通しも。日本の「真ん中世代」において、大都市を捨てて、地産地消や定常経済などを思考する動きも確かなものとして出ているよ、という指摘も。三宅さんの「自由と平等のサピエンス史」について、社会科学系の筆者が書いている内容の中には、理科系から見ると論理に無理がある部分が指摘されたのも面白く思いました。
一つの論稿を読む場合にも、読者の知的志向の多様性がより深い読み方を拓くというように、いろんな意味で「多様性」は大切なことで、『世界』を読む会も、「多様性」を担保する場でもあるのかな、などと。
次回は、zoomでなくて、生(なま)の会の予定です。
なお、今回の小岩の2月例会zoomでのオンライン開催の連絡メールを、2月25日(木)予定と間違って送ってしまった事情で、25日にも、zoomでのオンライン開催をする予定です。不完全な集まりになるでしょうが、zoomでのオンライン開催のお試し参加をどうぞ。希望の方は、連絡いただければご案内します。
今回の共通テーマは、
特集1 大絶滅の時代
○「生物多様性とは何か、なぜ重要なのか?」 五箇公一
○「生物多様性条約」 道家哲平
○「人新世の夜明け」 アンドリュー・レブキン
特集2 阿波根昌鴻
○「ガラクタの山を証すること」 榎本 空
でした。
2月号のお薦めは
■ 大塩 ・「オーストラリア・アフガン派遣部隊の戦争犯罪とその衝撃」
杉田弘也
・「韓国検察改革の制度化とその代償」 堀山明子
・「言論統制を進める台湾・蔡英文政権」 本田善彦
■ 櫻井 ・「2050年、カーボンゼロ社会は可能だ」
小西雅子
■ 須山 ・「廃炉への現実的道筋を提起する」 筒井哲郎
でした。
◎ 小岩の『世界』を読む会、3月例会 の予定
●日 時 3月18日(木) 午後7時
●場 所 南小岩8丁目21の8
小岩駅から徒歩約3分
●持ち物 雑誌『世界』3月号
○共通テーマ
・「新たな公害の世紀」 上田昌文
・「プラスチック依存社会からの脱却」 高田秀重
・「不戦の琉球弧へのイマジン」 星川 淳
・「日米一体の巨大軍事基地」 前田哲男
● 連絡先 須山
suyaman51@mail.goo.ne.jp