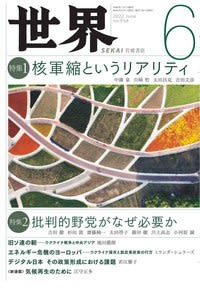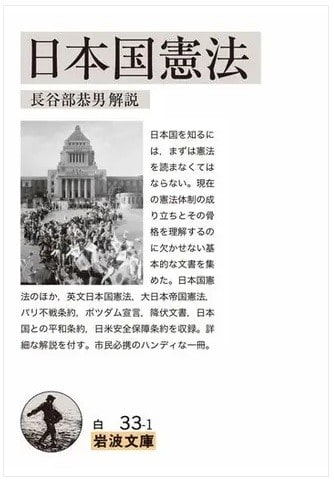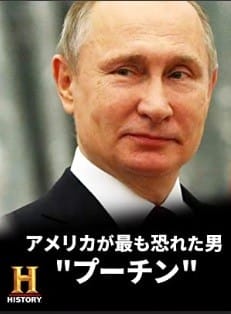富岡『世界』を読む会・5月例会の報告
(郡山さんから)
富岡『世界』を読む会・5月例会が5月25日(水)、5人が参加して開催されました。
今月の課題は『世界』5月号から、緊急特集「ウクライナ」の塩川伸明『ウクライナ侵攻の歴史文脈と政治論理』および西谷修『新たな「正義の戦争」のリアリティーショー』の二つの論考と、特集2「憲法の現在地」の大門正克『生きる現場からの憲法 第1回―夜間中学の学びと東アジアの歴史』でした。
Ⅰ.緊急特集 ウクライナ―平和への道標と課題―
まず、主に塩川論文から作成した「ウクライナの歴史」を参加者で確認しあった後、思い思いに感想を述べ合った。塩川論文については、年表をたどることで理解を深めあったが、西谷論文については、賛否が分かれた。主な意見を整理する。
1.西谷論文肯定
①日本国内の「満場一致」での正義=ウクライナを支援し、悪=プーチンのロシアを打倒せよという「好戦気運」に対して、警告を発しており、耳を傾けたい。
②ジョン・ミアシャイマーの警告、「NATOの東方拡大は絶対許さない」というプーチンの反発を米・NATOが無視したことが、クリミア併合そしてウクライナ侵攻の原因という指摘は、納得できる。
③米国のイラク侵攻とロシアのウクライナ侵攻についての日本を含む西側のメディアと世論は、極めて非対称的であり公平性と客観性を欠いているとの指摘は、重要だ。
④「悪はロシア」という図式では、核の危機を避けられない、との西谷氏の警告は極めて重い。
2.西谷論文批判
①NATOがロシアを攻撃するという可能性が全くない中で、ロシアが「NATOの東方拡大」に恐怖していたとは思えない。
②問題の出発点は「ロシアがウクライナを侵攻した」という事実である。
③「ゼレンスキー=コメディアン」という言説は、差別的である。
3.両論文を通した意見と感想
①「停戦への道」がほとんど論じられていない日本のメディアに、危機感を抱く。
②核のリスクが懸念されているが、改めて核兵器禁止条約批准と国連の役割強化を訴えるべきだ。
③平和憲法を持っている日本こそ「停戦」と「和平」を主導していくべきだ。
Ⅱ.特集2 憲法の現在地―大門正克『生きる現場からの憲法 第1回 夜間中学の学びと東アジアの歴史』
1.1970年代の大阪の夜間中学の実践記録から、在日朝鮮人の玄時玉さんの作文「かんばんの字がよめたとき・・・・・わたしは、うれしくてたまりません」に、本当の「学び」の実感と感動の言葉を読み取り、うれしくなった。
2.また、朝鮮戦争の開始年月について、岩井先生が教科書通りに「1950年6月25日」と教えたのに対し、時玉さんは自分の体験から「1949年より前」との認識を示しますが、先生はこれをきっかけに歴史を学び直し、「4.3済州島事件」にたどり着きます。こうした学びの実践は、感動的だ。
3.今日の夜間中学校の実践についても触れてほしい、との感想もあった。
◎冨岡『世界』を読む会・6月例会の予定
■開催日・場所:6月15日(水)9.30-12.30 吉井町西部コミュニティ・センター
■テーマ
(1)デジタル化について
①若江雅子『デジタル日本 その政策形成における課題』
②内田聖子『デジタル・デモクラシー 第6回―監視広告を駆逐せよ』
(2)特集2 批判的野党がなぜ必要か
杉田敦・齋藤純一の対談『リベラル政党の「可能性」と「不可能性」』