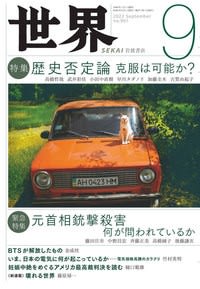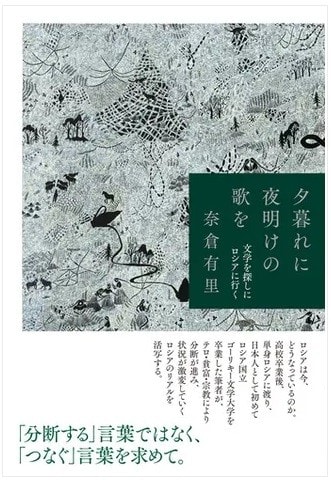東久留米の『世界』8月例会の報告
8月10日(水)、7時より、東久留米の『世界』を読む会・8月例会がzoomで行なわれました。「女性支援」のテーマが取りあげられているということで、奥様が是非参加したい、ということで飛び入りがあって、4名の参加でした。
■ 第一テーマ・「ジャーナリズムはどこに息づくか」依光隆明
・多様な報道が住民を支えるとあるが、多様な報道がその地域に存在し続けられるように、住民がメディアを支えることが大切だ。新聞を取ることも大切だろう。
・新聞の部数の急激な減少のグラフを見ると危機感を感じる。
・日本は同調圧力が強いと言われるが、同調圧力に負けない市民が育ってほしい。
・〔p.80〕「ジャーナリズムに必要な三つの原則」として①公権力の監視、②客観的な事実の追求、③弱い立場の当事者への寄り添い、とあるが、①の実戦として、情報公開請求をしてみたいと思った。
・自分たちが触れているメディアが、「公権力と同化したプロパガンダ」〔p.81〕になっていないかチェックする習慣を身に付けたい。読売、産経、日経は、「公権力と同化したプロパガンダ」だと感じる。
・「ママ友勉強会」〔p.84〕は、小さな地域に根づいた取り組みが民主主義を育てるという意味でいいなと思う。
・「小さな民主主義の紹介」〔p.85〕があれば、自分も小さな民主主義をやってみようと思うのでは。
・「達成感ある仕事には必ず読者がエールを送ってくれる」〔p.85〕とあるが、自分もよい記事を読んだと思ったら、「エール」を送ることをしてみようと思った。
・ジャーナリストになった人たちが、「三つの原則」〔p.80〕などを学んでいるんだろうかと不信を抱く。ジャーナリストが単なる就職先の一つになっているような傾向があるようで気になる。
・南アルプスを貫通する中央自動車道のルートが検討されていたとは驚きだ〔p.75〕。今のリニアのゴリ押しに通じている。
・「ジャーナリズムはどこに息づくか」の「どこ」は、ママ友勉強会などの小さな民主主義の場だということか。
・ジャーナリストが民主主義を支えるとすれば、人口に対するジャーナリスト比率を、諸外国と比べてみたいと思った。
・ジャーナリズムを支えるのは市民だから、市民とジャーナリストとの連帯、連携が大切だ。
・政府の発表をそのまま流すのでは「プロパガンダ」だよ、ということが、ロシアの報道などから、理解しやすい状況はある。
■ 第二テーマ・「分断を超える「女性支援」へ」戒能民江
・女性支援新法の制定までのプロセスがよくわかる論文だった。
・施行までに当事者の声をよく聞き取って欲しいなと思った。
・〔p.56〕にあるように、民間と行政の支援の共同があってこそ、課題解決への近道だと感じた。
・売春をしてしまう者は心が寂しいんじゃないかと思う。全ての子どもがどんな環境の下のあろうと、金銭的なことの心配なく平等に高等教育を受けられることが出来るようになって欲しいなと思った。
・親以外の大人たちのお節介などが子どもたちにとっては必要なのではないか。
・婦人保護事業の中身が分からないが、それは売春禁止法の第四章に基づいて行なわれてきたのだとわかった。
・男女共同参画法の少し前に、専業主婦に年金をおさめなくてももらえる制度が出来たが、女性は家庭で家事に専念する婦人を優遇するという家庭像で税制も組み立てられている。
・支援が必要な女性がいることに関心を持って状況の改善に努力した人たちがいることに、希望を感じた。
・婦人保護施設を視察した議員〔p.50〕は、よい議員だな。
・〔p.55〕施設でのルールが、「利用する女性のための」ルールになっていないとあるが、「何のため」ということを忘れてはいけない。
・〔p.56〕民間を下に見る行政の態度があったら、きちんと抗議すべきだ。
・日本の女性は海外でよく思われているので、あまり粗末に扱うと日本はやばいのでは。
・立場の弱い人を応援するメディアは応援したい。期待もする。
・「日本のジェンダーギャップ指数を、私たちが政権を取ったら、50位以内にします」(2021年は、156カ国中120位)と言えば女性の支持が得られるのではないか。そういう政治家、政党が出て欲しい。
■ 第三テーマ・「新たな歴史を紡ぐアメリカ新世代の労働運動」 松元ちえ
・困難はあるだろうが、希望が持てそうな展開にワクワクした気持ちがした。「ちむどんどん」。
・アマゾンはとてもよく利用しているのだが、日本のアマゾンに労組はどうなっているのか質問してみようと思った。
・日本のアマゾンの配達員の組合ができているとは、報道などでも知らせられていなかった。
・〔p.180〕トイレに行くことができず、ペットボトルで用を足すというのは衝撃的だ。
・ニューヨークは、不法移民に寛容な聖域都市だそうだが、日本でそんな都市があれば、ふるさと納税で応援したい。
・〔p.184〕「成功の秘訣」は、興味深かった。職場で一緒にメシを食べるなど、試してみたい。
・〔p.186〕フリードマン氏の言葉「危機感の共有」があって初めて希望が見える流れが可能になるだろう。
・組合結成への妨害がすごかっただろうな。日本でも組合員を差別、隔離するなど、ひどい状況があったが。生涯賃金ではとんでもない差を付けられる。
・一番組合結成が難しいと思われていたアマゾンでの組合結成は画期的なことだった。
・〔p.180〕「スリーストライク」で解雇は、刑務所の終身刑ルールで聞いた言葉だ。
・「次世代オルガナイザープロジェクト」(オルプロ)https://note.com/orpro_2022
は、新しい動きで注目だ。「オルグ」という言葉に久しぶりに出遭った。
◆8月号のその他のお勧めは
○ 髙木 「メディアは自らを改革できるか」 南 彰
「報道の自由度ランキングで10位以内を目指す」という公約を掲げる政党、政治家が出て欲しい。
奈倉有里『夕暮れに夜明けの歌を』、スベトラーナ・アレクシェーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』、『ボタン穴から見た戦争』は、素晴らしい。
○ 須山 「気候再生のために 変えれば、変わる」 江守正多
◎ 東久留米の『世界』を読む会、9月例会のお知らせ
・「冥福の祈りを邪魔しているのはだれだ?」 高橋純子
・「妊娠中絶をめぐるアメリカ最高裁判判決を読む」 樋口範雄
※ 他に、昼の部として、第3水曜、4時から会場で行なう会 もあります。