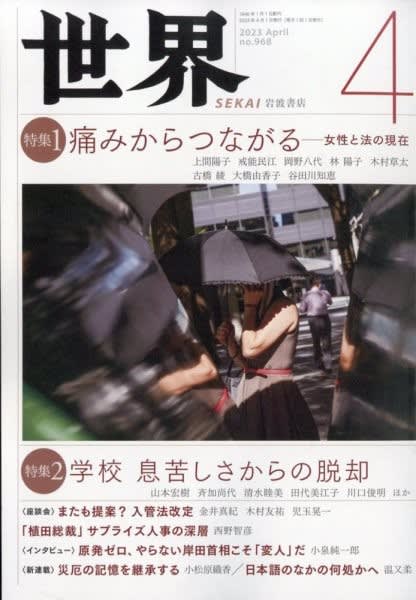富岡の『世界』を読む会・3月例会の報告
(郡山さんから)
富岡『世界』を読む会・3月例会が、3月15日(水)、高崎市吉井町西部コミュニティ・センターで開かれました。今月のテーマは、『世界』3月号から、〈特集1世界の試練 ウクライナ戦争〉の野村真理『西ウクライナの古都リヴィウが見てきたこと』、小山哲『ポーランドからみた「ウクライナ侵攻」』の二つの論考と、〈特集2保育の貧困〉の田淵紫織『「保育の質」はなぜ失われてきたのか』を取り上げました。
Ⅰ.野村真理『西ウクライナの古都リヴィウが見てきたこと』、小山哲『ポーランドからみた「ウクライナ侵攻」』について
参加者にとっては、なじみの薄い地域の言語や民族についての論文で、初見の知識も多く、ウクライナ戦争の背景を知るうえで大変勉強になった、と感想が出された。キーワードは、「民族混住地域」と「民族浄化」。西ウクライナの古都リヴィウの歴史は、ポーランド王の支配—オーストリア帝国への編入—再びポーランド領—第2次世界大戦後ウクライナとなる。こうした歴史を経る中で、民族混住地域が生み出された。そしてポーランド・ウクライナ国境の画定過程で凄惨な民族浄化が執行されたという。
ウクライナ侵攻の現場とでもいうべきウクライナ東部ドンバスについての記述を引用しておく。
「帝政時代に石炭供給地としての開発が始まり、ソ連時代には石炭や鋼鉄関連産業によってソ連の工業化を牽引したドンバスには、ウクライナ人、ロシア人だけではなく、ギリシャ人、タタール人、アルメニア人、ユダヤ人など、多様な出自の労働者が集まり、ロシア語を共通語としつつ、彼らのあいだで民族や国家を越えた強力な地域帰属意識が形成された」。
参加者にとっては、なじみの薄い地域の言語や民族についての論文で、初見の知識も多く、ウクライナ戦争の背景を知るうえで大変勉強になった、と感想が出された。キーワードは、「民族混住地域」と「民族浄化」。西ウクライナの古都リヴィウの歴史は、ポーランド王の支配—オーストリア帝国への編入—再びポーランド領—第2次世界大戦後ウクライナとなる。こうした歴史を経る中で、民族混住地域が生み出された。そしてポーランド・ウクライナ国境の画定過程で凄惨な民族浄化が執行されたという。
ウクライナ侵攻の現場とでもいうべきウクライナ東部ドンバスについての記述を引用しておく。
「帝政時代に石炭供給地としての開発が始まり、ソ連時代には石炭や鋼鉄関連産業によってソ連の工業化を牽引したドンバスには、ウクライナ人、ロシア人だけではなく、ギリシャ人、タタール人、アルメニア人、ユダヤ人など、多様な出自の労働者が集まり、ロシア語を共通語としつつ、彼らのあいだで民族や国家を越えた強力な地域帰属意識が形成された」。
Ⅱ.田淵紫織『「保育の質」はなぜ失われてきたか』
「規制緩和」と「弾力化」の下で、今保育園で何が起きているのか。待機児童問題の解決策として政府は、定員を上回る園児を受け入れ、「質」をおとして「量」を確保する解決策をとった。その結果、慢性的な人手不足や専門性の軽視が進み、現場が疲弊してしまっている、という。園児虐待の背景である。こうした保育の「質」の低下は、園児の人権の侵害だという指摘は、重い。
「規制緩和」と「弾力化」の下で、今保育園で何が起きているのか。待機児童問題の解決策として政府は、定員を上回る園児を受け入れ、「質」をおとして「量」を確保する解決策をとった。その結果、慢性的な人手不足や専門性の軽視が進み、現場が疲弊してしまっている、という。園児虐待の背景である。こうした保育の「質」の低下は、園児の人権の侵害だという指摘は、重い。
Ⅲ.4月例会の案内
1.月日・場所:4月26日(水)14.00-16.00 西部コミュニティ・センターにて(4月例会は第4水曜日!!)
2.テーマ ①吉田千亜『原発12年後の「子どもたち」』、満田夏花『原発回帰 GXの正体と民意の行方』
②田代美江子『包括的セクシャリティ教育の可能性』
1.月日・場所:4月26日(水)14.00-16.00 西部コミュニティ・センターにて(4月例会は第4水曜日!!)
2.テーマ ①吉田千亜『原発12年後の「子どもたち」』、満田夏花『原発回帰 GXの正体と民意の行方』
②田代美江子『包括的セクシャリティ教育の可能性』