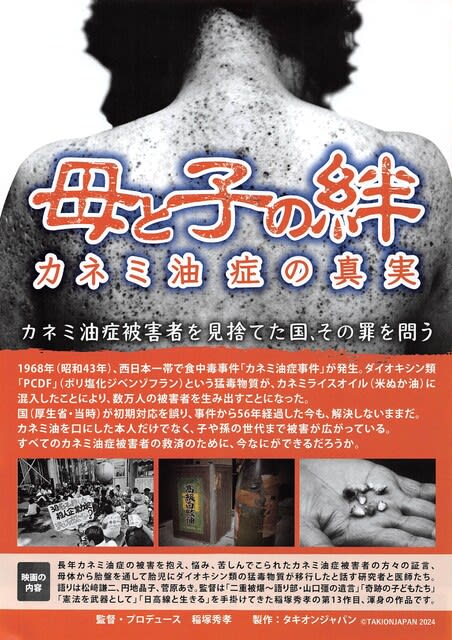一碧文庫の辻さんから、田村一二の『忘れられた子等』の書誌情報がきた。初版は、確か、教育図書だったと思う。
「忘れられた子等」の再版について
大雅堂からは第6版までで、第6版は昭和20年9月20日の発行です。
先日送付した「石山学園日誌」の抜書きで、昭和20年7月19日に「前二著3000づつ増版」の記述があり、前二著とは「忘れられた子等」と「石に咲く花」のことになるので、この時点で第6版発行は決まっていて、増版であることからおそらく「改訂」はされていないと思われます。
時期的に終戦直後といっても直後すぎますしね。
それで、その後の出版はというと、東京の出版社になりますが「冬芽書房」というところから昭和24年5月に発行のものがあります。これが大雅堂以降では直近になると思います。
一碧文庫には所蔵がありません。
ただ、国会図書館のデジタルコレクションでは全編公開されています。
書誌情報は以下のとおりです。
永続的識別子:info:ndljp/pid/1158995
タイトル:忘れられた子等
著者:田村一二 著
出版者:冬芽書房
出版年月日:1949
請求記号:a377-19
書誌ID:000000854436
識別子(DOI):10.11501/1158995