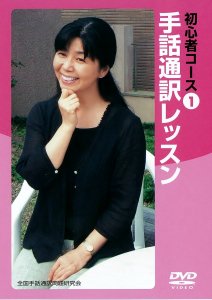昨日と打って変って 今日はいい天気でした。文字通り立春でしょうか?
手をつなぐ育成会の『手をつなぐ』1月号を手に取ってみると 「裁判員制度始ります」ということで特集が組まれています。
証言台に立つことの難しさと聞き取り技術の大切さ を読んでいると
「人の話を聴くというのは、私たちも普段ごく当たり前にしていることですが、相手の言いたいことがおおよそ理解できれば十分なことが多いと思います。相手の言っていることがよく理解できなくても、そのまま受け流してしまうこともよくあるのではないでしょうか。
しかし、法廷ではそういうわけにはいきません。証言台で話をしている人が言いたいことを(ウソを見破ることも含めて)、できる限り正確にとらえる必要があります。これは簡単な作業ではありません。法廷は『話を聞くのが難しい場所』でもあるのです」
「被告人、被害者あるいは目撃証人が質問をよく理解し、自分の言葉で体験や考えていることを話すことができるように、専門家である裁判官、弁護人、検察官が質問の仕方や言葉遣いに配慮することが必要です…」と述べられ、聞き取りの技術の大切さが説かれています。
裁判員制度に望むでは
裁判員制度によって、知的障害のある人たちも司法へ参加することになったことは インクルージョンの第一歩だと述べられています。そして選任手続きや裁判の場面における課題について具体的な提起をしています。
●選任手続きでの支援者の同伴等の支援体制と配慮
●第三者の介在が認められていない裁判で支援者の同伴等の支援 体制をどうするか
●知的障害のある人が、時間のかかる裁判や評議に加わる際の集中力や体調
●わかりやすい内容や表現による裁判資料の必要性
●裁判員の障害特性等を知らされない弁護人や検察官の対応
●障害への理解不足から、知的障害のある人を排除して議論や進行がなされる危険性
●知的障害のある人にとっての理解と遵守
これらを読んでいると、私たち手話通訳者やろう者が裁判員制度が始まるに際して手をつないでいくべき人たちが身近にいることに気づかされます。