24日(日)その2.よい子は「その1」から見てね モコタロはそちらに出演しています
モコタロはそちらに出演しています
昨夕,デザートに息子がゼミ合宿のお土産に買ってきた上州沼田名物「焼まんじゅう」を食しました 原材料は小麦粉の割合が多く 食感としてはパンに近いものがありましたが,味噌味(信州味噌)で美味しかったです
原材料は小麦粉の割合が多く 食感としてはパンに近いものがありましたが,味噌味(信州味噌)で美味しかったです













昨夕,サントリーホール「ブルーローズ」で「サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン」の「ストルツマンと日本の仲間たち」公演を聴きました プログラムは①モーツアルト「クラリネット三重奏曲変ホ長調K498”ケーゲルシュタット”」,②ブラームス「クラリネット・ソナタ第1番ヘ短調」,③同「ヴィオラ・ソナタ第2番変ホ長調」,④ブルッフ「8つの小品」から第2曲,第3曲,第6曲,第4曲です
プログラムは①モーツアルト「クラリネット三重奏曲変ホ長調K498”ケーゲルシュタット”」,②ブラームス「クラリネット・ソナタ第1番ヘ短調」,③同「ヴィオラ・ソナタ第2番変ホ長調」,④ブルッフ「8つの小品」から第2曲,第3曲,第6曲,第4曲です 演奏は,クラリネット=リチャード・ストルツマン,ヴィオラ=磯村和英,ピアノ=小菅優です
演奏は,クラリネット=リチャード・ストルツマン,ヴィオラ=磯村和英,ピアノ=小菅優です
クラリネットのストルツマンは1942年アメリカ生まれ.ピーター・ゼルキンらと1972年に室内楽ユニット「タッシ」を結成しました ヴィオラの磯村和英氏は1969年に結成された東京クァルテットの創設メンバーの一人です
ヴィオラの磯村和英氏は1969年に結成された東京クァルテットの創設メンバーの一人です 小菅優さんは2005年にカーネギーホールで,翌06年にザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・デビューを飾り,世界的に活躍するピアニストです
小菅優さんは2005年にカーネギーホールで,翌06年にザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・デビューを飾り,世界的に活躍するピアニストです

自席はセンターブロック6列目の右側です.会場は土曜の祝日ということもあってか満席に近い入りです
1曲目はモーツアルト「クラリネット三重奏曲変ホ長調K498”ケーゲルシュタット”」です モーツアルト(1756-1791)は故郷のザルツブルクを離れウィーンに出て活躍したわけですが,間もなくクラリネットの名手アントン・シュタードラー(1753-1812)に出逢います
モーツアルト(1756-1791)は故郷のザルツブルクを離れウィーンに出て活躍したわけですが,間もなくクラリネットの名手アントン・シュタードラー(1753-1812)に出逢います モーツアルトは彼から刺激を受けて「クラリネット協奏曲」「クラリネット五重奏曲」「グラン・パルティータ」などの傑作を作曲しましたが,このK.498のクラリネット・トリオもその一つです
モーツアルトは彼から刺激を受けて「クラリネット協奏曲」「クラリネット五重奏曲」「グラン・パルティータ」などの傑作を作曲しましたが,このK.498のクラリネット・トリオもその一つです 「ケーゲルシュタット」というのは,「九柱戯」(ボーリングの前身)の遊びの名称で,モーツアルトはこれで遊びながらこの曲を書いたという逸話からこの愛称が付けられました
「ケーゲルシュタット」というのは,「九柱戯」(ボーリングの前身)の遊びの名称で,モーツアルトはこれで遊びながらこの曲を書いたという逸話からこの愛称が付けられました 第1楽章「アンダンテ」,第2楽章「メヌエット」,第3楽章「ロンド:アレグレット」の3楽章から成ります
第1楽章「アンダンテ」,第2楽章「メヌエット」,第3楽章「ロンド:アレグレット」の3楽章から成ります ここで気が付くのは「アレグロ」がないということです
ここで気が付くのは「アレグロ」がないということです
ストルツマン,磯村和英氏と小菅優さんが登場し配置に着きます 小菅さんはいつもオシャレです.エレガントな衣装で登場です
小菅さんはいつもオシャレです.エレガントな衣装で登場です ストルツマンを見て,「ああ,タッシのストルツマンも歳を取ったなあ
ストルツマンを見て,「ああ,タッシのストルツマンも歳を取ったなあ 」と思いました.さっそく演奏に入りますが,若い小菅さんのパワフルなピアノに,磯村氏もストルツマンも圧倒されながら演奏しているように見受けられます
」と思いました.さっそく演奏に入りますが,若い小菅さんのパワフルなピアノに,磯村氏もストルツマンも圧倒されながら演奏しているように見受けられます この作品は好きなので十分楽しめました
この作品は好きなので十分楽しめました
2曲目はブラームス「クラリネット・ソナタ第1番ヘ短調」です ブラームス(1833-97)晩年の傑作です
ブラームス(1833-97)晩年の傑作です ブラームスは晩年にマイニンゲン宮廷楽団のクラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルト(1856-1907)と出逢い,再び創作意欲が湧き出て作曲したものです
ブラームスは晩年にマイニンゲン宮廷楽団のクラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルト(1856-1907)と出逢い,再び創作意欲が湧き出て作曲したものです この二人の出会いから生まれた作品には「クラリネット三重奏曲」「クラリネット五重奏曲」と2つの「クラリネット・ソナタ」があります
この二人の出会いから生まれた作品には「クラリネット三重奏曲」「クラリネット五重奏曲」と2つの「クラリネット・ソナタ」があります モーツアルトにしてもブラームスにしてもクラリネットの名手との出会いが名曲を生むことになったわけです
モーツアルトにしてもブラームスにしてもクラリネットの名手との出会いが名曲を生むことになったわけです
この曲は第1楽章「アレグロ・アパッショナート」,第2楽章「アンダンテ・ウン・ポーコ・アダージョ」,第3楽章「アレグレット,グラツィオーソ」,第4楽章「ヴィヴァーチェ」の4楽章から成ります
ストルツマンと小菅優さんが登場します ストルツマンは椅子をおもむろに持ち上げ,小菅さんの椅子に近づけました
ストルツマンは椅子をおもむろに持ち上げ,小菅さんの椅子に近づけました 小菅さんが「おっ,きた
小菅さんが「おっ,きた 」と一瞬身を引いたように思いました
」と一瞬身を引いたように思いました 気のせいだと思います
気のせいだと思います 第1楽章に入り,ストルツマンの憂いに満ちたクラリネットが会場を満たします
第1楽章に入り,ストルツマンの憂いに満ちたクラリネットが会場を満たします この曲でも小菅さんのピアノが圧倒します
この曲でも小菅さんのピアノが圧倒します この曲は第2楽章が良いですね.まさに今,秋の夜にピッタリの曲です
この曲は第2楽章が良いですね.まさに今,秋の夜にピッタリの曲です

プログラム後半の1曲目はブラームス「ヴィオラ・ソナタ第2番変ホ長調」です この曲はブラームスの「クラリネット・ソナタ第2番」をヴィオラ用に編曲したものです
この曲はブラームスの「クラリネット・ソナタ第2番」をヴィオラ用に編曲したものです 第1楽章「アレグロ・アマービレ」,第2楽章「アレグロ・アパッショナート」,第3楽章「アンダンテ・コン・モート」の3楽章から成ります
第1楽章「アレグロ・アマービレ」,第2楽章「アレグロ・アパッショナート」,第3楽章「アンダンテ・コン・モート」の3楽章から成ります
磯村氏と小菅さんが登場し演奏に入ります この二人の演奏で聴くと,まるで最初からヴィオラとピアノのために作曲された曲のように感じます
この二人の演奏で聴くと,まるで最初からヴィオラとピアノのために作曲された曲のように感じます クラリネットとヴィオラは相関関係があるのかもしれません.この曲も名曲です
クラリネットとヴィオラは相関関係があるのかもしれません.この曲も名曲です
最後の曲はブルッフ「8つの小品」から第2曲,第3曲,第6曲,第4曲です ストルツマン,磯村氏,小菅さんが登場し,さっそく演奏に入ります
ストルツマン,磯村氏,小菅さんが登場し,さっそく演奏に入ります 最初に演奏された「第2曲」を聴いた時,「2017年9月,ドイツでブラームスの作曲による作品が新しく発見されました
最初に演奏された「第2曲」を聴いた時,「2017年9月,ドイツでブラームスの作曲による作品が新しく発見されました 」と言われても信じてしまうくらいブラームスっぽい曲だと思いました
」と言われても信じてしまうくらいブラームスっぽい曲だと思いました ブルッフ(1838-1920)はブラームスとほぼ同じ時代に活躍した作曲家ですが,ブラームスとは友人でありライバルでもあったと言われています
ブルッフ(1838-1920)はブラームスとほぼ同じ時代に活躍した作曲家ですが,ブラームスとは友人でありライバルでもあったと言われています ロマン溢れる「ヴァイオリン協奏曲」が有名ですね
ロマン溢れる「ヴァイオリン協奏曲」が有名ですね
この作品でも小菅さんのパワフルなピアノがストルツマンと磯村氏を煽るように激しく掻き立てます 仕掛けられた二人も「若い者には負けん
仕掛けられた二人も「若い者には負けん 熟年パワーを目に物見せてくれるわ
熟年パワーを目に物見せてくれるわ 」とばかりに熱演を繰り広げ,さながら年金原資の配分をめぐる世代間の代理戦争の様相を呈してきました
」とばかりに熱演を繰り広げ,さながら年金原資の配分をめぐる世代間の代理戦争の様相を呈してきました 「音楽は国境を超える」とともに「音楽は歳の差も超える」ことを演奏で証明してみせました
「音楽は国境を超える」とともに「音楽は歳の差も超える」ことを演奏で証明してみせました 愛があれば歳の差なんて・・・・どこまで脱線するか
愛があれば歳の差なんて・・・・どこまで脱線するか
この日の演奏は,秋の夜に相応しいプログラミングで十分楽しむことが出来ましたが,このコンサートのタイトルは「ストルツマンと仲間たち」というよりも「小菅優とシニアの仲間たち」の方が相応しいのではないかと思いました
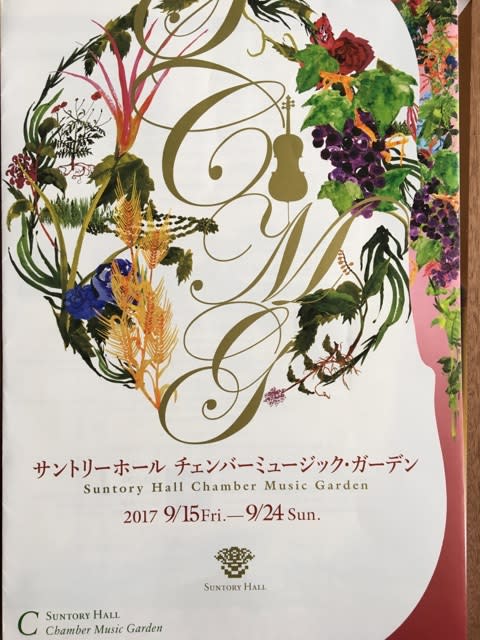
















 何とかセンターブロック右通路側のC7列12番を押さえました
何とかセンターブロック右通路側のC7列12番を押さえました
 どうでもいいことですが,この3人まったく似ていません
どうでもいいことですが,この3人まったく似ていません



