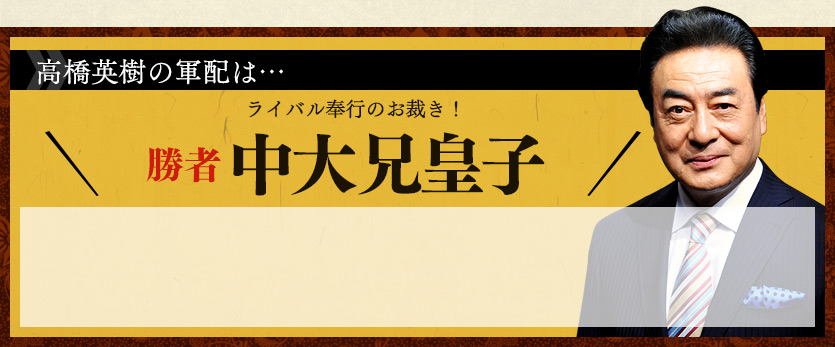天皇の被災地訪問は"菩薩行"である
PRESIDENT Online
島田 裕巳 宗教学者
これまで天皇が、自らの信仰は仏教であると公言したことはない。しかし明治に入るまで、天皇の信仰の中心にあったのは仏教だった。
代々天皇は仏教に対する強い信仰をもっていた。生前退位を控えたいま、宗教学者の島田裕巳氏は「天皇の象徴としての行為、それは神道ではなく、仏教ではないか」と問う――。(第1回)
※本稿は、島田裕巳『天皇は今でも仏教徒である』(サンガ新書)の「はじめに」を抜粋したものです。
天皇の退位と天皇の信仰
天皇の信仰を問う。それがこの本の課題である。
天皇の信仰を問うと言ったとき、それは不遜(ふそん)な行為ではないのか、不敬にあたるのではないかと考える人もいるかもしれない。
しかし、今やそれを問わなければならない時代になっている。それも、天皇のあり方がさまざまな点で重要な岐路に立たされているからである。
島田裕巳『天皇は今でも仏教徒である』(サンガ新書)
岐路に立っていることは、なによりもNHKのスクープ(2016年7月13日)によって天皇の生前退位の問題が浮上したことで明らかになった。
天皇は祈っているだけでよいのか
この点が今後、どのような方向で議論されるかは定かではないが、退位をめぐる有識者会議に呼ばれて意見を述べた有識者のなかには、退位にすら反対する人間が少なくなく、伝統を変えることがいかに難しいかが明らかになった。
そうした有識者の見解のなかで、もっとも極端なものは、天皇は祈っているだけでよいのであって、それ以外の「公的行為」をする必要などないというものであった。祈ることこそが天皇の本来のあり方であり、いくら高齢になっても、それが果たせる限り退位する必要はないというのである。
国民に対して、間接的な形ではあるものの、退位の意思を表明した2016年8月8日のビデオメッセージで天皇が強調したのは、即位以来、国事行為を果たすとともに、「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来た」ということだった。ところが、高齢になったことで、国事行為や象徴としての行為を十分に果たすことができなくなったというのである。
このビデオメッセージで、政治的な見解を述べることを封じられた天皇が、明確に退位の意思を示すことはできなかった。だが、長年考え続けてきた象徴としてのあり方を実践していくことに、天皇がいかに腐心してきたかが示される形になった。
その点では、退位に反対する有識者の考え方と、天皇自身の考え方が真っ向から対立したことになる。なにより印象的なのは象徴としての行為を否定し、それを天皇の務めから外れていると見なす有識者は、意外なほど多かったことだ。
象徴として実践してきた「慰霊の旅」
天皇が象徴としての行為として実践してきたのは、大規模な災害が起きたときの被災地への訪問であり、第二次世界大戦において多くの犠牲者を出した場所への「慰霊の旅」である。また、前述のビデオメッセージでは、「日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました」と述べられていた。
こうした行為は、国民から圧倒的な支持を得てはいるものの、たしかに、憲法に規定されたものではない。だからこそ、天皇自身、それをいかに実現するかに努力を傾けてきたわけだが、保守的な天皇観を持つ人間からすれば、それは天皇がする必要のない、無用の行為であるということになる。
そこには、天皇をめぐる、あるいは天皇制をめぐる難しい問題がかかわっているわけだが、一つ重要なポイントは、現在の天皇が30年ほどにわたる在位期間に考え、実践してきた象徴としての行為が、実は伝統に根差したものであり、天皇の信仰と密接な関係を持っているのかもしれないということである。だからこそ、今、天皇の信仰を問わなければならないのだ。
もっとも、この問題自体は、特例法が成立したことによって解決を見た。特例法の正式な名称は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」である。これによって、2019年3月末日には現在の天皇の退位が実現され、4月1日に新しい天皇が誕生することとなった。平成は31年で幕を閉じることが有力視されている。
ただ、現在の天皇による退位の表明には、皇位の安定的継承の問題がからんでいるのだが、こちらは解決策が見出されているわけではない。退位の問題をどのように処理するか、その枠組みを決めるために組織された有識者会議でも、その点について具体的な議論は行われなかった。
明治に出てきた「万世一系」の考え方
特例法について議論を行った衆参両院の委員会では、皇位(こうい)の安定継承をはかるためということで、「女性宮家(みやけ)」創設などの検討を盛り込んだ付帯決議も採択された。この決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、先延ばしすることはできない重要な課題」であるとも指摘されている。これは政府に対して、特例法の施行後、つまりは現在の天皇から皇太子への譲位が実現した後に、速やかに皇位の安定的な継承策を検討することを促すものである。ただし、これについては期限が設けられていないため、いつ議論が行われるのか、明確な見通しは立っていない。
そこには、有効な具体策が出てくる見通しが得られないということが深くかかわっている。女性宮家の創設のほかに、女性天皇の容認、さらには女系(じょけい)天皇の容認など、いくつかのアイディアは出されているものの、どれも決定的なものとは言えない。1947(昭和22)年にGHQの圧力により皇籍(こうせき)から離脱せざるを得なくなった旧皇族(旧宮家)の復帰を強く主張する人たちもいるが、離脱からすでに70年の歳月が経っており、その実現は相当に困難なものと思われる。
明治時代には、天皇について「万世一系(ばんせいいっけい)」という考え方が打ち出された。このことばは、明治維新の立役者の一人、岩倉具視(ともみ)が「王政復古議」(国立国会図書館所蔵『岩倉具視関係文書 第一』所収)という文書によって最初示したものであり、これ以降、天皇家は初代の神武(じんむ)天皇(在位紀元前660~前585年)以来、連綿と、しかも男系によって継承されてきたことが強調されるようになった。
ところが、皇位の継承の方法について定めた「皇室典範」が最初に制定された明治中期と現在とでは、日本の社会のあり方は大きく変わっている。皇室典範は、戦後、新しい憲法が制定されるのを機に部分的に改正されたが、そこでは、古い皇室典範では認められていた天皇が「側室」を持つことが否定された。これによって、皇位の継承はより困難なものになっている。