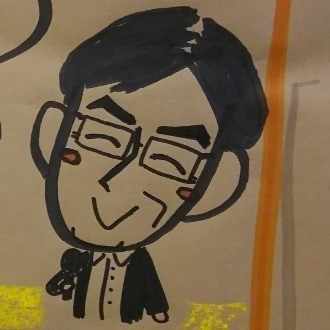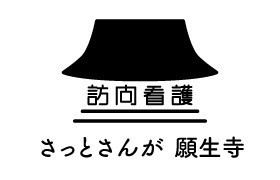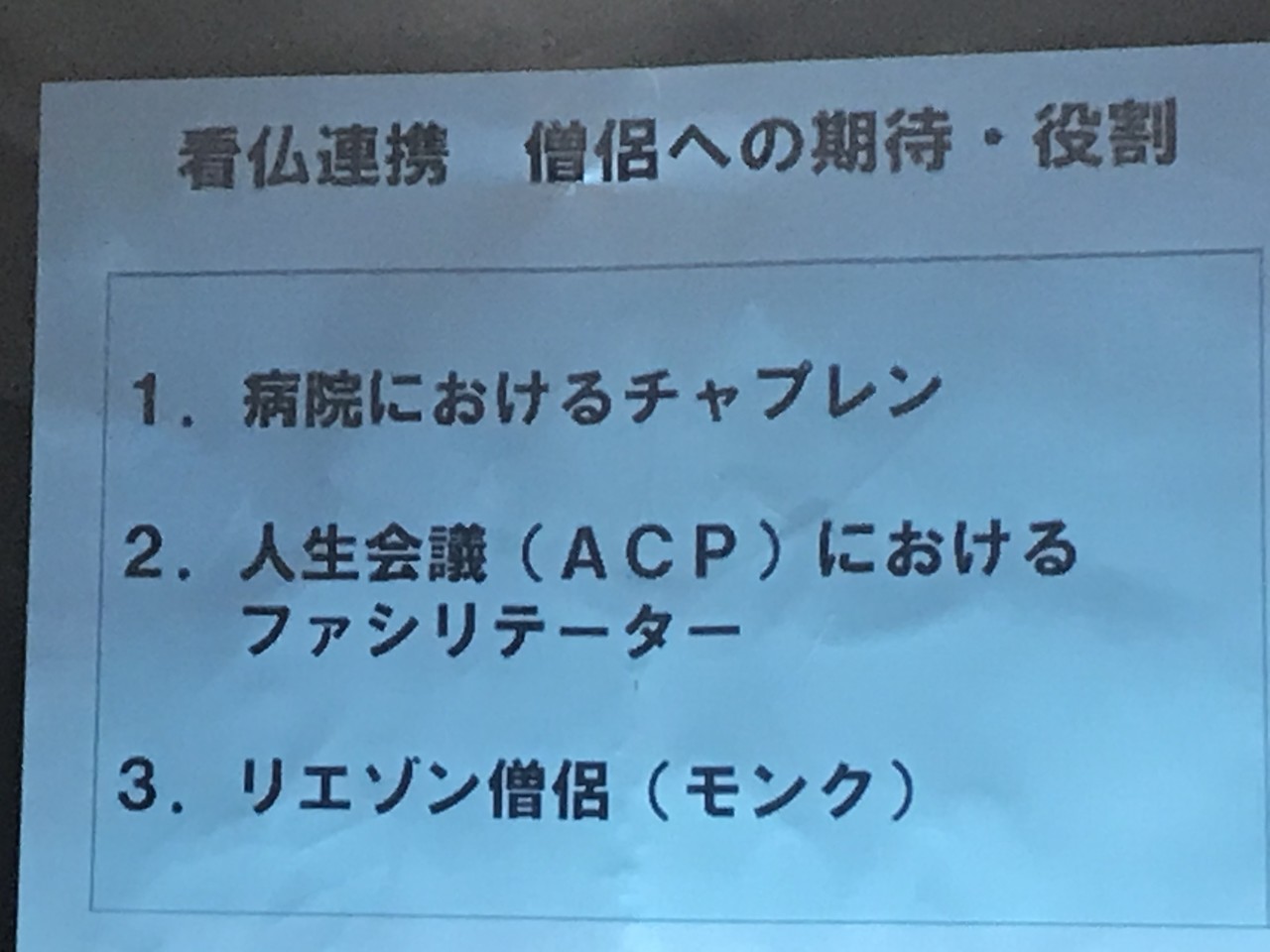ザ・芸能界 テレビが映さない真実
「週刊現代」2017年2月25日号より
田崎 健太ノンフィクションライター
跡を絶たない薬物乱用による芸能人の逮捕劇。芸能界はそれほどまでに汚染されているのか。なぜ、どのようにして彼らはクスリにハマっていくのか。そこには知られざる「システム」が存在する。
渋谷と西麻布のバーで
清原和博、ASKA、押尾学、酒井法子、小向美奈子――。
ここ数年、薬物で逮捕された芸能人である(清原は元プロ野球選手だが、引退後メディアに露出していたという意味では広義の芸能人に含んでいいだろう)。
なぜ彼ら、彼女ら、芸能界の人間はクスリに溺れるのか。
まず指摘できるのは、彼らは一般人よりもはるかに、日常生活の中でクスリと接する可能性が高いということだ。
「渋谷の一角にかつてバーがあった。目立たないが、芸能事務所関係者、マスコミの人、海外の芸能関係者まで集う知る人ぞ知る店。そこが『買える』ということで有名だったんです」
こう語るのは、芸能関係者のXである。Xは「今からでも2時間もらえれば、すぐにクスリを手に入れてきますよ」と豪語する。
Xは現在は薬物を断っているが、数年前に覚醒剤による逮捕歴がある。現在も芸能界に関わっているため、匿名とする。
「クスリを手に入れることのできるバーはぼくが知っているだけで、現在も都内に5つはある。経営者の方針にもよりますが、自らが売らずに、客同士に取引の場所を貸すパターンが多い。そういう噂のあるバーは、外国人モデルが沢山遊びに来ていて流行っている」
その中の一つ、西麻布のバーでのことだ。
「ある程度人数が集まったら、店を閉めちゃうんですよ。そしてテーブルをぴかぴかに磨いて、クスリ(コカイン)をざーっとテーブルの上に白線のように撒いて、みんなで鼻から吸っていく。その場には、何人も芸能人がいましたよ」
昨年12月に『FRIDAY』で報じられた俳優・成宮寛貴の薬物使用疑惑の写真も、マンションの一室で撮られたとされるものだった。成宮自身が薬物を使用していたか否かは今も定かではないが、こうした都心のクローズドな場所で、密かにクスリは取引され、使用されているのである。
Xは自ら薬物を使用する他、「運び屋」でもあった。芸能事務所の人間、テレビ局員などに毎日のように覚醒剤を運んでいたという。
「カジュアルにつき合おうと思えばできるんですよ。最初は葉巻みたいな感覚。まあ、あったら気持ちがいいよな、程度です。『覚醒剤を常用していると、身も心もボロボロになる』と言いますが、必ずしもそうならない人もいる。15年、20年やりつづけて、中毒にならない人も知っています」
Xもまた「カジュアル」に覚醒剤に手を出した。そして、その量は次第に増えていった。
「ぼくの場合、仕事が忙しいときは、やらなかった。クスリをやると、自分では能率が上がっているつもりでも、実際の作業は遅く、そして雑になる。やりたくなるのは、盆暮れとか、しばらく人に会わなくていいとき。クスリをやって人に会うとばれてしまいますから。
清原さんが、『週に一度、子どもと会った後、寂しくなって覚醒剤を使っていた』という報道がありました。でも、覚醒剤をやったことのあるぼくたちから見ると『来週まで子どもに会わないのだから、クスリを使えると考えたんじゃないか』と勘ぐってしまうんです」
「1回1000万円」の女
ノンフィクション作家の溝口敦は著書『薬物とセックス』の中でこう書いている。
〈覚醒剤はよく「前借りのクスリ」といわれる。寝ないで頭や身体を動かしていたければ、明日の分、明後日の分までエネルギーを前借りできる。
(中略)しかし前借りの利息はべらぼうに高く、300%、500%の利息では済まず、場合によっては一生涯かけても払いきれないほどの利息を要求してくる〉
逮捕される直前の2年間は、重度の中毒になっていたとXは振り返る。
「友だちや女の子の家で(薬物を使用する)行為に没頭してました。仕事に穴を空けたこともあります。家族もいますし、何度もやめようと思ったんですよ。何度も覚醒剤を捨てました。川に投げたことも、トイレに流したこともある。
でも、せいぜい我慢できて3週間。運び屋をやっていたので、その間もちょいちょい誘いや問い合わせが来るんです。最後はこれは長く続かないな、早く捕まらないかなと思っていました」
Xもまた、その利息を逮捕という形で払うことになった。
もう一つ、芸能界で薬物が横行する大きな原因として、薬物が性行為と結びついていることをXは指摘する。
「薬物の快楽というのは、バクチ、あるいはセックスと一緒にやると、かけ算になる。女性の側に使用する気がなくても、知らない間にコンドームにシャブを塗られたり、と様々なやり方があります。ぼくの実体験では、女性の方が一度経験するとクスリに夢中になりやすい」
芸能界には、タレント、あるいはタレント志望の女性が溢れている。そのため、芸能界とクスリは親和性があるのだ。
「芸能界でのし上がっていくには、クスリか女のどちらかを手配できることが必要なんです」
芸能界に関する噂として、いわゆる「枕営業」の話がある。これに関連して、事務所やマスコミ関係者に対する「営業」とは限らないにせよ、芸能人やモデルとの売買春を斡旋する「交際クラブ」が存在するのは事実だとXは言う。
「あるモデル事務所の人間と会った時、ひっきりなしに電話がかかってくる。『どうしたの?』と聞くと、『今から(モデルを)手配できないかと言われた』と言うんです。
ひと昔前までは、『芸能人を抱く』なんてヤクザしかやっていなかったようなことを、今は小金があれば誰でもできるようになっています。5万~10万円払って会員登録すると、最初は女子大生なんかを紹介してもらえるんですが、金を出せば、それだけ女性のランクも上がっていく」
そう言ってXはスマホを取り出し、女性の顔写真が並んだ交際クラブの会員向けサイトを見せてくれた。
「今の交際クラブは、『芸能人とやりたい』とか『クスリを使いたい』といった、客のあらゆる要求に対応します。その中には、クスリを使ったセックスができる女の子もいる。芸能事務所の中には、こうした交際クラブを運営する組織と癒着しているところもあります」
グラビアアイドルや、ある程度有名なモデルになると、1回数百万円から1000万円程度の「値段」がつくという。客がもし「クスリを使いたい」と言い出せば、彼女たちはそこから溺れてゆくことになる。
人間の意志の力は強くない
Xは、ある芸能事務所の人間から「手配できる女性」の作り方を教えて貰ったことがあるという。
「グラビアアイドルの女の子などは、給料が安いので現金を持っていない。でも、住んでいるのは家賃40万円のマンションなんてこともある。
もちろん、セキュリティの問題というのもあるでしょうけれど、本当の理由は別にあるんです。高級マンションに住まわせて、毎晩のようにミシュランの星のついたレストランに連れて行ったり、売れっ子が出入りしている店を覗かせる。
さんざん遊ばせたあとで、女の子の家族、あるいは心ある友人たちのことを『あの人たちはこんな高級店に行くことはできない。そんなくだらない人間の話を聞く必要はない』と言い続ける。
そして、『しみったれた生活と、今の華やかな生活のどっちがいいんだ』と選択を迫る。自発的に後者を選ぶようになれば、『一丁上がり』です」
Xは'09年に覚醒剤取締法違反で逮捕された、グラビアアイドルの小向美奈子とも面識があった。
「彼女はクスリ好きではあったけど、中毒という感じではなかった。15歳ぐらいから芸能界に入って、可愛い、可愛いと言われ続けてきた。でも20歳を超えると、自分への注目は減ってくる。彼女は、自分を見て、見てというタイプ。かまって欲しいんです。
彼女はそのうち、イラン人の売人グループとも接触をもつようになり、自分で覚醒剤を扱うまでになったと言われます。『男の人はこういうことをしないと喜んでくれないんでしょ』と思い込んでいたんでしょう」
こういうこと――とはもちろん覚醒剤を使った性行為である。
近年、冒頭で挙げた芸能人たちのように、40代から50代の薬物乱用者が増えているという。'09年8月に逮捕された酒井法子は現在45歳、昨年2月に現行犯逮捕された清原和博は49歳、昨年11月に逮捕され、その後嫌疑不十分で不起訴となったASKAは58歳だ。Xが指摘する。
「人は結局、カネがあると快楽を極めたくなるんじゃないでしょうか。'90年代に、渋谷のセンター街などでイラン人の密売人が偽造テレホンカードや覚醒剤を売っていましたよね。その当時若かった人たちが、現在40代~50代になって、時間と経済に余裕ができて何をするか――というパターンではないか」
警察庁によると、薬物乱用で1年間に約1万4000人が逮捕されており、そのうち65%が再犯者だという。高い再犯率が薬物依存の特徴である。
薬物依存症の回復を支援するリハビリ施設『館山ダルク』代表の十枝晃太郎によれば、ダルクに入所するのは逮捕歴がある人間が多いという。
「2回、3回というのは当たり前で、10回を超える人もいます。依存症を治そうと自分から入ってくる人間は少ない。社会的信用、お金を失って、生活も破綻する。周りに人もいないので国に頼るしかなく、生活保護の申請をするわけです。
そこでダルクに行ってリハビリをして、よくなれば面倒を見ましょう、という行政からの依頼で来る方が全体の約半分です」
十枝の母は、故・松方弘樹との間に息子をもうけた歌手の千葉マリアである。十枝自身も、かつて薬物依存症になり、それを克服した過去がある。克服のために重要なのは、環境を変えることだと十枝は考えている。
人間の意志の力は強くない
Xは、ある芸能事務所の人間から「手配できる女性」の作り方を教えて貰ったことがあるという。
「グラビアアイドルの女の子などは、給料が安いので現金を持っていない。でも、住んでいるのは家賃40万円のマンションなんてこともある。
もちろん、セキュリティの問題というのもあるでしょうけれど、本当の理由は別にあるんです。高級マンションに住まわせて、毎晩のようにミシュランの星のついたレストランに連れて行ったり、売れっ子が出入りしている店を覗かせる。
さんざん遊ばせたあとで、女の子の家族、あるいは心ある友人たちのことを『あの人たちはこんな高級店に行くことはできない。そんなくだらない人間の話を聞く必要はない』と言い続ける。
そして、『しみったれた生活と、今の華やかな生活のどっちがいいんだ』と選択を迫る。自発的に後者を選ぶようになれば、『一丁上がり』です」
Xは'09年に覚醒剤取締法違反で逮捕された、グラビアアイドルの小向美奈子とも面識があった。
「彼女はクスリ好きではあったけど、中毒という感じではなかった。15歳ぐらいから芸能界に入って、可愛い、可愛いと言われ続けてきた。でも20歳を超えると、自分への注目は減ってくる。彼女は、自分を見て、見てというタイプ。かまって欲しいんです。
彼女はそのうち、イラン人の売人グループとも接触をもつようになり、自分で覚醒剤を扱うまでになったと言われます。『男の人はこういうことをしないと喜んでくれないんでしょ』と思い込んでいたんでしょう」
こういうこと――とはもちろん覚醒剤を使った性行為である。
近年、冒頭で挙げた芸能人たちのように、40代から50代の薬物乱用者が増えているという。'09年8月に逮捕された酒井法子は現在45歳、昨年2月に現行犯逮捕された清原和博は49歳、昨年11月に逮捕され、その後嫌疑不十分で不起訴となったASKAは58歳だ。Xが指摘する。
「人は結局、カネがあると快楽を極めたくなるんじゃないでしょうか。'90年代に、渋谷のセンター街などでイラン人の密売人が偽造テレホンカードや覚醒剤を売っていましたよね。その当時若かった人たちが、現在40代~50代になって、時間と経済に余裕ができて何をするか――というパターンではないか」
警察庁によると、薬物乱用で1年間に約1万4000人が逮捕されており、そのうち65%が再犯者だという。高い再犯率が薬物依存の特徴である。
薬物依存症の回復を支援するリハビリ施設『館山ダルク』代表の十枝晃太郎によれば、ダルクに入所するのは逮捕歴がある人間が多いという。
「2回、3回というのは当たり前で、10回を超える人もいます。依存症を治そうと自分から入ってくる人間は少ない。社会的信用、お金を失って、生活も破綻する。周りに人もいないので国に頼るしかなく、生活保護の申請をするわけです。
そこでダルクに行ってリハビリをして、よくなれば面倒を見ましょう、という行政からの依頼で来る方が全体の約半分です」
十枝の母は、故・松方弘樹との間に息子をもうけた歌手の千葉マリアである。十枝自身も、かつて薬物依存症になり、それを克服した過去がある。克服のために重要なのは、環境を変えることだと十枝は考えている。
芸能界に戻るから再犯する
だが、逮捕されても再び同じ場所、同じ仕事に戻ることのできる芸能人は、再犯の可能性が高いという。
「ぼくの場合は、薬物依存で本当に全てを失いました。残っていたのは、母親と弟という家族だけだった。この2人に申し訳なくて、ダルクに入ったんです。
例えば、小向さんなどは、捕まって出てもまた、ストリップやAVで稼ぐことができる。彼女を使って仕事をしようという周りの人間もいるでしょう。その場合はどうしても再犯の可能性が高くなる」
その意味で、宮古島などで療養生活を送る清原和博は、正しい道を歩いていると十枝はみている。
「清原さんは逮捕されたあと、『一日一日の闘い。今日は勝ったぞ、明日も頑張ろうという毎日の積み重ねです』と話していますが、ぼくたちの考えと同じです。本当に一日、一日の積み重ねが大切なんです」
警視庁池袋署組織犯罪対策課で薬物取り締まりを担当する蜂谷嘉治警部は、「NO DRUGS」という会を主宰している。これは元薬物乱用者、その家族たちが集まって互いの経験や現状を語る会である。蜂谷警部が逮捕した乱用者の更生のため、7年前に始めた取り組みだという。
「薬物乱用の抑止力の第一は、我々のような警察の取り締まり。その次が家族を大切に思うかどうか。家族を失いたくないという抑止力が働く。家族の方に同席してもらっているのはそのためです」
彼もまた日々の積み重ねが大切だと強調する。
「とりあえず今日はやらないで済んだ、みたいな生活なんです。その一日が積み重なって、一ヵ月、そして一年となる。私たちは『もうやりません』という言葉は信じませんが、『今、やってない』は信用するというスタンスです」
しかし、夫人が更生支援をしているというASKAの場合はまだしも、清原は保釈の際の身元引受人がなかなか決まらなかった。家族という「最後の砦」さえ持たない芸能人が薬物と訣別する道は、決して平坦ではない。(文中敬称略)