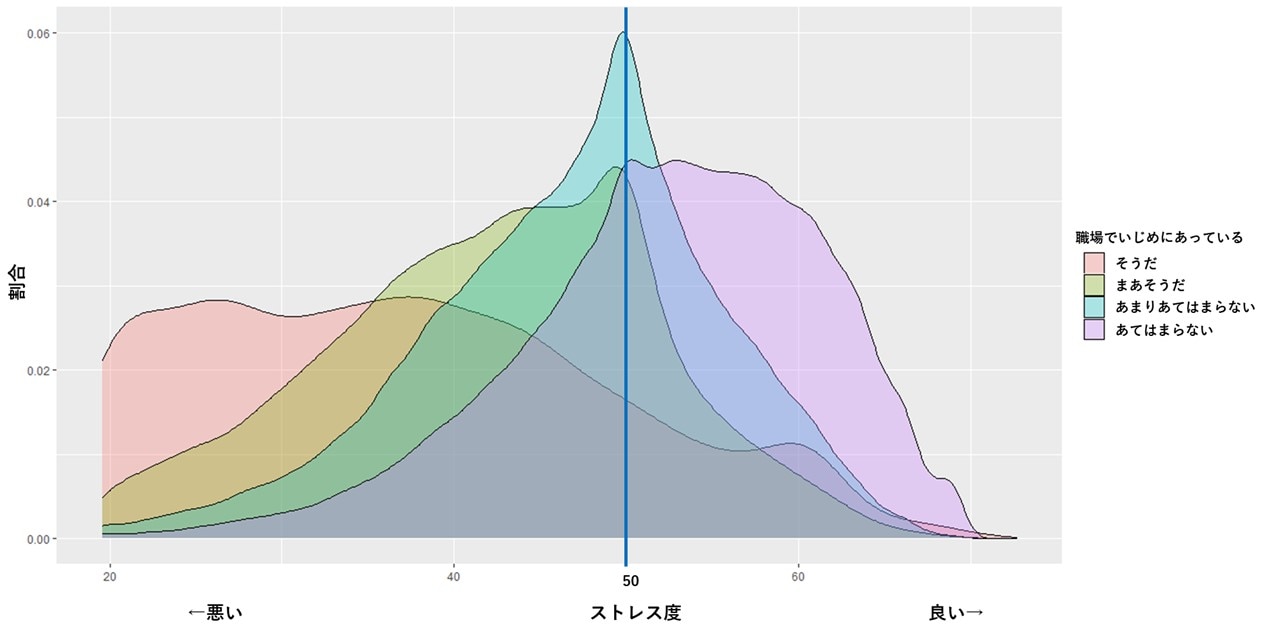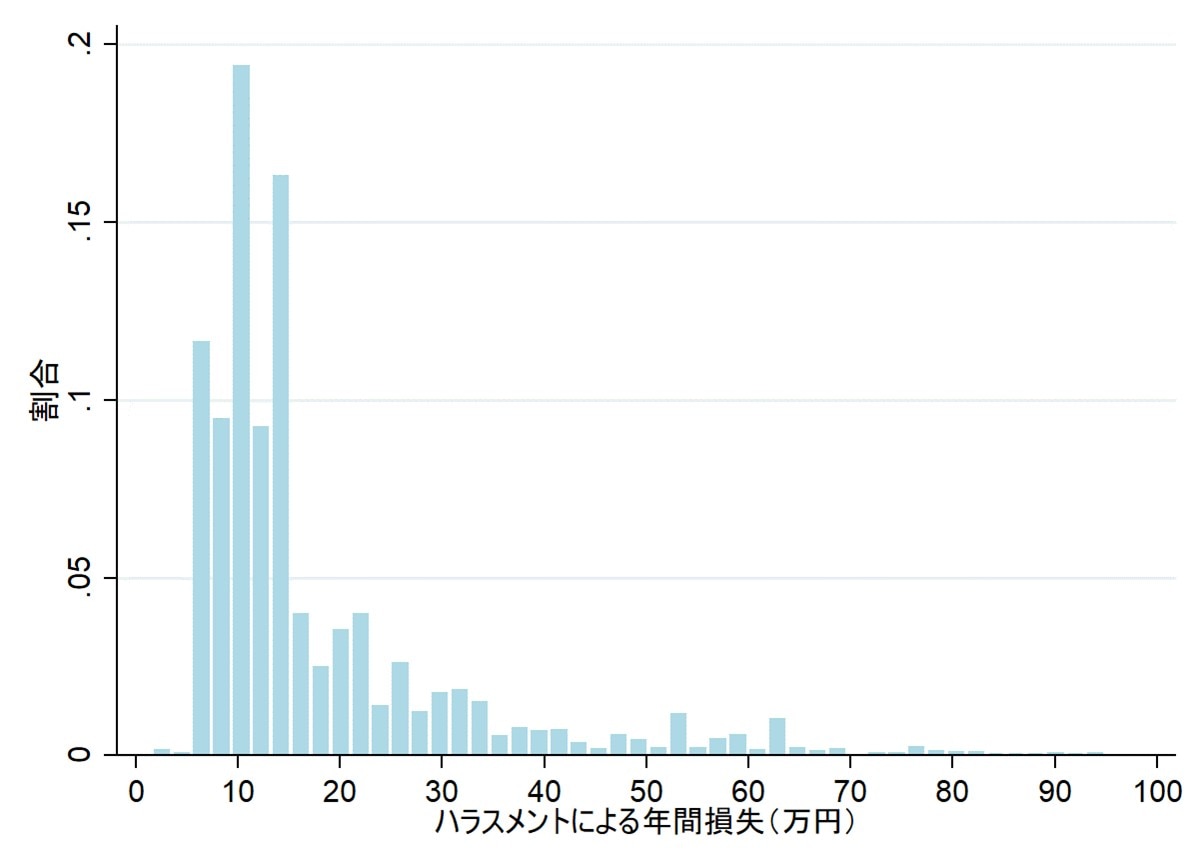「差別犯罪」の先には「大量虐殺」がある
差別感情を元にした「犯罪」がより過激化している。最前線の現場で取材を続ける記者が、在日コリアンを狙った2件の放火事件を始め、脅威を増すヘイトクライムがなぜ生まれるのか、社会背景を探る。更に関東大震災時のジェノサイドから現代のヘイトスピーチまで、連綿と続く「民族差別」の歴史から差別の構造を解き明かすルポ。
【目次】
まえがき
第一章 ヘイトクライムの転換点――ウトロ放火事件
第二章 連鎖するヘイトクライム――コリア国際学園放火事件
第三章 脈々と続く差別という「暴力」
第四章 一〇〇年前のジェノサイド――関東大震災時の虐殺
第五章 ヘイトクライムの背景
第六章 ヘイトクライムとどう向き合うか
第七章 ヘイト解消への希望、共生
あとがき
主要参考文献一覧
●鵜塚 健:1969年、東京都生まれ。毎日新聞大阪本社編集制作センター編集部長。93年入社、大津支局、大阪本社社会部、外信部、テヘラン支局長、大阪本社写真部長等を経て現職。近年は在日外国人問題の取材に力を入れる。著書に『イランの野望 浮上する「シーア派大国」』(集英社新書)、『SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか』(共著、毎日新聞出版)。龍谷大学大学院非常勤講師。
●後藤 由耶:1981年、東京都生まれ。毎日新聞東京本社写真映像報道センター記者。2008年入社、大津支局、大阪本社写真部を経て現職。11年の東日本大震災の際には発災当日から現地で取材。ヘイトスピーチ解消法成立前からヘイトスピーチ問題を大阪や川崎などで追ってきた。15年からは新たに立ち上げられた映像取材部門での取材を担う。
花岡事件(はなおかじけん)は、1945年6月30日、国策により中国から秋田県北秋田郡花岡町(現・大館市)へ強制連行され鹿島組 (現鹿島建設) の花岡出張所に収容されていた 986人の中国人労働者が、過酷な労働や虐待による死者の続出に耐えかね、一斉蜂起、逃亡した事件。警察や憲兵隊により鎮圧・逮捕され、中国人指導者は有罪判決、鹿島組現場責任者らも終戦後、戦犯容疑で重刑を宣告 (のち減刑) された。事件後の拷問も含め、中国人労働者のうち、45年12月までに400人以上が死亡した。
この事件をめぐり、元労働者の生存者と遺族の計 11人が中国人強制連行強制労働被害者として日本で初めて、当時の使用者鹿島建設を相手に損害賠償を求めて訴訟を起した。第一審は原告請求棄却、原告側は東京高等裁判所に控訴、同裁判所が和解案を提示していたが、2000年11月29日、鹿島は企業としても責任を認め、原告11名を含む986人全員の一括解決を図るために5億円の基金を設立することで和解が成立した[1]。
なお、「花岡事件」とは狭義の意味では日本側がつけた中国人の「暴動事件」の名称であるが、広義においては、中国人労務者の第一陣が花岡出張所に連行され、GHQによって停止させられるまでの約18か月間に彼らをめぐって起こった、本項における事件を指す[2]。後者は、1980年代からの鹿島建設への法的・道義的責任追及と被害者の被害回復のための一連の活動および訴訟のなかで、鹿島建設による「花岡強制連行・強制労働事件」という視点からの意味も含んでいる[3]。
事件の背景
日中戦争の長期化と太平洋戦争の開始にともない、日本国内の労働力不足は深刻化し、鉱山や土木建設などを中心とした産業界の要請を受け、東条内閣は1942年(昭和17年)11月27日に「国民動員計画」の「重筋労働部門」の労働力として中国人を内地移入させることを定めた「華人労務者内地移入に関する件」を閣議決定した[4]。
44年2月の次官会議決定によって、同年8月から翌1945年5月までの間に三次にわたり38,935人の中国人を日本に強制連行し、国内の鉱山、ダム建設現場など135の事業場で強制労働させた[5]。
古くから銅の産地として知られていた東北北部三県(青森、岩手、秋田)の中央に位置する秋田群花岡町(現在の大館市)には藤田組(現・同和鉱業)の花岡鉱業所があり、軍需生産のための増産体制によって乱掘が繰り返された。
このため1944年5月、七つ館鉱の上を流れる花岡川が陥没するという大落盤事故が発生し、花岡川の付替工事が要請された[6]。その工事を藤田組の土木部門を請け負ったのが鹿島組(現・鹿島建設株式会社)で、44年8月以降、鹿島組花岡出張所に強制連行された986人の中国人は、主に花岡川の改修工事に従事させられた[7]。
事件の概要
中国人たちは「中山寮」という収容所に入れられ、粗悪で少量の食料と過酷な労働、補導員と呼ばれた鹿島組職員の虐待の中で次々と殺されていった。労働、生活条件の劣悪さは、986人のうち418人が死亡したという事実に示されており、彼らの飢えと栄養不足の凄まじさは生存者および現地の住民、医師等といった日本人の証言で明らかにされている[8]。
過酷な労働と生活、非人間的処遇に耐えかねた中国人たちは、45年6月30日夜(7月1日との説もある)、一斉蜂起し日本人監督4名と日本人と内通していた中国人1名を殺害して中山寮から逃亡した。しかし直ちに憲兵隊、警察、地元警防団らによって鎮圧、再び捕らえられ、逮捕時に殺害された者がいた他、共楽館前の広場に集められて炎天下にさらされ、取調では凄まじい拷問にさらされ、蜂起の後の3日間で実に100名を超える人々が虐殺された[9]。死体は10日間放置された後、花岡鉱業所の朝鮮人たちの手で3つの大きな穴が掘られ、埋められた。
起訴された者が勾留された他は、この後も中国人たちの状況に変化は無く、さらには8月15日の終戦後もこの状態は続き、最終的には秋ごろのGHQによる発見・介入によって事態は終了した。7月に100人、8月に49人、9月に68人、10月に51人が死亡している[10]。鹿島組は中国人の分も食料や物品の配給を受けていたが、ピンハネにより中国人には殆ど行き渡っていなかったもので、事件後に食料についてはようやく改善されたとの一部の中国人証言もある。しかし、それでも死者が多数続き、待遇もむしろ起訴されることになって拘置所に入れられた中国人の方が良いレベルであったという。
逮捕された中国人の取調責任者である当時の大館警察署の元署長は、共楽館前に集めたのは中国人らがリンチに遭うのを恐れて彼らが希望したためであり(後の雑誌では、この元署長は中国人を捕まえた警防団が自然に共楽館に集めたように述べている[11]。)、日射病で倒れた者が数人いるだけ、拷問はなく、食事も与えた、事件後は鹿島組の暴力もやめさせたと主張し[12]、警察が調べられる筋合いは無く、自身が後にこの件で逮捕・起訴されたのは鹿島組の弁護士がキーナン検事との個人的な関係を利用し警察に罪を押し付けたためと聞いていると主張した[13]。
しかし、共楽館前には中国人が逮捕された者から次々と連れて来られていること、日本人にも広場だけで中国人57人が亡くなったことを証言する関係者がいること[14]、中国人も憲兵が拷問をしなかったのに対し警察は自供しても拷問したことを証言していることから、野添憲治は、この元署長の証言は信頼できず、共楽館内で取調を行うため、共楽館前の広場に集めたものとしている。(憲兵らは中国にいた経験がある者が多く、中国人はメンツを重んじることを知っていたため、一人ひとり取り調べる等してうまく扱い、拷問の必要もなかったという。)