
令和コメ騒動!なぜ今さらコメ不足?遅すぎる備蓄米放出と政策の迷走
消費者の財布を直撃しているお米の値上げ。政府は備蓄米の放出をやっと決断しましたが、すでに昨年夏に吉村大阪府知事は、備蓄米の放出を政府に求めていました。しかし、政府は慎重に考えるなどと、結果的に何もしない政策を行ったため、現在も高値が続いております。お米は、日本人の主食でありながら、なぜ失策を繰り返すのか?
1. なぜ今、コメ不足が問題になっているのか?
昨年夏、吉村大阪府知事は備蓄米の放出を政府に求めました。しかし、坂本哲志農林水産大臣は「民間流通が基本となっている米の需給や、価格に影響を与える恐れがあるため、(備蓄米の放出は)慎重に考えるべきものというふうに考えております」と対応を遅らせたことで、現在も高値が続いている要因とも考えられます。
■2023年の異常気象と供給減少
2023年の記録的猛暑による収穫の現象、コメの品質が低下、政府による生産調整により流通量が減少しました。これらの要因により、実際に市場に流通するコメの量が減り、供給不足が発生しました。農林水産省の統計によれば、2024年の収穫量は平年並みとされていますが、昨年の供給不足の影響が継続しており、需給ギャップが解消されていません。
■減反政策が生んだ長期的な生産力の低下
日本のコメ生産は長年の減反政策によって縮小されてきました。生産量が調整されていた期間が長すぎたため、いざ需要が増加しても、田んぼをすぐに作ることはできず、急激に生産を拡大することが難しい状況です。また、農業従事者の高齢化や後継者不足も、供給不足の原因となっています。
■インバウンド需要と物流問題による影響?
訪日観光客の増加に伴い、外食産業のコメ需要が急増し、供給が追いつかない事態が発生しています。また、物流コストの上昇や人手不足が影響し、一部地域では安定供給が困難になっています。 このような原因が一般的に報道されていますが、コメ不足になるほど、訪日外国人がコメを食べているとは思えません。また、先日、「消えたコメ21万トン」などという報道がありましたが、本当に管理できているのでしょうか?
2. コメ価格高騰はインフレ政策の一環なのか?
1993年の米騒動とは異なり、令和の米騒動は単なる供給不足の問題ではないと考える人も多いのではないでしょうか?
■コメ価格が消費者物価指数(CPI)に与える影響
コメは消費者物価指数(CPI)の「食料」カテゴリーに含まれ、価格が上昇すればインフレ率の上昇に寄与します。コメ価格の上昇が続けば、食品全体の価格にも影響を与え、結果としてCPIを押し上げることになります。特に、日銀が目標とする2%の物価上昇を達成するための「便利な要素」となっていた可能性も考えられます。
■なぜ2024年は備蓄米の放出が遅れたのか?
通常、政府は価格上昇を抑えるために備蓄米を市場に放出します。しかし、2024年は価格が高騰しているにもかかわらず、備蓄米の放出が遅れました。これは「急激な価格変動を避けるため」との説明がされていますが、実際には、インフレ率の上昇を維持するために政府が価格調整を遅らせたのでは?という疑念も生じます。コメは日本国民全員と言っても良いほど消費されますので、その効果は小さいものではありません。あくまで憶測の話しです。
■他国の事例と日本の対応の違い
中国やインドでは政府が積極的に穀物価格を管理し、国内市場を安定させています。一方、日本は市場原理に任せる姿勢が強く、価格変動に対して迅速な対応が難しい状況です。 しかし、余計なことをしたとバッシングを受けるより「市場原理を尊重」した結果、対応が後手に回る傾向があります。適切なタイミングでの備蓄米放出や生産拡大を行うことで、コメ不足と価格高騰を回避できた可能性もあったでしょう。
3. 今後のコメ市場と日本の農業の未来
日本のお米は危機的な状況であるようにも感じます。しかし、この状況を放置しておけば、お米すら輸入に頼ることになる未来になるのかもしれません。
■備蓄米放出と価格安定化の可能性
今後、政府は備蓄米を市場に放出し、価格を安定させる施策を取ると見られています。しかし、一度上昇したコメの価格は簡単には下がらず、小売価格の『高止まり』が懸念されています。一方で、市場調整がうまく機能しなければ、急激な価格下落を招く可能性もあります。大きく変動を調整することはマーケットに影響が大きく、政府は適切な対応を求められています。
■コメ輸出拡大のチャンスを活かせるか?
減反政策の影響で生産能力が縮小された日本ですが、これを機に「攻めの農業」へと転換できる可能性もあります。和食の人気を背景に、日本産の高品質なコメを輸出市場に展開するチャンスですが、価格競争や物流インフラの問題が課題となります。
■日本の食料安全保障と農業政策の転換点
減反政策は、GHQから始まる小麦食の推進の影響を受けたことは間違いありませんが、2018年の廃止まで継続されたことで、さらなる問題を引き起こしたとも考えられます。コメ不足は一時的な問題ではなく、日本の農業の構造的な課題が表面化した結果とも言えます。今後、農業支援策や生産体制の見直しを進め、持続可能な供給を実現することが求められます。
コメ不足は偶然か、政策の意図的な結果か?
コメ不足の背景には、異常気象による供給減少だけでなく、政府の農業政策の失敗や市場コントロールの遅れがあることが明らかです。あってはならないことですが、価格高騰が政府のインフレ目標達成のために黙認されていた可能性すら疑ってしまいます。
石破首相をはじめ、昨今の政治家は、『注視して』『議論を重ねて』『市場原理を尊重』といった発言を繰り返すばかりで、傍観しているだけとしか思えない発言が目につきます。権限のある人間が、責任ある行動を取ることが、当然の職務です。問題を先送りし、後手後手の対応となれば、その負担は国民が被るのです。
■コメの価値を再確認
コメは日本人にとって主食であり、生活に欠かせない重要な食材です。全ての国民が、いつでも手ごろな価格で入手できる環境は必然です。そのための備蓄米ですので、適切なタイミングで放出されなければ、備蓄米の本来の役割を果たせません。
今後のコメ市場の動向と農業政策の転換が、日本の食料安全保障と経済全体の行方を左右するでしょう。主食のコメすら適切に管理できないようでは、他の食料政策や農業支援策にも同様の課題が生じる恐れがあります。食料安全保障を強化し、安定供給を実現するためには、計画的な政策と迅速な対応が不可欠です。政府、農家、消費者が一体となり、日本の農業の未来を築いていく必要があります。
完全ノーリスクのトレード・シミュレーターで自由に練習&検証!
ワンクリックFXトレーニングMAXの詳細ページ













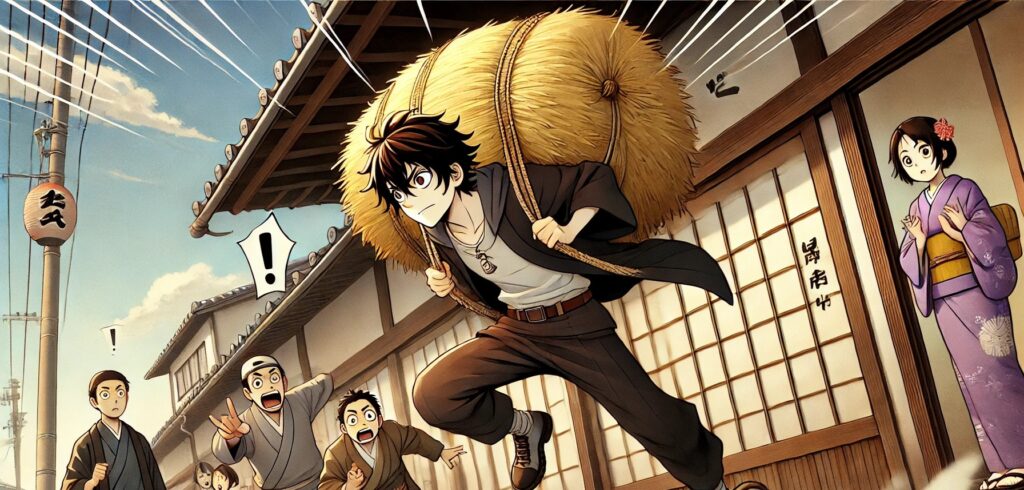








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます