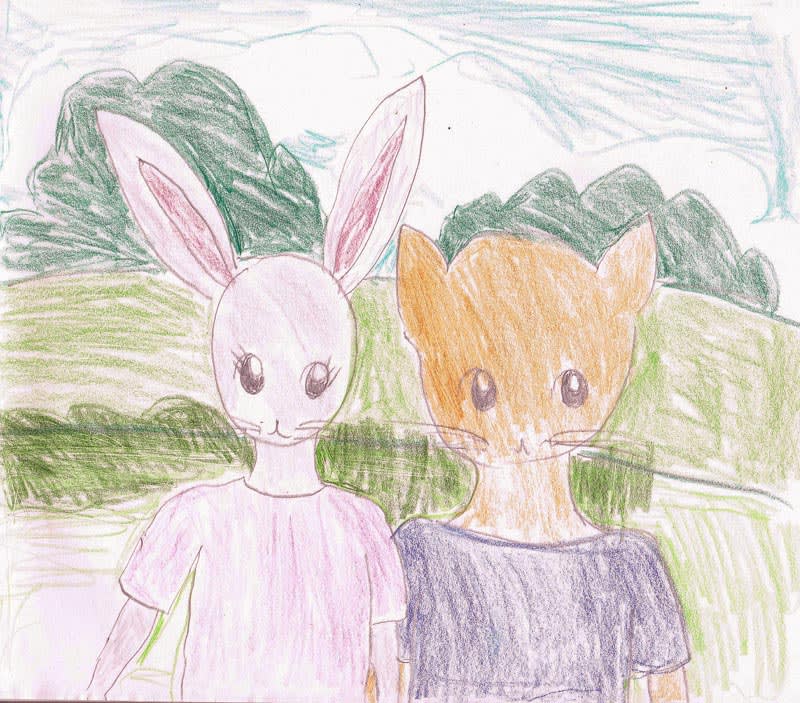といったって、別に毎日ミュージカルを見ているとかそういった話しではない。
これは、多分私の個人的なクセで(と言っても、これは妻と二人だけの状況でしか起こらないことだけど)、私は自分の会話をすぐ「うた」にしてしまうクセがある。
ほとんど99%、その場で創作する「アドリブ」だけど、話すことばに忠実にフレーズやリズムを乗せて歌う(当たり前だ。そうじゃなきゃ歌になるわけない)。
だから、当然子供のうたのように「シンプルで繰り返しの多い」フレーズばかり。
気がつくとこれをやっているから、きっと二人(夫婦)の間の符丁のようなものに近いのかもしれない。
別に恵子を明るくしようとか元気づけようとかいう意図ではない(だって、彼女が病気になるはるか前からコレだから)。
ただ単に気がつくと「あっ、歌ってる」という感じ。
どれぐらいの頻度かというと、多分会話の1/3ぐらいはコレ。
他人から見るとけっこうな頻度だろうと思う。
ということは、それを毎日聞かされている恵子にとってもかなりの頻度に違いない。
それに気づくと「ウルサイだろうな」と思い彼女に聞く。
「ウルサイ?」。
すかさず「うるさい」という返事が返ってくるからきっとそうなのだ(ハハハ)。
1/3は歌ってると言ったが、じゃあ、歌ってない時はごく普通の会話かというと、これもそうでもない。
たしかに「歌ってこそ」いないが、その代わり身体のどこかが動いている(ことに気づく)。
動いているというは、つまり身体のどこかがリズムをとっている、ということ。
これだってそばにいる人間にとってはかなり「ウルサイ」はずだ。
朝一番、起き抜けにやる私の仕事は、彼女と私の血圧を計ること。
この時も(無意識に)「血圧はかろう、血圧はかろう〜」と歌っている(ははは、マジかよ? 朝っぱらからよく歌えるナ)。
かと思えば、玄関の呼び鈴がなると「誰か来た、誰か来た〜」と歌いながら玄関へ向う(もちろん来訪者の目の前ではビタリとやめるが)。
一日の最後に温泉で「足湯」を作ってベッド脇で恵子の足のマッサージをする。
この時だって、歌いはしないが、何かリズムを取っている。
つまり、私って「多動症かナ?」と時々思う。
私が今小学校にあがるかあがらないかぐらいの年令だったらまず間違いなく教師から親が呼び出されて「病院に行かれた方がよろしいのでは?」と言われるはずだ(つまり、 ADHDではないの?と)。
小学生の時の通知表の評価欄の脇にも担任のことばで「落ち着きがありません」と書かれていたぐらいだからきっとそうだったのだろう。
うわ〜、これってヤバイじゃん。
今だったら、完全に「問題児」の仲間入りだ。
でも、幸い私が子供だった頃はめちゃくちゃ社会がおおらかで「何でも許容していた」時代だから「こんな子もいて、あんな子もいて…」といろんな生徒を学校が認めていたのだと思う。
つまりは、今よりも日本の社会そのものに「多様性」があったのだ。
そう考えると現代の子供というのは、どれだけ生きにくいのかと思う。
社会や世界がこれだけ「広がり発展した」ように見えても、その実人々の心は逆にどんどん「狭く」なっているのかもしれないと思う。
多分、本当の「天才」はこの時代現れにくいのかもしれないとも思う。
他と「違う」ことを許さない社会は、「天才の出現を拒む」からだ(だから、ほんのちょっと違うだけで「この子は天才だ」と騒ぐ...「その程度で...!」アホらしい!)。
音楽でもアートでも、さまざまな分野で「技術」はものすごくレベルアップしたような気がするけど、みんな同じで「ツマラナイ」。
なんでみんな同じなのかナ?
私が小さい時、「演奏」や「音楽」に感じていたこと。
それは、ノーミスでの演奏ほどつまらないものはない、ということ。
「完璧に演奏する」ことを目指す人が多ければ多いほど音楽の質が下がっていくような気さえする。
だって、音楽の表現って「ミスをしない」ことが目的ではないはず(たとえクラシックのような再現芸術であっても)。
私は、音楽とはその人の「こころ」を音を通じて相手に伝えることだと思っているので、ミスをするかしないかなんてことはどうでも良いことだと思う。
よく終演後のコンサートの楽屋でステージから戻って来るなり「ああ、あそこ間違っちゃった」と叫ぶご仁がいる。
完全なバカ野郎だと思う(女性でも)。
お前さん、お客さんのこと考えてなかったの?
アナタ、一体誰に向って演奏していたの?
自分のことしか考えてないから「ミスしたかどうか」にこだわっているのだと思う(きっとこのご仁にはそこしか見えていなかったのだろう)。
なので、そういうことをおっしゃる方とは二度と一緒に音楽を分かち合いたくない。
音楽ってもっと自由でもっとハッピーなものでしょう。
同じように人生も、もっと自由でハッピーなものでしょう。
今、この瞬間がハッピーと思えなかったらいつハッピーになるの?
私はそう信じているんだけどナ…。