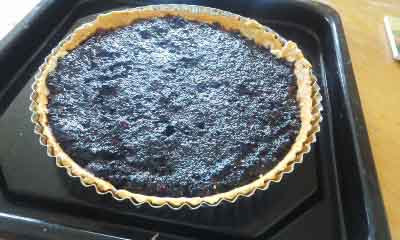音楽って結局この2つで説明できるんじゃないのかと小さい頃からずっと思ってきた。
身体が下に向って動くダウンビートと身体が空に向って起きあがる動きがアップビート。
その「上下の動き」が、音楽そのもの。
でも、まあ人間は「上下」に動くだけでなく横にも揺れるので、「タテのり」「ヨコのり」の2つがあると説明する人もいる。
ただ、横の動きもどこかで結局「着地」は必要なので(重力があるからネ)、最終的には人間の身体のどんな動きもダウンビートとアップビートのどちらかとして理解できるはず(だと私は理解している)。
なぜこんな話しを始めるかというと、ここ7、8年地元のシニアの人たちのアンサンブル(常時十数人参加しているのでそれなりの数だ)を指導しているせいか、この問題がいつも頭から離れない。
プロの音楽の世界でプロの人たちと音楽をやっていく上では何の問題もなかった事柄が、シニア世代のアマチュアの人たちを指導していると「え〜?!」と驚くようなことをたくさん発見する(同じ素人の人たちを指導するのでも、子供たちや若い人たちには絶対に起こらないことがこの年代には起こる)。
その中でも究極が、このビート感覚。
よくコンサート会場で手拍子のウラ打ちができない人たちをお見かけするが、若い世代の人たちは問題なくウラ打ちの手拍子ができるのに、ある程度年輩の人たちにはこれが絶望的にできない人がいらっしゃる。
なので、手拍子だけでなく楽器をやる上でもアップビートやシンコペーションのリズムでつまづくシニアの方は多い。
ロックのような単純な8ビートはそれほどでもないのだが、サンバやボサノバなどの微妙なシンコペーションの音楽がけっこうヤバい。
頭と身体がすぐにバラバラになってしまう。
ただ、これを「若い人たちは小さい頃からこうしたビートに慣れているから」とか、「シニア世代はあまり慣れていないから」ということだけに理由を求めるのは早計だ。
根本的に日本人は音楽と身体の動きを結びつけて理解しようとする意識がそもそもなかったことの方が切実な要因だと私は思っている(明治時代の音楽教育にその元凶がある)。
なので、年輩の人ほど「音楽」と「踊り」を直感的に結びつけない人(あるいは、結びつけられない人)が多いのはある程度仕方のないこと(だろう)。
それに対して、若い世代ほど「音楽=動き」に身体が素直に共感する。
ヒップホップにしろ、ラテンにしろ「音楽=踊り」であることを身体が無意識に理解してくれるからだ。
ただ、この「音楽=踊り」の感覚も(戦後すぐから比べれば)多少成長したとはいえまだまだ欧米ほどではない。
極端に言うと、日本人は「ダンス用」に作られた音楽でしか身体を動かすことができないのかもしれないとさえ思う。
未だに(バスドラムの)4つ打ちのシンプルなビートには身体が反応しても、例えば、スローなブルースになると途端に身体が動かなくなる人は多い(ところが、欧米のパーティでは、「え?こんな音楽でよく踊れるね?」というぐらいどんな種類の音楽でも彼ら彼女らは踊る)。
日本人が「音楽=踊り」と素直に思えない最大の原因がことばにあることは明白だ(と私は前から思っている)。
もちろん、日本語だけでなく、「ことばが音楽や身体の動きを作りだす」という原則はどこの国のことばにも当てはまる。
その証拠はいくらでもある。
例えば、日本語ではaiueoの5つの母音が必ずどの単語からも切り離せない。
基本的にことばのアクセントは母音にしか存在しないので、bdcghjxyzといくら子音だけたくさん並べても(子音だけの)ことばにはアクセントの置きようがない。
逆に、日本語はアクセントだらけなので全ての音が下向きに落ち地面に着地してしまう。
で、結果として、身体が上に向うアップビート(裏ビート)はほとんど起こらないのでリズムはハネない(ナツメロ歌謡曲にはこの類いが多い)。
日本人が「ミスド」とか「スマホ」とかいった単語を作りたがるのもこの理由からだ。
母音3つを並べると日本語として音が着地しやすくなる(つまり発音しやすいということ)。
なので、時々有り得ない(トンデモない)ことが起こる。
例えば、ハンバーガーチェーンの略称も「マック」だし、パソコンの名前も「マック」。
これは日本語でしか起こらない現象だ。
なぜなら、ハンバーガーの McDonaldの頭の Mcには母音が全くないので本来マックとは発音できないはず。
逆に、パソコンは Macなので、明らかに「マック」としか発音できない。
英語の苦手な日本人が海外に旅行した際に一番苦労する発音がこのハンバーガーの Mc Donaldだということを見れば日本語がいかにアップビートを持たない言語かがよくわかる。
アフリカには、(人名も地名も) Nで始まる音が多い(例えば、ンドゥールとかいう名前の人がいる)。
以前、東京の本郷近くにある大きな音楽学校で何年か作曲を教えていたことがある。
いつも学生たちに課題の作品を提出させていたが、ある時、一人の学生がメチャメチャ面白い作品を提出してきた。
この曲、山下達郎のクリソツ作品(もちろん彼はワザと達郎風で作ってきたのだ)。
でも、実際に面白かったのは作品そのものではなく彼の歌唱の方。
自分で作ってきたカラオケをバックに彼はクラスで自作を熱唱した。
それがあまりにも達郎ソックリだったのでクラス中大ウケ。
でも、ここで見落としてならないのは、彼が達郎ソックリに歌うことができた理由だ。
彼は、すべての歌詞の前に、ほんのちいさな 「n 」の音を意図的に挟みながら歌っていた。
例えば、「♬きっとキミは来ない〜♬」なら「nきっと〜、nきみは〜、n来ない〜」と歌う。
これで(達郎)クリソツになる(でも、この時のn は本当に弱い微妙なnではないとダメなのでちょっと練習が必要だ)。
この達郎歌唱のカラクリをこの学生は見抜いていたのだ(ウソだと思うのならお試しあれ)。
つまり、ここが一番大事なポイントで、日本語の母音の存在が日本の洋楽にとって大きな障害になっていることに(ニューミュージック以降の)若い世代の音楽家はいちはやく気づいていたのだ。
そのために、サザンから始まった「日本語をいかに日本語らしくなく歌うか」の方法論をアーティストは皆それぞれ独自に考え続けているのだ(現在、ますますその傾向に拍車がかかっているような気がする)。
この「ことばが音楽や生活のスタイルを規定する」というかなり大きなテーマは、本来ならば文化人類学者たちが研究しなければいけない大きなテーマなのだが、そういうえらい学者先生たちは音楽にあまり関心がないようで、未だにそんな論文にも著書にもお目にかかったことがない(レヴィ・ストロースがほんの少しだけ触れているが)。
50〜60年代に ニューヨークフィルの指揮者だったレナード・バーンスタインが子供向けTV番組『ヤング・ピープルズ・コンサート』の中でこのことばと音楽の問題を、とても易しく明快に解説してくれていた。
しかし、私は、この「ことばと音楽」の問題に明快な解説を与えてくれた人をバーンスタイン以外まったく知らない。
70年代80年代ポップスの牽引役だったある著名な作詞家(女性)の友人と飲んでいた時、彼女がこんなことを言っていた。
「そのうち日本語のポップスから日本語がなくなって英語ばかりになってしまう日が来ると思う」。
え?アンタ本気でそんなこと考えてるのと突っ込んだものの、時代は確実にその方向に向っているんだろうなと思う時もある。
全てが母音にひっぱられる日本語が身体を確実に大地に着地させようとするのに対し、サンバやボサノバを歌うポルトガル語の音は確実に大地から離れ空中に浮遊する(このことをポルトガル語に堪能な友人のサンバ奏者が歌いながら解説してくれた)。
日本語で洋楽を表現する時必然的に起こる「違和感」は、本当に日本語を崩すことでしか解決できないのだろうか。