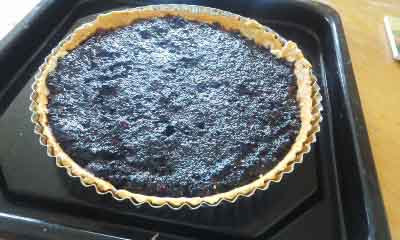長年、音楽を生業として暮らしてきた。
その立場から音楽療法というものにずっと関心を持ち続けてきた。
結果、いろんなものが見えてきた。
「音楽と音楽療法って何が違うの?」
この疑問は、プロの音楽家にとっても、音楽とは関係のない一般の人たちにとっても共通したものだろう。
果たして、私自身もこの疑問に完璧に答えられるかどうかの自信はない(というか、この疑問に完璧な答えを提供できる人が世界中に一体どれだけいるのだろうかとも思う)。
とはいっても、自身で「音楽療法研究会」なるものを主宰したり、音楽療法の臨床例を作っていく具体的な動きなどをここ数年さまざまに行なってきた身としては無責任なことも言えない。
日本の音楽療法が欧米から完全に出遅れているのは、一にも二にも実際の治療現場が少ないことに起因している(と私は思っている)。
ここでも、明治以降に始まった日本の音楽教育、音楽文化の普及運動と同じ過ちを繰り返しているような気がしてならない。
現在、日本の音楽家のレベルが(音楽のありとあらゆるジャンルで)欧米と比較して遜色ないことは誰もが知っている。
では、そうした優秀な日本の音楽家の人たちが音楽家として充分に生活していけるのだろうかというと、答えはノーでしかないだろう。
つまり、ことばを変えれば、日本に「音楽マーケットや音楽というニーズがどれだけ存在するのか」という問題に行き着くのだ。
ニーズがなければモノは売れない。
当たり前の話しだが、どういうわけか、日本ではお客さんが少ないのに、音楽や音楽家だけが過剰に生産されている。
だから、必然的に「音楽で食べていける人が少ない」というごく当たり前の現実が生まれてしまう。
なぜそうなったのか?
もともと日本社会になかった(西洋音楽という)ニーズを明治政府の役人たちが無理矢理作ろうとしただけの話し(かもしれない)。
それが150年たった今でも尾を引いている(のかもしれない)。
(江戸から大政奉還された)当時の明治政府が真っ先にやらなければならなかったことは、音楽家を育てるために留学生をヨーロッパに送ることではなく(「この時、宮内庁の楽師たちが勉強しにドイツに行った」)、「一般の人たちが音楽を楽しめるような環境」を作らなければならなかったはずなのだ(この結果が「鹿鳴館」では、「え〜?そうなの?!」だ)。
そうした社会底辺の音楽に対するニーズ作りにはまったく手をつけないで、いわゆる「ハコ」だけを先に作ろうとした。
これは、今も昔も変わらない(「お役所仕事」の典型)。
なにも劇場だけが「ハコ」ではない。
こと音楽文化に関していえば、「音楽家」だって「ハコ」の一部。
ただ、このことに音楽家自身も、聴衆も、お上さえも気がついていない。
音楽家は「クリエーター」という「ソフト」だから、けっして「ハコというハードなんかじゃない」と思いたいのだと思う。
音楽文化の担い手は一体誰なのか?
それは、紛れもなく一般大衆。ここが「ソフト」なのだ。
音楽療法だって同じこと。
まずもって、音楽療法ということばを勘違いしている。
音楽と音楽療法は違う。
すべてはここから出発しなければいけないはずなのに、この(音楽と音楽療法の)境界が未だにアヤフヤなままだ。
私の(個人的な)定義では、「音楽は、コミュニケーション」だと思っている。
それが「神とのコミュニケーション(あらゆる宗教に音楽は必須)」であれ、「自然とのコミュニケーション(これが、ダンスを含めたさまざまな儀式用の音楽を作る)」であれ、「人とのコミュニケーション」であれ、音楽とは「何かを伝え、受け取る」ために存在するもの。
だから、音楽家がステージで演奏する、それを聴衆が聞く。ここで「何か」が伝わらない限り、聴衆が感動したり心に何かを得ることはない。
すべての音楽家はここを理解するところから始めなければならない(と私は思っているのだが、現実はそうとばかりも言えない)。
そこで、改めて「音楽療法とは何か」を考える。
「音楽を使って、(人の)乱れてしまった心身のバランスを回復する治療、施術を行なうこと」。
病気というのは、心であれ、身体の一部であれ「本来そうあるべきバランスが崩れたり損傷したりしている状態」のことを指すはず。
「音楽療法」の定義としては、これだけで充分だろう(米国音楽療法学会では、もうちょっと難しいことばで定義しているが内容はこれとほぼ同じ)。
しかし、日本では、これを拡大解釈し過ぎているような気がしてならない。
私たちがよく行なう、病院でのコンサート、施設でのコンサート、デイサービスなどでの音楽まで音楽療法の一つだと思っている人は多い。
私は、厳密な意味では、違うと思う。
なぜなら、それは「治療目的」ではないからだ。
「心を癒すことも一種の治療なのでは?」と言う人もいるかもしれない。
しかし、その人の「心が癒されたかどうか」は、あくまで個人の問題(受け手の問題)だ。
40人の(さまざまな疾病の)患者さんを集めて同じ音楽を同じように演奏して40人全員が同じように癒されるなんてことはあり得ない。
それで、自閉症の子供の心が改善されるのか、パーキンソン病の人の身体の動きが改善されるのか、鬱病が改善されるのか….?
もし音楽療法を「治療の一つ(これがセラピーということばのもともとの意味だろう)」として使うのであれば、(当たり前の話しだが)一人一人の患者さんの生活や心、歴史、つまりその人自身の中身(プロフィール)と向き合わない限り、「何をどうやってどういう風に治療するのかを」決められるはずがない。
要するに、その人の「個人史」を傾聴することから始めなければならないし、現在の症状を詳しく観察しなければならない。
(「医は仁術」という考えからすれば)本来、医者も(クスリを処方する前に)同じ作業をするべきなのだろうが、そんな悠長なことをやっている医者はあまりいない。
個々人のキャラや育った環境などで、ひょっとしたら音楽なんか治療にまったく必要ないのかもしれない(むしろ邪魔になるかもしれない)。
一緒に歌った方が良いのかもしれないし、何か演奏を聞いてもらった方が良いのかもしれない。
あるいは、何かを一緒に叩いたりした方が良いのかもしれない(自閉症や行動障害の子供にはこうした方法を取ることが多い)、あるいは、一緒にダンスでも踊った方が良いのかもしれない(パーキンソン病の患者にはタンゴセラピーが有効とされる)…。
一人一人の人間の心の中に入り込まない限り、「音楽による処方箋」なんか作れるわけがないのであって、これを作っていく作業そのものが音楽療法だと言ってもよい。
先日、私が会長をつとめる伊東市介護家族の会主催で「米国認定音楽療法士佐藤由美子さんによる講演会<死に逝く人は何を思うか>」を市内の健康福祉センターで開いた。
これは、私の個人的願望(ホスピスでの体験豊富な佐藤さんの話しを聞いてみたいという願望)と「日本の社会や地元に音楽療法を根付かせるためにはどんな草の根運動が必要か」という思いから企画したものだった。
佐藤氏は、子供たちへの治療を主に行なう音楽療法士や高齢者を中心に行なう音楽療法士とは違い、終末医療の現場で行なう「見送りのための音楽」を専門的に行なう音楽療法士。
必然的にホスピスや終末緩和病棟などが現場の中心となる(佐藤氏のような存在は日本ではまだ珍しいが、おそらくこれからの時代はこうした音楽療法士が最も必要とされるのではと思う)。
この分野でも日本社会は立ち遅れている。
確かに日本の病院にも緩和ケア病棟はあるし、ホスピスもほんの少しはあるけれども、そうした医療現場(こうした現場ではもはや医師の出番は少ない)自体が日本には(欧米に比べて)圧倒的に少ない。
未だにほとんどの人が病院で人生を終え(あの世に)旅だっていくことが紛れもない現実だというのに…。
しかも、日本のホスピスは主に癌の末期患者に限定されている(これには、医療現場での複雑な政治的理由が存在するがそこには触れない)。
講演の中で佐藤氏は「アメリカの音楽療法士は7000人、日本は2700人とおっしゃっていたが、(別に佐藤氏の説が間違っているとか数字が違うとかいうことではなく)この数字は現実的にあまり意味がないのではと私は思っている。
なぜなら、日本で2700人というのは、あくまで(ある団体が発行した)音楽療法士資格を持っている人の数に過ぎない。
つまり、(司法試験や医師試験という国家資格は違う、ある民間団体が発行した)音楽療法士免状はもらったけれど、現実的にその免状の使い道がないのでは、それこそ(資格自体が)「絵に描いた餅」だ。
国家資格でもなく、ましてや保険点数にも数えられない音楽療法を診療科目にする医療機関がこの日本に一体どれだけあるというのか。
もちろん、まったくないわけではないのだが、どう考えても、この2700人全員が就職できるだけの医療機関や施設があるとは思えない(実際、ないし….)。
ということは、どういうことなのか。
要するに、日本の音楽療法士はほぼ全員「自称音楽療法士」ということになる。
いや、音楽家だって(国家試験がない以上)全員「自称音楽家」なんだからたいした違いはないじゃないかと反論する人もあるかもしれないが、「自称音楽家」と「自称音楽療法士」では意味あいがまったく違う。
自称音楽家(私も含めて)の音楽に満足するかしないかは(個々の音楽家を聞いた)その人の個人の自由。
それこそ、好きだから、嫌いだからという趣味嗜好の問題で片づけることも可能だが、「音楽療法」という「医療行為」では、単なる趣味嗜好の問題では片づけられない。
医療施術者としての(結果に対する)責任が問われることになる。
つまり、この部分での自覚が日本の「自称音楽療法士」には足りないから余計に音楽療法そのものが社会から信用されないということになってくる(今でも、他の多くの代替医療と同じように「音楽療法は胡散臭い」と思っている人は世の中に大勢いる)。
ここが、音楽療法がこの国で受け入れられない根本の理由かもしれない。
私は、ずっとそう思い続けてきた。
では、何をすれば良いのか。
「きちんとした音楽療法士を育てること(つまり、どういう教育をするかという問題)」と同時にこうした人たちが臨床を行なうことのできる現場をたくさん作ること(つまり、社会的なコンセンサスと医療機関や施設などとの連携や面密なプログラム作り)」が必要だと私は思っている。
「ニワトリ(治療現場)が先か、たまご(療法士の育成)が先か」という問題ではなく、この二つを同時に行なっていかない限り、いつまでたっても、この国での音楽療法の普及はないだろうと思う。