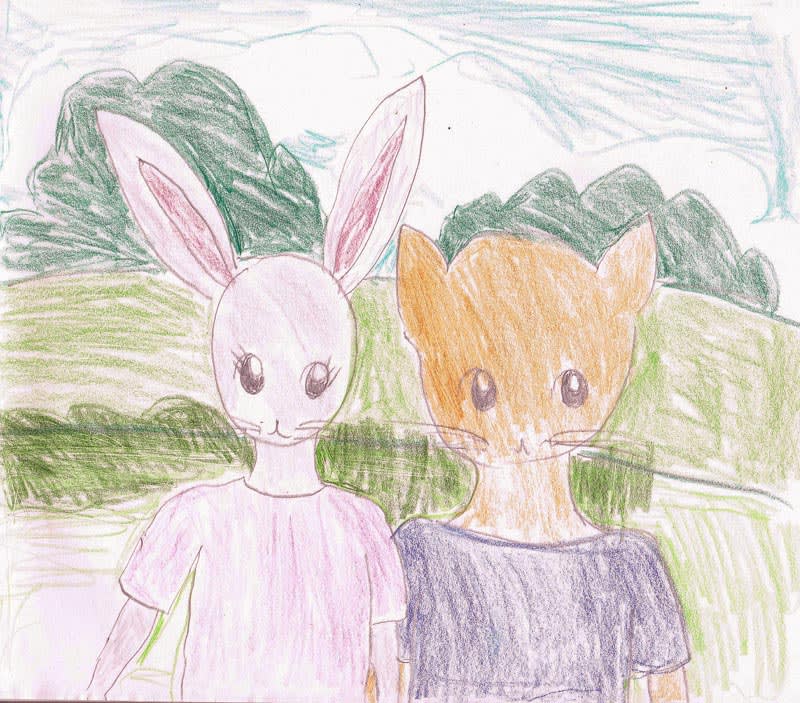十九世紀末、ノルウェーの貧しい漁村に住んでいる二人の姉妹。
この姉妹は、父が厳格なルター派教会の牧師で、父亡き後教会を守り村の人たちの監督牧師の役を引き受けて細々と暮らしている。
そこに住み着くお手伝いさんの名前はバベットさん。
もともとはフランスの三ツ星レストランの一流シェフだったバベットさんだが、1871年のパリコミューンの騒ぎでフランスを追われこの北欧の片田舎まで流れ着き姉妹の家の家政婦として働くようになる。
姉妹の毎日の暮らしを驚くほど豊かに切り盛りするバベットさんの唯一の楽しみはフランスの宝くじを買い続けること。
そして、ある日とうとう当りくじを引き当てる。
バベットさんは、姉妹や村人への感謝の印に昔働いていたパリの高級レストランのフルコース料理を当りくじで得たお金を全て使い果たしてもてなす。
これぞフレンチの極み!のような高級料理に対してわざと何も感じないフリをする村人たち(すべての快楽に対して禁欲的に生きるルター派にとって、カソリック信者のように味を楽しむことはある意味「罪」の一つだからだ)。
一方「こんな美味しいもの、フランスでも滅多に食べられない!」と目の前の料理やワインの蘊蓄を語る客の一人の将校。
この将校は、かつて姉妹の妹に恋心を抱いていた人。
晩餐が終わり招待された村人(姉妹も含めて)がこの上ない至福に浸る時、姉妹はバベットさんが「これが最後」と別れを切り出すものと覚悟する。
しかし、バベットさんの答えは意外なものだった。
「私は、また元の無一文になってしまったので、引き続き家政婦として働かせてください」と。
このことばを聞き姉妹は「(賞金を全部食事に使ってしまうなんて)なんでそんなバカなことをしたの」と唖然とする。
その問いに対する答えが「この世の中に貧しい芸術家はいませんから」というバベットさんのことば。
私は、この映画を最初に劇場で観た時、このことばを聞けただけでも映画を観た価値があったと思った。
しかし、原作ではもっと適確なことばで芸術の意味が説明されている。
バベットさん曰く「わたしは、すぐれた芸術家なのです。すぐれた芸術家はけっして貧しくなることはないのです」。
さらにこう付け加える「芸術家が次善のもので喝采を受けるのは恐ろしいことなのです。芸術家の心には、自分に最善を尽くさせて欲しいという世界中に向けて出される悲痛な叫びがあるのです」。
一番ではなくて二番で良いのではと言った政治家がいたが、世の中、最初から二番手を狙う人に何かを成し遂げられる人はいないと思う。
別に芸術だろうと科学だろうとスポーツだろうとどんな世界でも。
「芸術家が次善のもので喝采を受けるのは恐ろしいこと」。
私もそう思う。
だからこそ一切手を抜かずに全財産使い果たして最高のフレンチを村人たちにふるまったシェフ・バベットさんの味が「幸福」を招いたのだと思う。
『バベットの晩餐会』を書いたイサク・ディーネセンは、デンマークの貴族の家に生まれ嫁ぎアフリカに移住する。
しかし、夫のプランテーション経営は失敗し(しかも、夫は浮気で梅毒になってしまい彼女も感染させられる)離婚しデンマークに戻り作家として自立する。
しかし、まだ女性が自立して職業を持つことなど許されない時代だったため、彼女は、カレン・ブリクセンという本名を捨てて、イサク・ディーネセンという男性名で作家としての活動を始める。
それがこの『バベットの晩餐会』を書いた人物だ。
さらに、彼女の夫とのアフリカでのプランテーション経営破綻と恋愛の話しが、メリル・ストリープとロバード・レッドフォード主演の『愛と哀しみの果て(原題は”Out of Africa”)』という映画にまでなる。
『バベットの晩餐会』も『愛と哀しみの果て』もまだ観たことがないという人はぜひ二作ともご覧になることをお勧めする。
この2つの映画を既に見た人も、「『愛と哀しみの果て』でメリル・ストリープの演じる女性が、『バベットの晩餐会』を書いた人物なんだ」と思って見ればけっこう味わいも違ってくるだろう。
もちろん、私が一番注目してもらいたいのは、当時の北欧の貴族の生活でもアフリカの生活でもなく、「全財産を捨ててもなおかつ心を豊かに人を幸せにしてくれるもの、それが芸術なんだ」という点だ。
最近メディアで売れっ子になってしまった脳科学者の中野信子さんがどこかで(ご自分の IQの高さを例にあげながら)「IQの高さと人の幸せは比例しません」と言っていた。
当たり前じゃん。
そんなこと今頃気がつかれたのですか(と逆に彼女を突っ込んでみたくなる)。
実際は逆でしょう(とさえ思う)。
現実にはIQの高い人ほど、(お金や高い地位は得られるかもしれないけど)逆に、本当の幸せからは遠いのでは?
私の演奏(音楽)で誰かが幸せになれる。
もうそれだけで、私(自身)は貧しさから解放されている(ということになるのだ)。
バベットさんの料理で人が幸せになる。
この喜びを与えられる人たち(すべての芸術家)が貧しいわけはない。