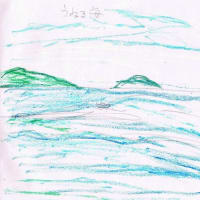四六時中どこかで戦争をやっているアメリカという(トンデモナイ)国に私が留学したのは七十年代後半。
あの泥沼のベトナム戦争が終わった直後だった。
大学のキャンパスのあちこちには至るところにまだ(学生たちの)反戦運動の名残りがあった。
と同時に、実際に戦場で戦い負傷しながら帰還したベテラン兵士(退役軍人を英語でveteranという)たちの姿も大勢キャンパスで見かけた。
私にとっては、日本で大学を卒業した後の学士編入だ。
否応無しに日本のキャンパスの風景とアメリカのそれを比較してしまう。
それがベトナム戦争直後だったからなのか、それともアメリカの大学ではそれが普通の光景なのか、私が最初に目にしたキャンパスはあまりにも「奇異」だった。
奇異ということばが適切なのかどうかはわからないけれど、私の素直な感情からすればそのことばが一番ピッタリきたような気がする。
それはそうだろう。
片方の手を切断してしまった人たち。あるいは両足を失ってしまった人たち。
いや、それどころではない。両手両足を持たない人たちだってキャンパスの中を(介助の人の助けも借りずに)自由に闊歩していたのだ。
それを「普通の光景」として受け入れられるほど、私はまだ「アメリカ」に慣れてはいなかった。
しかも、さらに私がもっと奇異に思ったのは、彼ら(その頃はまださすがにキャンパスの中で「ベテラン女性」の姿を見ることはなかったが)の異様なほどの明るさだった。
キャンパスを車椅子で移動する時の彼らの「ドヤ顔」も、教室に入ってくるなりいきなり机や椅子を電動車椅子でけちらして自分の場所をしっかりと作る(いささか乱暴な)「縦横無尽さ」もしっかりと未だに目に焼きついている。
もちろん今日本の街中で車椅子で移動する人たちを見ることはそれほど珍しい光景でもなくなった。
しかし、その時見たアメリカ人の表情と私が今日本で目にする車椅子の人たちの表情はどこかが決定的に違う。
どこが違うのか。
なぜかすまなそうに車椅子の上にいる人たちの多い日本の状況を見るにつけ、「別に悪いことをしているわけではないのになんでそんなに肩身の狭そうな表情をするのだろう」とつい思ってしまう。
それは、どこか健常者と対等な関係ではない今の日本の身障者の立場がそうさせているのでは…。
私は、そう思わずにはいられないのだ。
それは、老人介護の現場でも同じこと。
けっして老いることが罪悪なわけではないし(誰しもそうなるのだから)心や身体に障害があることだってけっして自分たちがそうなりたくてなったわけではないにもかかわらず世の中全体がどうもそんな(不平等な)関係を作りだしてしまっているように思えてならない。
障害者も老人も時に社会のお荷物的に扱われてしまうことだってある。
どうしてなんだろう、と思う。
日本の社会ってもっとお互い労りあって優しい社会だったはずなのでは。
やはりお金のせいなのだろうか。
老人や身障者が労働の対価を生み出しにくい存在だからなのか。
生産性の低い存在だからなのか。
ここ数十年の間に金融資本主義経済が日本人のいたわりあう心まで破壊してしまったのか…。
ここで私が思い出すのが、福祉の先進国家である北欧デンマークにある「高齢者三原則」だ。
これは、「自己決定の尊重」「自己資源の活用」「継続性の維持」という三つの原則のこと。
つまり、「高齢者自らが決定した暮らし方を尊重して,高齢者の残っている自己資源(残存能力)を活用して,高齢者の生活をできるだけ変化させずに支援する」という考え方だ。
だから、デンマークには、基本的に「介護」という思想がない(ことばぐらいはあると思うが)。
あるのは、高齢者が自立して生きられる社会を作る、という思想だけ(この高齢者ということばを身障者に置き換えても同じ意味になる)。
そんなこと当たり前じゃん、と私は思う。
「介護」ということばがあるからこそ、人と人との間に「介護してやる」「介護してもらう」という対等ではない関係が生まれてしまうのだ。
私がこれまでずっと介護施設で行ってきている「音楽サービス」は全て有料だ。
この「三原則」からすればこれも至極当たり前のこと。
この三つの原則を守るには介護する人と介護を受ける人が同じ目線に立たなければならない。
これ(同じ目線に立つこと)こそが本当の大原則。
どんな人間関係においても上下や優劣の関係があってはならない。
私はそう思っている。
そのための「有料」の音楽なのだ。
有料である限り、サービスをする側には「結果」を出すという「責任」が生じる。
だから、「介護してやってる、サービスしてやってる」という態度は絶対に取れないのだ(ここを勘違いしている介護士、看護士が時に施設内で問題を起こしたりする)。
有料だからこそ生まれる「対等な」関係なのだ。
無償のボランティアでは必ずどこかに「やってあげている」「やってもらっている」という目線のズレが生じる(このことに気がつかない人も案外多い)。
これで初めて相手の「個」を尊重し、その人の「資源(つまり人生や人となり、能力)」を考えながらサービスを持続的に行っていくという「三原則」が実現可能になってくるのだ。
日本の介護は、そこをまったく勘違いしている。
タダで「施す」のが介護であり福祉だというとんでもない勘違いを社会全体がしている。
こんな失礼な話(国)もないだろう。
こんな相手をバカにした話もないではないか。
こんな無礼を思いやりだと勘違いしている限り、日本人の「おもてなし」も一方的な押し付け、押し売りにしかならない。
そろそろバリアフリーなんていう和製英語を使うのはやめて、きちんとユニバーサルデザインの一つとして「おもてなし」の意味やノウハウを考えていかないといつまでたっても日本は「幸せな国」にはなれないのではないのか。
少なくともオリンピック、パラリンピック開催までにはこの意識だけでも持てるようにして欲しいと切に願っているのだが。
あの泥沼のベトナム戦争が終わった直後だった。
大学のキャンパスのあちこちには至るところにまだ(学生たちの)反戦運動の名残りがあった。
と同時に、実際に戦場で戦い負傷しながら帰還したベテラン兵士(退役軍人を英語でveteranという)たちの姿も大勢キャンパスで見かけた。
私にとっては、日本で大学を卒業した後の学士編入だ。
否応無しに日本のキャンパスの風景とアメリカのそれを比較してしまう。
それがベトナム戦争直後だったからなのか、それともアメリカの大学ではそれが普通の光景なのか、私が最初に目にしたキャンパスはあまりにも「奇異」だった。
奇異ということばが適切なのかどうかはわからないけれど、私の素直な感情からすればそのことばが一番ピッタリきたような気がする。
それはそうだろう。
片方の手を切断してしまった人たち。あるいは両足を失ってしまった人たち。
いや、それどころではない。両手両足を持たない人たちだってキャンパスの中を(介助の人の助けも借りずに)自由に闊歩していたのだ。
それを「普通の光景」として受け入れられるほど、私はまだ「アメリカ」に慣れてはいなかった。
しかも、さらに私がもっと奇異に思ったのは、彼ら(その頃はまださすがにキャンパスの中で「ベテラン女性」の姿を見ることはなかったが)の異様なほどの明るさだった。
キャンパスを車椅子で移動する時の彼らの「ドヤ顔」も、教室に入ってくるなりいきなり机や椅子を電動車椅子でけちらして自分の場所をしっかりと作る(いささか乱暴な)「縦横無尽さ」もしっかりと未だに目に焼きついている。
もちろん今日本の街中で車椅子で移動する人たちを見ることはそれほど珍しい光景でもなくなった。
しかし、その時見たアメリカ人の表情と私が今日本で目にする車椅子の人たちの表情はどこかが決定的に違う。
どこが違うのか。
なぜかすまなそうに車椅子の上にいる人たちの多い日本の状況を見るにつけ、「別に悪いことをしているわけではないのになんでそんなに肩身の狭そうな表情をするのだろう」とつい思ってしまう。
それは、どこか健常者と対等な関係ではない今の日本の身障者の立場がそうさせているのでは…。
私は、そう思わずにはいられないのだ。
それは、老人介護の現場でも同じこと。
けっして老いることが罪悪なわけではないし(誰しもそうなるのだから)心や身体に障害があることだってけっして自分たちがそうなりたくてなったわけではないにもかかわらず世の中全体がどうもそんな(不平等な)関係を作りだしてしまっているように思えてならない。
障害者も老人も時に社会のお荷物的に扱われてしまうことだってある。
どうしてなんだろう、と思う。
日本の社会ってもっとお互い労りあって優しい社会だったはずなのでは。
やはりお金のせいなのだろうか。
老人や身障者が労働の対価を生み出しにくい存在だからなのか。
生産性の低い存在だからなのか。
ここ数十年の間に金融資本主義経済が日本人のいたわりあう心まで破壊してしまったのか…。
ここで私が思い出すのが、福祉の先進国家である北欧デンマークにある「高齢者三原則」だ。
これは、「自己決定の尊重」「自己資源の活用」「継続性の維持」という三つの原則のこと。
つまり、「高齢者自らが決定した暮らし方を尊重して,高齢者の残っている自己資源(残存能力)を活用して,高齢者の生活をできるだけ変化させずに支援する」という考え方だ。
だから、デンマークには、基本的に「介護」という思想がない(ことばぐらいはあると思うが)。
あるのは、高齢者が自立して生きられる社会を作る、という思想だけ(この高齢者ということばを身障者に置き換えても同じ意味になる)。
そんなこと当たり前じゃん、と私は思う。
「介護」ということばがあるからこそ、人と人との間に「介護してやる」「介護してもらう」という対等ではない関係が生まれてしまうのだ。
私がこれまでずっと介護施設で行ってきている「音楽サービス」は全て有料だ。
この「三原則」からすればこれも至極当たり前のこと。
この三つの原則を守るには介護する人と介護を受ける人が同じ目線に立たなければならない。
これ(同じ目線に立つこと)こそが本当の大原則。
どんな人間関係においても上下や優劣の関係があってはならない。
私はそう思っている。
そのための「有料」の音楽なのだ。
有料である限り、サービスをする側には「結果」を出すという「責任」が生じる。
だから、「介護してやってる、サービスしてやってる」という態度は絶対に取れないのだ(ここを勘違いしている介護士、看護士が時に施設内で問題を起こしたりする)。
有料だからこそ生まれる「対等な」関係なのだ。
無償のボランティアでは必ずどこかに「やってあげている」「やってもらっている」という目線のズレが生じる(このことに気がつかない人も案外多い)。
これで初めて相手の「個」を尊重し、その人の「資源(つまり人生や人となり、能力)」を考えながらサービスを持続的に行っていくという「三原則」が実現可能になってくるのだ。
日本の介護は、そこをまったく勘違いしている。
タダで「施す」のが介護であり福祉だというとんでもない勘違いを社会全体がしている。
こんな失礼な話(国)もないだろう。
こんな相手をバカにした話もないではないか。
こんな無礼を思いやりだと勘違いしている限り、日本人の「おもてなし」も一方的な押し付け、押し売りにしかならない。
そろそろバリアフリーなんていう和製英語を使うのはやめて、きちんとユニバーサルデザインの一つとして「おもてなし」の意味やノウハウを考えていかないといつまでたっても日本は「幸せな国」にはなれないのではないのか。
少なくともオリンピック、パラリンピック開催までにはこの意識だけでも持てるようにして欲しいと切に願っているのだが。