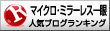KENJIさん殺害のニュースが流れてから1週間が経過した。一時期SNSではこれに関する書き込みであふれたが、それも落ち着き、国会での討論やマスコミでの専門家の分析などが目立つようになってきた。
特にSNSでは一時期、割と感情的な論調が散見されたが、すぐに落ち着いたようだ。今回の場合、やはり相手がよくわからない、という要素が大きい気がする。
今回の件が、日本とヨルダンの世論を動かすため、という意図は何となく読めてきたような気もするが、単なる暴力集団というわけでもなさそうだし、かといってわかりやすい争点(自分たちの生存権を確保したいというような)ではなく、なんらかの理念はあるらしいがそれが見えてこないし、ということで、攻めあぐねているようだ。
高橋源一郎氏がテロリズムに関してつぶやいたことを、ハフィンポストがまとめている。
高橋源一郎さん、テロ撲滅の方法は「この世界が生きるに値する場所だと信じさせること」
彼はヨルダン人パイロット殺害ビデオについて、その構成にある種の美意識を感じるとし、彼らは非人間的な野獣ではなく、人のの心を持っているはずだ、それ故により余計恐ろしい、としている。
そして、彼らが「死」について惹かれているのではないかとし、単に彼らを非難し否定しても、それこそが彼らの喜びとなるのだから無駄ではないか、と指摘する。また、(彼らの理解のポイントとなる)テロリズムは絶望から生まれるものであり、その源となる「人間的共感の完全な欠如」は、私達の周りにもテロリズムとは別の形で存在している。この世が生きるに値する場所だと信じさせることしか、彼らを滅ぼすことはできない、と結論づけている。
高橋氏はナチスドイツのメンゲレ博士を(美意識を持ちながら一方で残虐行為をした人として)例示しているが、テロリズムが一種の美意識に貫かれているというのは一般的によく知られていることではないかと思う。テロリズムに限らず、一般に戦争行為は死を賛美し美化しようとする。ISISにしても、その思想や行動の根本は「美」にあることに違いはない。むしろ、現実が苛烈になるほど、「美」に救いを求めていくのかもしれない(その「美」が、一般に受け入れられるものであるかどうかは、ここでは置いておく)。
そうした、表面的なものをはがしていくと、おおもとは何らかの圧政や迫害行為、貧困などが彼らを駆り立てているのではないか、と思えてくる。とはいえ、愛を知らずに育った子供が素直に人の好意を受け入れられないように、その解決は決して簡単なものではないだろう。
先ほど、SNSの論調について触れたが、僕自身もこんなケースに触れた。
知人の中国人の方が、SNSでKENJIさんの報道に触れ、これからは日本もテロの対象になっていくだろう、これまでは子供をアメリカ留学させることについて、治安に不安があることがネックだったが、今回の件で(治安については)日米共にその違いはなくなった。就職する頃には(安全と思われる)中国で働かせたい、ということを書いておられた。
ちょっと心に触れるものがあって、こういうデリケートな話題は慎重に・・という趣旨のことを(一応きつくならないように英語で)コメントした。ネットでこの種の話題に何か書くのは、僕個人としては異例のことだ。コメントは報道直後にされたが、いまなら何も書かなかったかもしれない。
ただ、いずれにせよこの方の認識は正確ではないと思う。今回は偶々渡航した日本人が標的になったが、日本国内のイスラム教徒はきわめて少なく、宗教的な問題や諍いは皆無である(それ故に、今回の件は余計ショックだったのだ)。中国は内陸部に多数のイスラム教徒がいる。新疆ウイグル自治区はじめ、少数民族問題は深刻であり、実際にテロ事件も近年多数起きている。今はそれが国際的に(ISISなどと)結びついていないだけの話だ。
話は飛ぶが、いわゆる「イスラム国(al Dawla al Islamia)」の呼称について、さいきんはダーイシュという言い方も普及してきたように思える。政府での呼称はISILあるいはISISと言うようになったのかしら?マスコミはまだいわゆるイスラム国が標準のようだけど。どちらにしてもわかりにくさに輪を掛けているようだね・・。