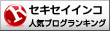内田樹 文春文庫
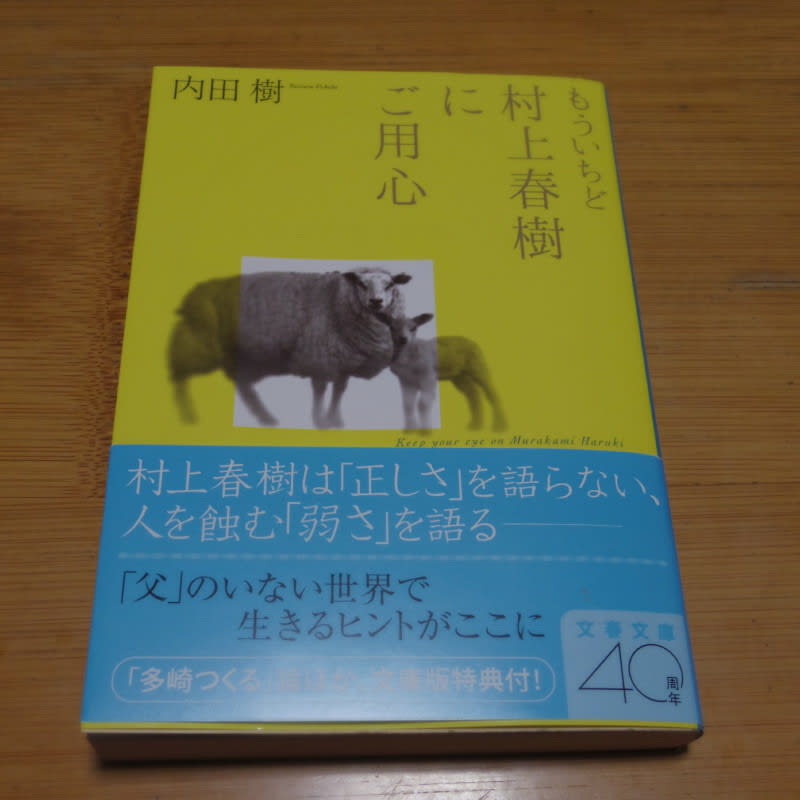
昨年暮れに、書店をのぞいたときに平積みされていたのを思わず手にとった。
いわゆる村上春樹解釈本である。現代の作家でこれほど解釈本の出ている人も珍しいと思う。
「村上さんのところ」で村上氏が、そういう解釈本を読んだことはない、読者も、自分で考えられた方が良いと思う、と書いているが、僕も面白そうだとは思いながら、解釈本は読んだことはなかった。
しかしこの本はちがう、といいたいところだが、どうやらこの本はあちこちに内田氏が書かれたコラム等の寄せ集めらしく、いささかまとまりがない。さすがに学者さんらしく、書かれた文章はとても鋭いけれど。
にもかかわらず、この本を取り上げたのは、氏の世代としての経験を書かれていた部分が心に引っかかったからだ。
柴田元幸氏との対談で、彼らの世代間の違いについて触れた部分がある。1954年生まれの柴田氏は、すぐ上の世代(内田氏や、村上氏も含まれる)、いわゆる紛争世代の人たちが苦手だという。
とても話し辛いのだそうだ。なぜ話し辛いかと考えたところ、この人たちはただ威張りたいだけなんだ、と思い当たったのだという。
内田氏はそれに賛成し、数が多いから威張れたのだろう、更に進んで、多数派の中で孤立しているときも、そういう自分って偉いという感覚を持っていた、多数でも威張り、少数でも威張っていた、と述懐している。
1970年前後のことについて、内田氏は「60年代の終わりは祝祭的な時間だったのですが、'70年の夏ぐらいからピークダウンして・・・すーっとダークな時代に入っていく。・・だんだん陰惨になって・・とにかく時代がキリキリととがっているような感じ。大学の中は空気が肌に突き刺さるようでしたね。」と語る。
この辺のことは、そこにいなかった僕には肌で感じられない感覚だ。厳密に言えば、僕には僕の('70年前後の)身体感覚はあるのだが、それは幼児として、家族の一員としての感覚だ。子供の頃、大学生の知人はいなかったし、僕が大学生になった頃には、内田氏の世代の人はいなかった。 同じ大学生でも、内田氏の世代と僕等は全く違う学生生活を送ったのだと思う(ついでに言うと、いま一緒に働いている会社の子もまた、僕等とは違う学生生活を送っていたようだ)。
彼らを知るようになったのは、社会に出てからだ。既に中堅以上のポジションにいた彼らは、噂通り異質で個性的だった。
この世代感覚の違いが、村上氏の文章を読んで、理解できなかった部分の理由なのかな、と思えてきた。