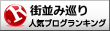今でも伝統的な純和風建築は、しかるべきところに頼めば建ててもらうことはできると思うが、一般的にはそのような建築に身近に触れること自体があまりなくなりつつある。
不動産関係も建築関係も素人なのであれだが、普通の住宅は僕らが子供の頃に比べても、和洋折衷の洋の割合がさらに高くなってきているように思う。そのほうが受け入れやすいのだろう。集合住宅でも、畳の間がある部屋は人気がない、と聞いて、驚いたことがある。
鉄筋コンクリートの家に作られる和室は、尺貫法の概念が通じない(これは大昔の団地の頃からそう。畳やふすまのサイズが一回り小さい)ことからして、和風建築とは異質なものだ。ふすまも、つくりとしては洋間の引き戸の表面だけ和風にしたもの、ということが多いようだ。

古い住宅のふすまは文字通り木と紙でできていて、現代の感覚ではいかにも頼りなげな感じがする。おそらく工作には職人技を要し、耐久性もベニヤの太鼓より相当劣るだろう。
(もっとも、すべての和風建築がそういう作りであったかはわからない。偶々前宅はそんな作りのふすまだったが、例えばお城のようなところはまた違う作りであるような気がする)。
前宅は昭和後期の木造住宅で、当時なりのモダンさと伝統を融合させたものだった。
今見るといかにも昭和(40年代)の日本家屋という感じだ。よく人には「のび太君の家みたいだ」と言っていた(漫画の設定ではかなり広い家らしいが)。
これとて、見る人が見たら随分と洋風でモダンな建て方だね、と思われるかもしれない。
昔の家は、畳の間がいくつかあっても、ふすまを外すと続きの広い間取りになるような作りが多かった。
来客時などはフレキシブルに使えて便利だが、プライバシーの観点から見るとかなり劣る。
前宅の場合、4つの部屋がすべて壁で仕切られていた。この点、当時としては(思想的に)新しかったのだと思う。
よく、昭和時代などとひとくくりで呼ぶとき、それはおおむね1960年代の前半ぐらいの時代を示していることが多いようだ。
各地に団地が建てられ、より西洋風な意匠を取り入れたアコモデーションが流行した。
それは一つの時代としては画期的だったことは確かだが、建築の流行はその前にも、そのあとでも変化している。障子窓がガラスになり(これは戦前からの流れ)、アルミサッシが普及する。それも最初は銀の地色だったものが、黒く染色され、ガラスも厚手のものが主流になる。
ひとつひとつの建物も、時代によってかなり変化があるが、それらがまとまった街となると、新旧様々な様式の建物が、少しずつ表情を変え、街を行く人々、自動車、ポストや電信柱、看板などが時代の移り変わりとともに変化していく。「三丁目の夕日」だけが「昭和」なわけではない。僕らの生きていた「昭和」は、また全く別の世界だった。
どんなものが和風といえるのか、なにがオーセンティックな和風建築なのか、という問いは難しい。ある意味ではどのような建物であれ、この国の歴史上存在した建物は全部和風だともいえるのかもしれない。