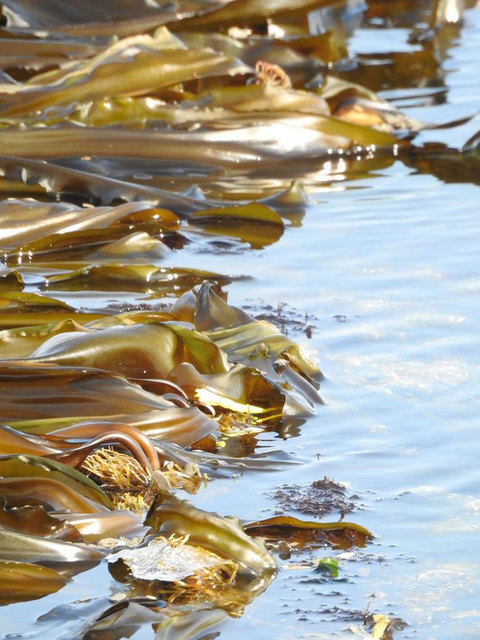春菊・風邪予防
春菊の硬い部分を落とし、熱湯で茎の方から塩茹でしてさっと冷水にとりザルに上げる。
醤油適宜を全体にふって(醤油洗い)、ぎゅっと絞って4cm幅に切る。
半すりにしたクルミやごま、蜂蜜、醤油少々を混ぜたものと茹でた春菊を和えます。
以蔵保蔵と言って脳の形に似ているクルミは脳を活性化させる効能があり、良質な脂質は便秘解消にも有効です。
ビタミン、鉄分、カリウム、カロテンなどが豊富な春菊と合わせると相乗効果があります。
春菊は胃腸の調子を整え、不眠、よく夢を見る(多夢)、むくみ、貧血などの気になる症状がある方にお勧めの野菜です。
ペリルアルデヒドなどの独特の香り成分は気の巡りをよくし、イライラを静める効果が期待できます。
豚汁(とんじる)・健長汁・巻繊汁(けんちんじる)
乾燥するこの季節は喉や体を潤す根菜や果物が多く出回りますね、大根、蓮根などは喉にも良い野菜です。
肌寒くなってくると、温かい汁ものを作りたくなります。
けんちん汁と豚汁は似ていますが、作り方が違うのをご存知ですか?
けんちん汁は約750年ほど前、鎌倉の(建長寺)で崩れてしまった豆腐と野菜を煮込んだのが始まりと言われる精進料理。
ごま油で野菜などを炒めてから昆布や干し椎茸の出汁を使い醤油風味で仕上げます。
豚汁は野菜と豚肉を鰹出汁で煮込み、味噌で仕上げたものです。
ですが、いいとこどりのミックスをしてコクをだすのが美味しい、多めに作って3日間くらい楽しみます。
発酵茶・烏龍茶・台湾茶

台湾茶のお茶のいれ方や所作はゆったりしたムード、とてもリラックスします。
いれ方一つで美味しさが変わります、しっかり楽しみたいので、台中にある台湾茶館の師匠に教わった通りに、急須や茶器を温め、茶葉によって置き時間も異なる事をしっかり把握していれるようにし、楽しんでいます。
いただく時は、まず香りを楽しんでから口に含みます、同じ烏龍茶でも味わい、喉越し、香りがそれぞれ違って、蜜や花の香りがするものもあります。
阿里山烏龍茶、金せん茶烏龍茶など素敵です。
上質な茶葉は寒暖の差が激しい高山で収穫されますが、選ばれた茶葉は摘まれる時間も決まっていて早朝の4時〜10時頃までに行われ、ハサミも使わない手作業だそうです。
香りがあんまり良いので、茶葉を包んで黒豆の蜜煮に加えてゆっくりと煮てみたらスッキリとしてほんのり香りが残る、これが大正解!
黒豆好きの私には来年の御節の目玉になりそうです。
茶葉の香りは気の巡りを良くし、発酵茶は体を温めます、忙しくなる年末の休憩時にピッタリのお茶です。