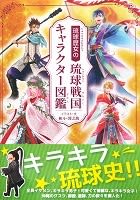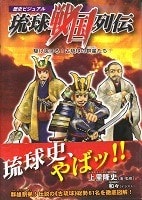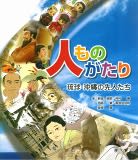「テンペスト」に負けずとも劣らない、
MY fovorite book「百十踏揚」
テンペスト三昧の今日この頃ですが、
久しぶりに「百十踏揚」から、行脚記事を書いてみましょうか。
■勝連城跡/四脚門跡■

「何年ぶりか……」
二度目の京旅は、豪壮絢爛たる寺々、公家館などにも見覚えがあり、
こんどはゆっくりと、それらを眺め渡す心のゆとりもあった。
公家の館や門構えなどを見上げて、
「立派な門だな。こんな門を、勝連にも構えたいものだな」
と、阿麻和利が呟くのへ、
すかさず津堅が、
「帰国したら、勝連城に建てましょうぞ。
このような門を構えれば、勝連城はまた一段と、
見事なものになりましょうぞ」

*
勝連城内に、大和の公家館の四脚門に似せた、
檜の楼門が建ったのは、それから間もなくであった。
公家館の門は板屋根であったが、
こちらは高麗系の大瓦を乗せ、
門柱や棟は赤と黄の彩色を施した。
これによって、勝連城はまた見違える豪壮な趣を備えた。
「百十踏揚 191-」(与並岳生著/新星出版)

天下を揺るがした「梟雄」阿麻和利。
―――これを討ち滅ぼして、鬼大城の武勇は、また一段ととどろき渡った。
勝連凱旋後、鬼大城にはまず戦功として、
勝連城から持ち帰った戦利品の中から、
阿麻和利の「錦緞衣装」と
勝連城の楼門が授けられた。
「百十踏揚 569-」(与並岳生著/新星出版)

勝連グスクからは瓦が出土しています。
当時、瓦は非常に高価なものであり、
瓦が出土するのは5箇所のみだそうです。
首里城、
首里城隣の崎山御嶽、
前王都である浦添グスク、
久米村のあった那覇、
そして勝連グスク。
そのことからも当時の勝連が
いかに特別で、力を持っていたのかが分かるのです。
ちなみに勝連グスクから出土した瓦は
グスク下の資料館でも見ることができますよ。

そして、
過去記事「その後の大城賢雄」でも書いてますが、
勝連戦後、この四脚門を賜ったのは
大城賢雄なんですねー。
わざわざ門を解体して、首里まで運んだんですね。
勝連グスクの四脚門が、
それほどのものであったということが、想像できますね。


歴史ブログ 琉球・沖縄史
記事や写真がお気に召しましたら
ぽちっと応援お願いします♪
最近クリックが少なくてちょっとサミシイ…(;_ ;