草稿記事を完成させての、アップです。
先日、2012.2.19の朝日新聞
PTA反響編:上〈どうする?〉
で、文科省の現時点での見解が示されました。
120219朝日新聞【PTA反響編:上〈どうする?〉】任意加入周知に波紋
拙ブログ過去記事(上記)から、一部を再掲します。
(赤字:引用者)
--- 引用ここから ---
********
Q 会員でない子どもはPTA行事に参加できる?
A PTAは子どもたちの健全な成長をはかることを目的とした団体。個別の行事が、特に「会員の子ども限定」などと役員会で定められていない限り、一般的には参加できる
(文部科学省社会教育課)
********
この、Q&Aの、文科省社会教育課の見解には、大きな疑問を覚えます。
子どもは会員ではありませんし、
児童を差別するような団体が、公共の場である学校で
活動していいものでしょうか。
我が子のため、会員の子のためのPTA活動ではないでしょうに。
大人が、いじめを教えてどうするの?
--- 引用ここまで ---
これに対し、ライラパパさんから、下記のコメントが
寄せられました。
--- 引用ここから ---
大きなルールの上にのったローカルルールであってほしいですよね。
(中略)
また大きなルール「法律」ですが難しいですよね。
社会教育法には罰則規定がありませんから「絵にかいたモチ」程度になっていると考えます。
判例が出ていれば「こうじゃないのか」と言いやすいのですが、判例がなければ難しいですね。
と言う事は「判例が出るまではどちらでも主張できる」と解釈できます。
役所が曖昧な対応をしていたとして、また国民、住民である保護者が指摘していたとしても何ら問題ないという事です。
--- 引用ここまで ---
> 多くの方が主張されるように、PTAがただのサークル(社会教育関係団体)の一つだとすれば
> 規約に「会員の子ども」と謳うことも可能で、別段問題ないということになりうる?気がします。
今回の新聞記事での(2/19)文科省見解は、まさにおっしゃることに当たるのでは、と思います。
> そういう方向にかじ取るところが出ないとも限らない気もします。
現実問題、そうでしょうね。
「会費を払わない&労働力も提供しない変わった親の子どもには、サービスをする価値がない」などと考える人は、実際にいますから。
(人として残念です。)
ですが、わたしはこう考えています。
PTA規約は、あくまでもローカルルール。
PTA規約の上に、区市町村の条例があり、その上に都道府県の条例があり、その上に法律があり、さらに上に憲法がある。
そして、さらに日本が批准した国際条約があります。
ローカルルールは、この枠組みを外れて設定されてはなりません。
例えば、1994年5月に日本が批准した
「子どもの権利条約」にはこう謳われています。
*****
第2条
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
***** ![]() http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
「子どもの国際権利条約」まで話を持って行くと、やや大げさかも知れませんが、児童の差別は、いかなる場合もしてはいけないんだという国際的な大原則を、確認しておきます。
子どもの権利を変な風に振り回すまえに、親の責任をきちんとまっとうしたいものだとも、考えます。

















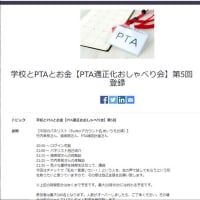

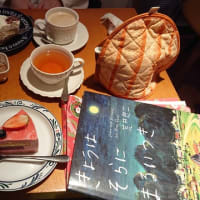
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます