PTAから学校に寄付をして、その後気になる結果になった二つのケースをご紹介します。
一つ目。
拙ブログ過去記事に、昔いただいたコメントです。ずっと自分の中でひっかかっています。
120226朝日新聞【PTA反響編:下〈どうする?〉】会費が学校の「第二の財布」?
の3コメント目です。
*** 赤字太字by猫紫紺 ***
寄付については (元役員)
市Pの役員の時、学校遊具の修繕費を要望しようと思い、市内小中学校に調査(アンケート)をかけました。多くの遊具が使用不可の状況になっていることもそうだったのですが、各学校、地元の方やPTA、地域の名士の方からの寄付された遊具(特に木製遊具)の多いことにびっくりでした。(昔です)何かしてあげたい、またその余裕もあったのかもしれませんが本当の好意からの寄付だと思います。
今は当然公費での修繕費はつかないし、撤去にも費用がかかる。悩ましい問題です、特に物は減価償却していきますからね。実は遊具修繕費(あくまで公設)は最初の予算査定はゼロ査定だったみたいですが、市Pとして要望した後の復活折衝で予算をつけてもらえたと聞きました。
どこまでが公費でどこから私費か?
***
このケースは、PTA連合が行政に働きかけて、過去に寄付された木製遊具の撤去ないし修繕の予算をつけてもらったとのこと。
寄付を検討する場合、物品の持ち主とメンテナンスの責任はどこ?
ということをクリアにする方がよさそうです。
2つ目。
地域の行事(お祭り)に、行事主催者のための炊き出し用大鍋を卒業生が寄付したケース。
こちらは、公費とはまた別の話ですが、PTA活動には関連してきます。
そのお祭りは地域行事のため、多くの地域団体、スポーツ少年団、各学校PTAが関わっています。PTAの場合、「有志」をうたっている学校もあるのですが…
その学校では、大なべの出所が、我が校の先輩の寄付、ということで、地域行事にPTAからいつも人を出すことになっています。
こういうケースがいいのか、悪いのか私にはわかりません。個人的にひとつ言えるのは、先輩の行動で、後代が役目に縛られてしまうのはチト厳しいと思う口です。
遊具の寄付もお祭りへの援助も、最終的には「子どもがよろこぶ」ことをめあてに行っているものでしょうから、善意が困ったことになる例といえましょうか。
(地域振興・地域連携とPTA、暮らしと体調の両立ってほんと難しい、 という立場です。)
寄付と言ってもなかなかに難しいと思うこのごろです。
なお、文科省としては「真に自発的な寄付」ならば歓迎、というスタンスのようです。
PTAの源流の書類を紐解くと、高邁な理念もなんのその、「資金集めはどうする?」的な文章がでてきたりします。日本のPTAは、寄付文化のアメリカ型PTAをお手本としているのですから、それも当然といえましょうか。少なくとも、足りない公費をPTAが補完するという実態(2012に読売新聞等で報道:一例)は、終戦直後のしっぽを引きずっていると思います。
お金って、満足したらもっと欲しくなる性質のものですし…
公金の使いづらさというものがあるようですし。よくわかりません。
そう、PTAで無償労働をするのもいいけれど、税金払うくらいいっぱい働くのも、現代的で意義ある道のひとつだともいえると思うのです。
追記:140130 改題しました。

















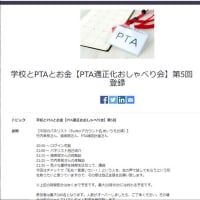

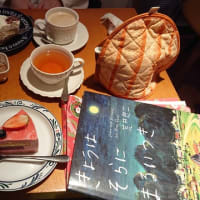
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます