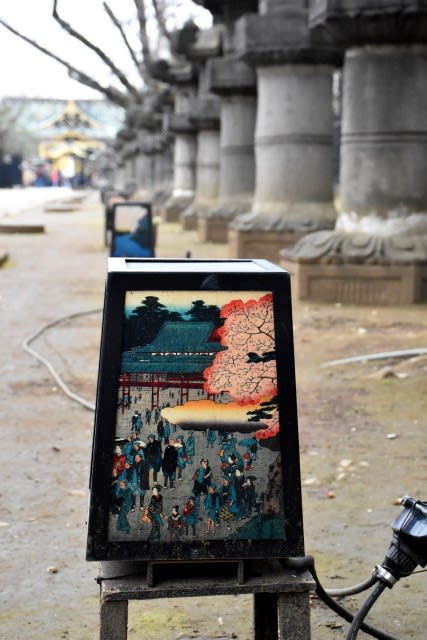ダイサギ、チュウサギ、コサギ、
一般に白鷺と呼ばれる白い鷺たちです。
その中で一番小型なのがコサギ、
一年中比較的よく見られる留鳥です。

河原の砂地に白い鷺がやってきました。
嘴が黒色、コサギです。

コサギ、
嘴と脚が黒色、
足はイエロースリッパと称され、
黄色で体に似合わない大きさです。

河川、池沼などの浅い水の中で餌を探している姿を見ることが多く、
いつも足がははっきり写らないのですが、
砂地にいるとイエロースリッパと言われる所以がよくわかります。

砂地には餌がいないと気付いたのか
しばらくして、飛び立ちました。
首をZ型に縮めて飛行します。

こちらは公園の小さな池、
コサギがめずらしく木の枝にとまりました。

木の枝の上、
首を伸ばして鶴のようなポーズをとってくれました。
胸には飾り毛、夏の繁殖期にはさらに頭部に飾り毛(冠毛)ができます。
一般に白鷺と呼ばれる白い鷺たちです。
その中で一番小型なのがコサギ、
一年中比較的よく見られる留鳥です。

河原の砂地に白い鷺がやってきました。
嘴が黒色、コサギです。

コサギ、
嘴と脚が黒色、
足はイエロースリッパと称され、
黄色で体に似合わない大きさです。

河川、池沼などの浅い水の中で餌を探している姿を見ることが多く、
いつも足がははっきり写らないのですが、
砂地にいるとイエロースリッパと言われる所以がよくわかります。

砂地には餌がいないと気付いたのか
しばらくして、飛び立ちました。
首をZ型に縮めて飛行します。

こちらは公園の小さな池、
コサギがめずらしく木の枝にとまりました。

木の枝の上、
首を伸ばして鶴のようなポーズをとってくれました。
胸には飾り毛、夏の繁殖期にはさらに頭部に飾り毛(冠毛)ができます。