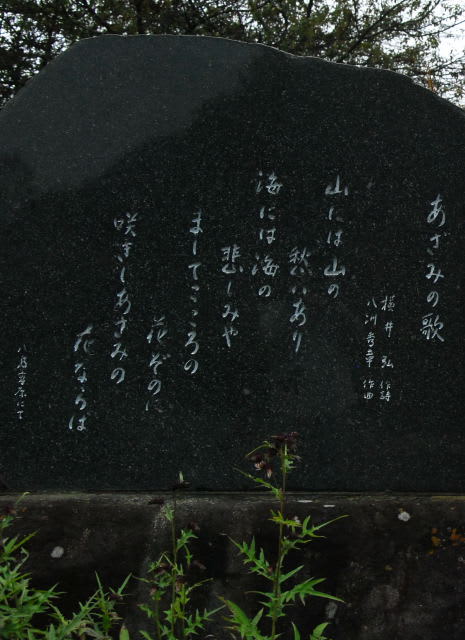遅れを取り戻すように,秋が急テンポでやってきました。
つい半月ほど前はティシャツで過ごしていましたが,
今日はセーターが欲しくなるほどの気候です。

ハグロトンボをよく見る小さな川,
ハグロトンボが急な秋の訪れに,あわてるかのように,
川面に浮かぶ水草に卵を産み付けています(9/19)。
ハグロトンボの象徴である黒い翅も色があせ,秋の色に変わっています。
もう間もなく短い生涯を終えるのでしょう。

飛びながら水の中に卵を落とすもの,水辺の土の中に卵を生むもの,
水中の植物に卵を産みつけるもの,
雄雌が連結して産卵するもの,雌だけで生むもの,
トンボは種類によって産卵の仕方が異なり,いろいろな形があるようです。
ハグロトンボは雌だけで,水中の植物に産み付けるスタイルのようです。
セーターをあわててさがし九月尽
つい半月ほど前はティシャツで過ごしていましたが,
今日はセーターが欲しくなるほどの気候です。

ハグロトンボをよく見る小さな川,
ハグロトンボが急な秋の訪れに,あわてるかのように,
川面に浮かぶ水草に卵を産み付けています(9/19)。
ハグロトンボの象徴である黒い翅も色があせ,秋の色に変わっています。
もう間もなく短い生涯を終えるのでしょう。

飛びながら水の中に卵を落とすもの,水辺の土の中に卵を生むもの,
水中の植物に卵を産みつけるもの,
雄雌が連結して産卵するもの,雌だけで生むもの,
トンボは種類によって産卵の仕方が異なり,いろいろな形があるようです。
ハグロトンボは雌だけで,水中の植物に産み付けるスタイルのようです。
セーターをあわててさがし九月尽