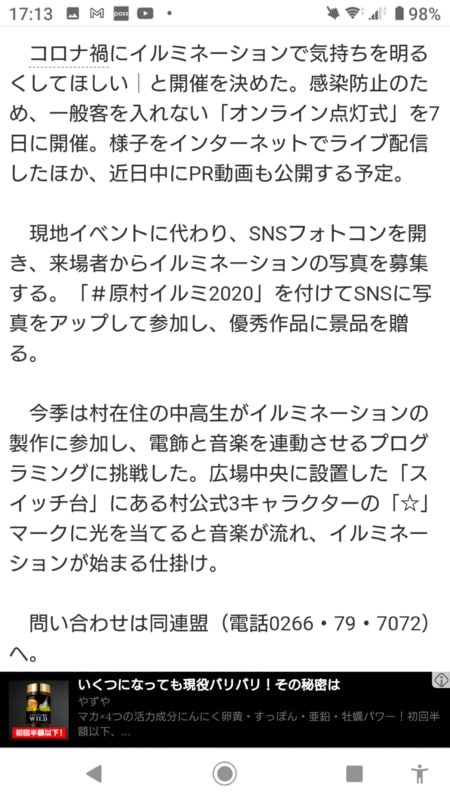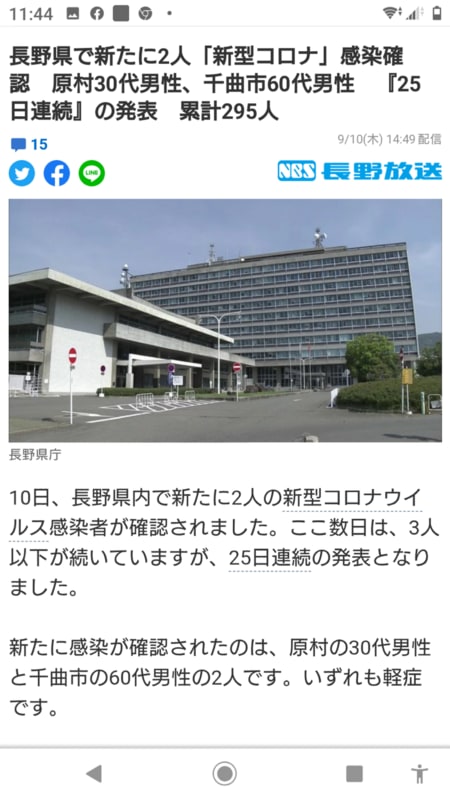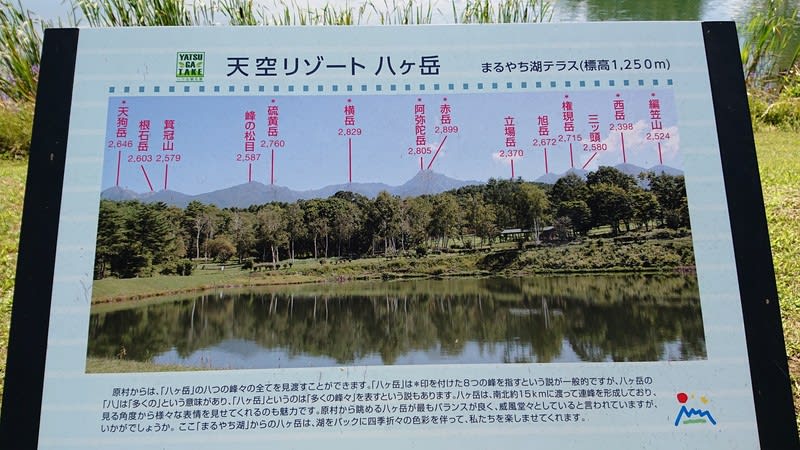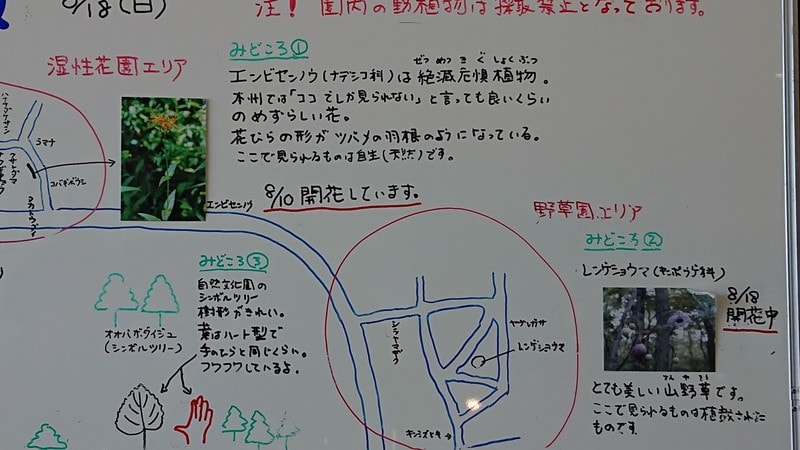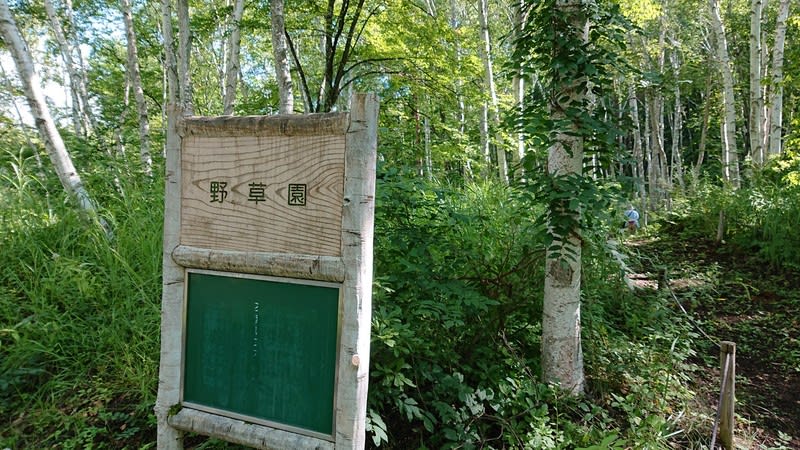2000年から原村に通い始めて、2020年の今年に初めて訪問しました。
勿論、原村に家を建てた時から原村郷土館があることは知っていましたが、すべてうろ覚えでした。
今回も家内が寄ってみようと言い出さなければ、伺うことなしに原村大通りを鉢巻道路に向かって直進していました。
開放期間は7月から9月までの夏季の期間のみでしたが、訪問したのは9月21日でした。
母屋も、蔵も解放されており拝見することができました。
母屋は縁側から拝見しただけでした。
係りの人がおりましたが、今回は外からのみで峠の我が家に戻りました。
1 原村郷土館です。

2 蔵の脇に「にょう」があります。「にょう」と言うと尿と勘違いされるので「わらにょう」と言うこともあるようです。「にょう」を知ったのも原村で拝見してからです。過去の自分のブログ記事で「にょう」ないし「わらにょう」でヒットした記事はこちらです。

3 屋根にトタン板でしょうか、茅葺の屋根を覆いつくしているようです。茅葺の屋根を維持することだけですら大変な経費が掛かるので致し方ないのかも。

4
原村郷土館のHPから一部引用させて頂きます。
江戸の終わり頃か明治の初めに建てられたといわれる、原村中新田の伊藤米之助氏宅を移築したもので、間取もこの地方では一般的なものです。平成18年には昭和30年代前半の農村生活の様子を再現しようと、台所や井戸の復元、裏縁側・食器棚の修理、敷地内の環境復元など、村をこよなく愛する方々と行ないました。
閉館中も敷地内にお気軽にお入りいただき、縁側等でお休みください

5 今回は特に見たかったのが、蔵などに漆喰などを塗るために発達した「鏝絵、こてえ、こて絵」です。蔵の壁に白い漆喰で盛り上げて幾何学模様が施されています。 この模様自体は「こてえ」ではありません。

6 蔵の屋根の所にも素敵な「こてえ」が描かれていましたが撮影しそこないました。是非、閉館日でも蔵の正面に向かって左手に在りますのでご覧いただけます。

7 原村の土蔵を彩る鏝絵(こてえ)として展示されています。来年の7月には是非ともお邪魔してみてください。

8

9

9 続いて、母屋へ。
母屋の座敷には赤ちゃんや未だ幼い子供を入れる大きな「ちぐら」がありました。御飯が覚めないようにお櫃を囲うものや、猫の「ねぐら」になる猫ちぐらが今でも有名です。こちらは、幼子を畑や田圃の脇に連れていきこの大きな「ちぐら」に入れえて保育と仕事を両立していたものです。自分の想像を超える大きさと言うか高さでした。子供が寄りかかっても倒れて外に転げ落ちても大変ですし。よじ登って出て来ることもできない大きさでした。長年の歴史を感じさせる道具ですね。でも、重そうですよ。

10 炊事場など料理する台所です。左手には風呂桶もも見えます。 
11

99