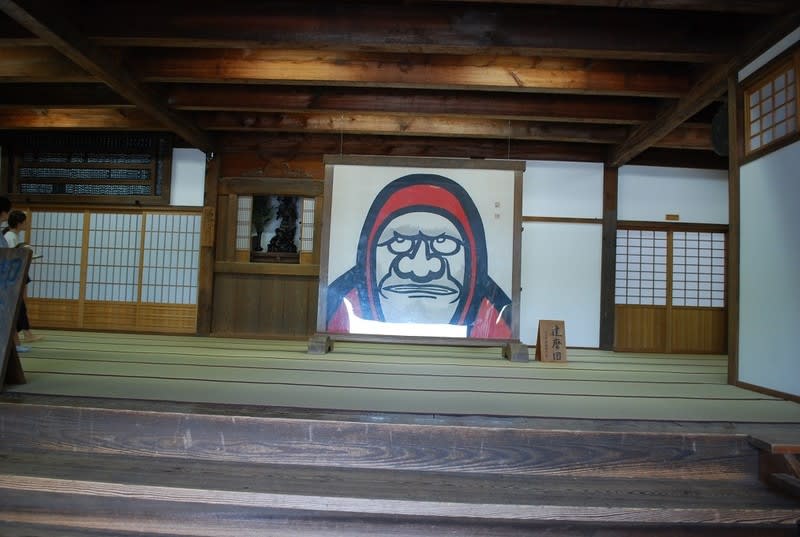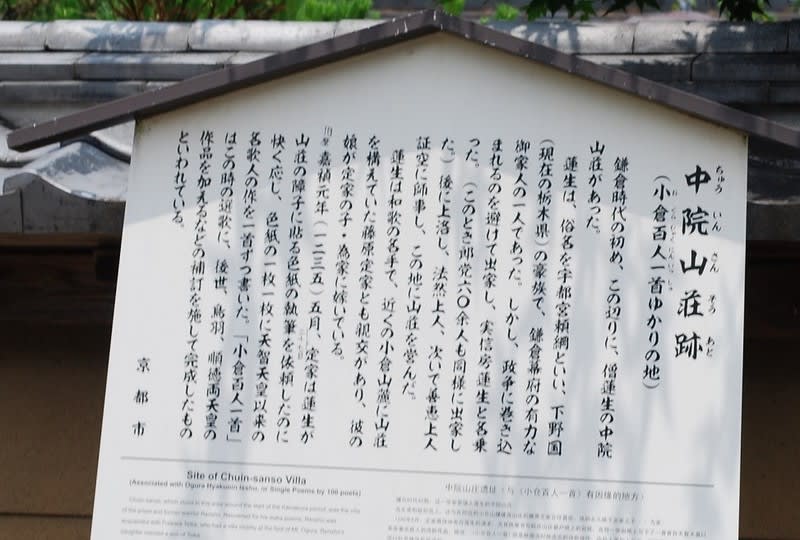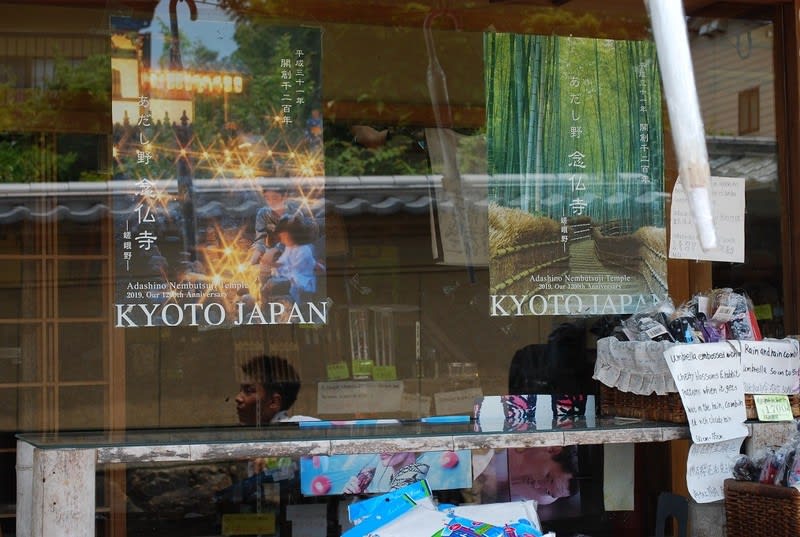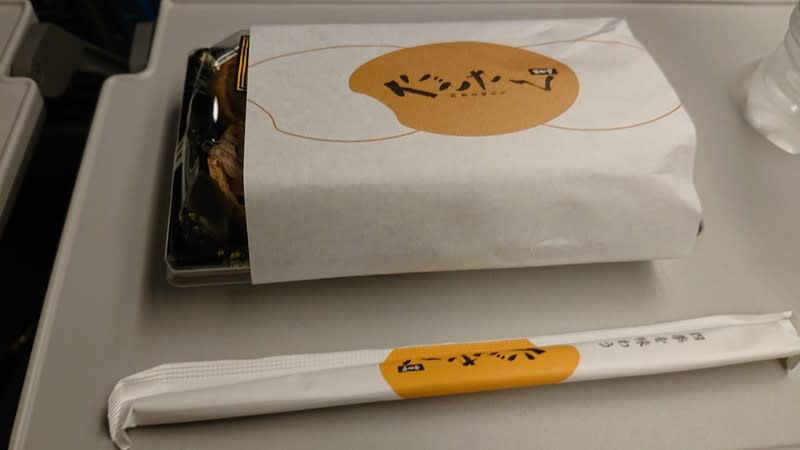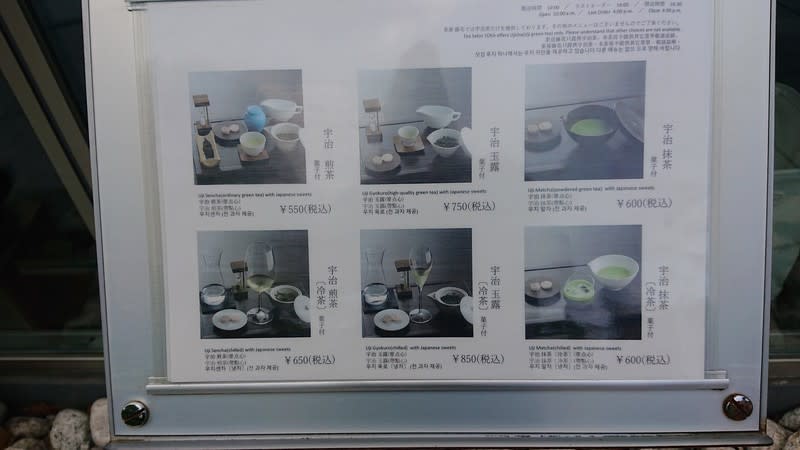好きでも嫌いでも無かった韓国・朝鮮。
以前は今ほどニュースに昇る事も、話題になる事の無い自分にとっては影の薄い国だった韓国&北朝鮮。
自分が幼い頃は大人は全く相手にしていない国だった。
それもそのはずだが、自分が子供の頃はGDPでも一人当たりの所得でも問題外であった。
今ではネットを観れば韓国&朝鮮の事がニュースに上る。
今回はG20の事、そして北朝鮮の核とミサイルの事。
話題を賑わしている隣国です。
【慰安婦問題】その韓国に誤った情報を提供し長い事誤った記事も訂正することなく両国を反目させる原因を作った朝日新聞。
決して許すことのできない新聞である。
長い事愛読してきたのに、事実を確認せずに報道した責任は廃刊に値すると思っている。
事実でない事を報道した責任は絶対に許すことができない。
時が流れてしまうので、後日第二弾でもう少し内容を述べたいと思っている。
以前は今ほどニュースに昇る事も、話題になる事の無い自分にとっては影の薄い国だった韓国&北朝鮮。
自分が幼い頃は大人は全く相手にしていない国だった。
それもそのはずだが、自分が子供の頃はGDPでも一人当たりの所得でも問題外であった。
今ではネットを観れば韓国&朝鮮の事がニュースに上る。
今回はG20の事、そして北朝鮮の核とミサイルの事。
話題を賑わしている隣国です。
【慰安婦問題】その韓国に誤った情報を提供し長い事誤った記事も訂正することなく両国を反目させる原因を作った朝日新聞。
決して許すことのできない新聞である。
長い事愛読してきたのに、事実を確認せずに報道した責任は廃刊に値すると思っている。
事実でない事を報道した責任は絶対に許すことができない。
時が流れてしまうので、後日第二弾でもう少し内容を述べたいと思っている。