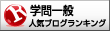「国民のヴォロンテ・ジェネラアルを以って法であるとし、法による拘束をば自由の実現であると説くルウソオの理論が、一方では自由・解放の時代思潮の尖端を行くものであったといわれ、他方で国家の権力を絶対化する思想の根源を成したと解せられるのは、共に理由のあることである。これら二つの
— review (@myenzyklo) 2017年11月12日 - 12:38
対蹠的な解釈が共に理由があるということは、ルウソオの理論に内在する大きな矛盾を物語っている。しかし、この矛盾は、決して単にルウソオだけの問題ではない。「国民主権主義」と「国権絶対主義」との対立・矛盾・交錯は、西洋近世の政治思想の共通の問題であり、したがって、西洋近世の政治思想の
— review (@myenzyklo) 2017年11月12日 - 12:43
発達を指導した政治的自然法理論の共通の問題であった。故に、この点を更に立ち入って考察することは、法と政治の関係を論究するための最も重要な手がかりとなるであろう。」
— review (@myenzyklo) 2017年11月12日 - 12:50
(尾高朝雄『法の窮極に在るもの』s.51第一章 自然法の性格 四 自然法理念の政治化)
※ 尾高はマルクス・エンゲルスの唯物史観や、彼自身の誤解するヘーゲルの「一元論」批判(独り相撲)を行ったのち、ルソーの社会契約論における「国民の総意」のかかえる思想的な問題点を指摘する。そのうえで、上のパラグラフをもってこの第四節の結論とする。しかし、ここで尾高が
— review (@myenzyklo) 2017年11月12日 - 13:01
「国民の総意を概念として捉えられなかったことがルソーの限界だ」というヘーゲルのルソー批判について知っていたかどうか?ここまでの記述では彼がそのことを知らなかった可能性が強い。それも思考における二律背反の問題として尾高は認識できていたかどうか?
— review (@myenzyklo) 2017年11月12日 - 13:10