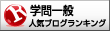先に取り上げたヘーゲルのルソーに対する批判は次のようなものである。
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:24
「ところでしかし国家一般の、あるいはむしろ特殊的な国家の、またその法や諸規定の歴史学的な起源がどのようにあり、もしくはどうあったか、国家がまず家父長的な関係から生じたか、恐怖やあるいは信頼から生じたか、a
職業団体などから生じたか、またこのような国家の法の基づくものが、いかにして神の法、実定法もしくは契約、慣習などとして意識によって把握され確定せしめられたか、これらは国家の理念そのものには関係はなく、ここにもっぱら問題である哲学的な認識の見地よりすれば、現象として歴史学的な b
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:24
事実に属するものである。すなわちある現実の国家の権威についてみる場合、それが様々な理由を求めようとする限り、それらの理由は、その国家において行使されている法の諸形式からとられているのである。⎯⎯哲学的な考察はひとえに一切のものの内面的なもの、すなわちこのような、思考された概念をc
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:33
取り扱う。この概念の探求に関してルソーは、単にその形式上にのみ思想である原理(いわば社会の衝動、神的な権威のごとき)でなく、内容上も思想である、しかも思考そのものである原理、すなわち意思を国家の原理として立てるという功績をなした。しかしルソーは意思を、単に個別的な意思の d
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:48
特定の形式によってのみ解し(その後フィヒテもなしたように)、普遍的な意思を、意思の本来的(an und für sich)に理性的なものとしてではなく、単にこの個別的な意思から意識されたものとして生まれた、単に共通のものとして解したに過ぎなかったから、国家における個人の結合はe
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:53
契約となり、したがってこの契約は個人の恣意、臆見、および言い表された同意に基づくもので、その結果として、本来的(an und für sich )に存する神的なものと、その絶対的な権威と尊厳とを破壊するところの、さらに広汎な単に悟性的な様々の結果をもたらすのである。f
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 20:54
それ故に、これらの抽象が暴威を振るうにいたるや、まことに一面では我々が人類について知って以来はじめての恐るべき光景、いっさいの実際に現存する諸制度や伝承を転覆して、偉大なる現実の国家の憲法を今や全く新たに、そして思想によって創始し、かつそれに与うるに g
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:04
単に空想された「理性的なもの」を以って基礎たらしめようと欲する光景を現出せしめるとともに、他面では、それは単に理念を欠いた抽象にすぎないから、その試みをも、もっとも戦慄すべく、もっとも驚くべき事件たらしめたのである。」 h(法の哲学§258補註)
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:04
※ 現実に歴史的事件としてフランス革命が発生した時、その戦慄すべき破壊的な結末を目撃したヘーゲルは、それら現象の根本的な要因として、ルソーの抽象的で悟性的な思想としての「国家契約説」にあることを説明している。
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:17
尾高がもし、法哲学のこの説明を読んでいれば、ルソーの国家契約説の論理的な帰結について批判する際にも触れていたはずである。そうでないから、次のような引用をして事足れりとすることになる。
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:51
「だから、ディギィなどは、ルウソオの思想はフランス革命の人権宣言
によってではなく、ヘエゲルの絶対主義の国家哲学によって継承された、と主張するのである。ルウソオの『社会契約論』に万能の国家権力から人間を解放する福音ではなく、人間をば国家の絶対命令の下にあますところなく隷属せしめる教説であった、と論ずるのである。
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:51
ルウソオの説くところを仔細に吟味して見ると、ディギィのような解釈もまた極めて鋭い洞察に立脚するものであることが知られる。」(ibid.,s. 51)
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 21:51
「近世の自然法論から岐れた国民主権主義と国権絶対主義とのこの対立は、その後も色々な形でくりかえされつつ今日に及んでいる。その中で、近世政治思潮の主流は、大体として前者にあるということができるが、そのいわば敵役のような形で演ぜられてきた後者の役割も、決して小さいものではない。a
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 23:03
しかも、両者は、そのいずれもが、結局「法の窮極に在るもの」を政治に求めているのである。法の究極に在るものが政治であるならば、政治は、一方では「法を作る力」となって働き、他方では「法を破る力」として作用する筈である。ここに法と政治をめぐる二つの主要なテエマがある。b
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 23:04
この二つのテエマに、いままで述べて来た「国民主権主義」と「国権絶対主義」の対立を織りなしつつ、これを、その顕著な現れであるところの「憲法制定権力」や「革命権」や「国家緊急権」の思想について叙述して行くことが次の二つの章の任務にほかならない。」(ibid.,s.57)
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 23:04
※
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 23:17
ここで確認しておく必要があるのは、尾高が「国民主権主義」と「国権絶対主義」の二者を、アウフヘーベンの対象としてではなく、二律背反の、二者択一の対立概念として捉えているらしいことである。もしそうであるなら、これも悟性的思考の典型と言わなければならない。
この悟性的思考の限界を尾高が克服しえているかどうかを検討すること、これも彼のこの著書における検証課題である。
— review (@myenzyklo) 2017年11月13日 - 23:17