先日のニュースで、数学の「ガウス賞」初代受賞者に、伊藤清京大名誉教授が選ばれたことが報じられていた。この賞は、実際に役立つ数学の応用に実績をあげた研究者を顕彰するそうである。伊藤清氏の業績は、氏が1942年に内閣統計局に勤務していたときに研究したという、粒子の不規則な運動を予測する「確率微分方程式」の理論に対して与えられたそうである。
しかし、この方程式が実際に応用され活用されたのは、実に40数年後の1980年代に、「デリバティブ(金融派生商品)」の価格決定に関する理論においてだそうである。だから、伊藤清氏の理論が株屋さんの金儲けに「実際に役立つ」のには、ほぼ半世紀の歳月を要したということになる。これは数学の世界の話である。
ひるがえって、同じ学問科学の世界でも、哲学においてはどうだろうか。哲学は、果たして数学のように「実際に役立つ」ことを期待できるのだろうか。もちろん、その答えは、人がどのような「哲学観」をもつかによって決まるのだろう。ある人は、哲学は詩や文学と同じだから、必ずしも「実際に役立つ」ことがなくともよいのだ、というかもしれない。音楽などと同じようにそれ自体に意義があって、哲学が「実際に役立つ」ことなど求められるだろうかと言うわけだ。
あるいは、自然科学や社会科学と同じように、哲学にも現実に有効な「実際に役立つ」ことを要求する哲学者がいるかもしれない。私も実はこの立場に立ちたいと思っている。哲学もまた現実に有効な理論的知識でなければならない。
それでもし、哲学が実際に役立つとすれば、それは哲学がどのような性質を持っているからだろうか。
哲学はまず第一に、「真理」を探求することを目的としている。「真理とは何か」それ自体が哲学の中心的なテーマである。そして、宗教がまた「真理」にかかわる世界だとすれば、哲学は宗教と接点を持つということになる。哲学が宗教を問題にし、また、宗教とならべて論じられるのも、そのためである。だから、真理を知ろうとすれば、哲学や宗教の門をたたかなければならないということになる。
しかし、哲学が宗教と異なって一つの独立した領域を形作っている限り、哲学が宗教と異なる独自性があるはずである。その独自性とは何か。それは、哲学が思考をあるいは概念を唯一の研究手段としているところにある。哲学は何より真理を思考によって、概念によって把握しようとする。哲学とは、思考を思考によって分析すること、概念を概念によって研究することでもある。だから、哲学は「思考の科学」と呼ぶこともできる。哲学が言語学や心理学と近接した関係をもつのもそのためである。
ただ、この仕事は、それが極めて困難でゆえに、私たち凡人には容易に成し遂げられないということなのだろう。そして、哲学は宗教を理解するが、宗教は哲学を理解できるとは限らない。哲学も宗教も同じく「真理」を、世界との宥和を、宗教的に言えば「救い」を目的とし、対象としているのに、宗教が時には狂信的に熱狂し、「理性」を失って最悪の「非真理」に転化しがちであるのと異なっている。
宗教が「信仰」を求めるのに対して、哲学はその正反対に「疑う」ことを本質とする。その意味で、プラトンが、「どこに行き着くか分からないけれども、思考の、論理(ロゴス)の行き着くところまで徹底して行こう」と語っているのは、いかにも「哲学の父」にふさわしい言葉といえる。ヨーロッパ人のその「ロゴス」に対する信頼は、このプラトンに始まる。ヨーロッパの羨むべき貴重な伝統であり遺産だと思う。また一般に、コーカサス人種が観念的であるのに対して、モンゴル人種は実利的であるといわれているように、東洋人にとっては哲学は得意な分野ではないのかもしれない。
明治の文明開化以来100余年を経過しているけれども、残念ながらわが国にこの伝統が移植され根付いたとは全く思わない。わが国の科学や学問は、その実利的、実用性の側面はとにかく、ひよわな宗教の精神と同じく、あるいは、それが原因で、その根はまだ極めて浅く脆いと言うべきだろう。
人は誰でも自由にのびのびと思う存分に「思考」しているのだけれども、ただ、往々にして、優れた自然科学者であっても、その思考を論文、著書などに書き表しているのを読むとき、その論文に使用されている、「概念」や「判断」、および「推理」などがきわめて粗雑だと思うことが少なくない。もちろん、私自身のそれもきわめて粗雑だから、偉そうなことを言う資格は全くないことはよくわかっている。けれども、多くのベストセラー作品を生み出している、脳解剖学者の養老孟司氏や数学者の藤原正彦氏らの著書を読んだときも、そのような印象を受けた。(書評 藤原正彦著『国家の品格』)
だから、やはり、少なくとも学問や科学の世界で生きてゆこうと考えるような人は、一通り哲学の基礎的な訓練を受けておく必要があると痛感している。もし哲学に「実際に役立つ」実利的な性格があるとすれば、学者や科学者ら研究者の思考や論理がより正確により厳密になることが期待できることだろうか。少なくとも、哲学によって、つねに思考の厳密性、正確性を向上させて行かなければならないという自覚を持つようにはなる。
実際に太平洋戦争前の大学や大学院では、科学研究者の基礎的な教養として論理学の訓練を受けたと聞いているが、最近の大学や大学院ではあまりそういうことは聞かない。これはまあ私の世界が狭いだけかもしれない。
ある国民の政治や教育、芸術、行政(地方自治)その他の水準が貧しく低いとすれば、それは結局、その国民が所有する大学および大学院での教育の貧困に原因がある。国民や民族の文化は、その国民や民族が所有する大学および大学院の水準に規定されるからである。それ以上に高まることは期待できない。日本の大学教育と欧米のそれとを比較してみることである。
加藤紘一氏や小沢一郎氏、小泉純一郎氏ら政治家も、また、財務省や外務省の公務員職員も、そして堕落したマスコミ人もすべて、大学で「教育」されて社会に送り出されてきたのである。彼らもまた大学で「倫理教育」と「学術教育」を受けて世に送り出されて来る。現在の大学が彼らのような水準の人材しか社会に送り出しえていないとすれば、大学教授をはじめとする大学の教職員は、今一度自分たちの使命と義務を深刻に反省する必要があるだろう。そして、その中でも、大学および大学院で、どの程度の水準で哲学研究が行われているかが決定的に重要であると思う。大学改革の難しさもここにある。
政治家における人材をとっても、吉田松蔭などは言うまでもなく、岸信介や池田勇人ら往年の政治家らと比較しても現代の政治家の資質はどうか。自民党の総裁候補、安部晋三氏は憲法改正とならんで教育改革を新政権のテーマにするようである。江戸明治大正期の教育と教育制度を、もちろん、それらを絶対視するつもりは毛頭ないが、戦後世代が自分たちの受けた教育を相対化して反省し、現在のそれと比較することによって、アメリカ占領軍の統治下で始まったいわゆる戦後教育の制度と内容の欠陥を、あらためて根本的に再検討するという問題意識をせめてもたなければならないと思う。それが、日本が自由で独立した主権国家としての道を歩みだす第一歩である。哲学もまた「真理」の探求をみずからの仕事と課す限り、そのためにいささかでも貢献できることがあると思う。










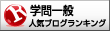




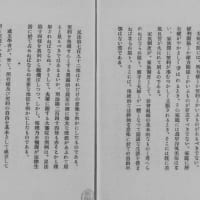

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

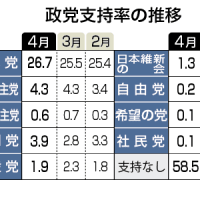









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます