§1
常識というものは、ただそれが知ろうとする対象についてだけを考えるが、しかしその時、知識そのものについては考えようとはしない。つまり、知識そのものついては思い浮かべないのである。知識そのものの中にある全体の姿は、単に対象のみではなく、自我の知るという作用でもあり、a
自我と対象との相互の関係でもある。つまり意識である。
§2
哲学においては、知識を規定するものは、ただ単に一方的な事物の規定だけとは見られない。むしろ事物の規定と事物そのものを共に含むところの知識が問題となる。言い換えると、知識の規定は客観的な規定としてのみではなく、
主観的な規定とも見られるのである。むしろ、知識の規定とは、客観と主観との相互の関係の特定の形態だと言える。
§3
そこで知識の中には、事物とそれに対する規定の両方があるから、一面から言えば、それらは全く意識の外にあって、意識にとっては全くの外来品として、出来合いのものとしてc
外から与えられたものであると考えることもできる。しかし他面では、意識は知識にとって、事物そのものと同じく、本質的なものであるから、意識はこの自分の世界を自分自身で規定し、その世界のさまざまな規定を自分の態度と活動によってその全部を、あるいは一部を自分で作り出し、または d
変形するものと考えることもできる。第一の見方は実在論(Realismus)、他方の見方は観念論(Idealismus)と名付けられる。しかし、ここ哲学では、事物の一般的な諸規定は、ただ、客観の主観に対する特定の関係と見なければならない。d
※いわゆる常識の、日常の知識というものが、つまり人間の知識が、単なる実在論でもなければ、また観念論でもなく、それは客観と主観との関係の特定のあり方であること、つまり、人間の知識が本質的に弁証法的なものであることが示されている。
§4
さらにはっきり言えば、主観とは精神である。ところで、精神は存在する対象に本質的に関係するものであるから、現象するもの(erscheinede)である。その限り精神は意識である。だから、意識についての論考は、
精神の現象論(Phänomenologie des Geistes)でもある。
§5
しかし精神が他のものとの関係を離れて、自分自身の内部で、したがって自分自身との関係において、自己の活動性の面から見られると、それは本来の精神論、つまり心理学である。 b
§ 6
意識とはふつう、その外部にあるか、または内部にある対象についての知識であって、その対象が精神の働きが加わることなくして意識に現れたものであるか、それとも精神によって作り出されたものであるかは問題ではない。意識のさまざまな規定が、精神そのものの働きに基づくものである限り、
精神は精神の活動の面から考察される。
§7
意識とは自我の対象に対する特定の関係である。我々が対象から出発する限り、意識の持つ対象の区別に応じて、意識にも区別があるということができる。
§8
しかしまた同時に、対象は本質的に意識に対する関係から規定される。
したがって、逆に対象の区別は意識の発展に依存すると考えらる。この相互性は意識そのものの現象する領域の中に生じてくる。したがってこの相互性から見れば、これら意識の面と事物の面の二つの規定の、いずれが絶対的に主導性を持つかという先に§ 3で述べた問題は未決定のままに残される。










 review @myenzyklo
review @myenzyklo





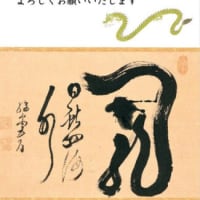
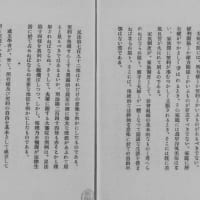

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

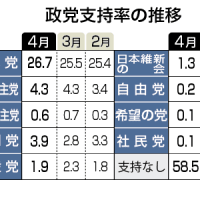







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます