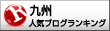めがね橋 余生をながめ 菖蒲池
梅士 Baishi
諫早は長崎の入り口に位置する長崎街道要衝の宿場町である。
今は諫早湾開拓問題でもめているが、鰻料理とめがね橋で知られる.
しかし、自分にとっては、小説家・野呂邦暢(代表作「草のつるぎ」「諫早菖
蒲日記」など)の街というイメージが強い。
かつて諫早の田舎風の静かな図書館が気に入って通っていたことがあっ
た。
そのときに読んだのが、『地峡の町にて』という野呂作品であった。
その本の装丁がそっくり諫早のイメージになっている。
諫早のめがね橋は、昭和32年(1957年)の本明川の洪水のとき、多くの
流木などをせき止めて諫早大洪水の原因となったといわれる。
洪水で流されないほど頑強な作りであったが、それが禍して、今は諫早公
園の池に余生を送ることを余儀なくされている。
そのめがね橋の池に菖蒲が咲いていた。
そんな季節だろうかと疑ったが、諫早のめがね橋には良く似合う花である。

【日本学生たちよ、国家独立の為に立ち上がれ!】
60年、70年の安保反対闘争は、社会主義の嵐であった。
なぜ、そんなことになったのか、戦後ベビーブーマーたちの反乱のよう
でもあった。
岸信介は国賊のように罵られてもいた。
ところが、正義であることを疑わなかった学生運動こそは、社会主義
の妖術に踊らされた悪魔的な熱狂であった。
しかし、現代はどうか。
政府自らが日米の安全保障システムを壊そうとしているのである。
学生運動のカルマというべきか。
結果、日本滅亡の秒読みが始まってしまった。
学生たちよ、それでも黙ってみているのか。
維新の志士とはならないのか。
民主党・社会主義政権打倒、安保堅持、普天間基地存続、地方自
治廃止、「日本国憲法廃棄」、独立憲法宣言、消費税廃止・・・。
そうしたことを叫ばないのか。
街頭に立たないのか。
デモ行進をしないのか。
学生よ、天命に目を覚ませ!
天の声を聞け!
国作りの青春を送れ!
今が、その時である。
立憲女王国・神聖九州やまとの国
梅士 Baishi