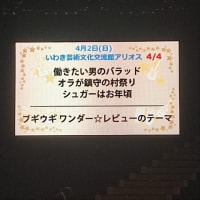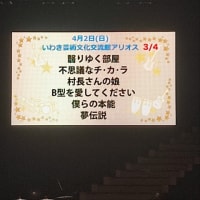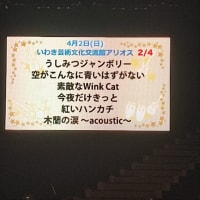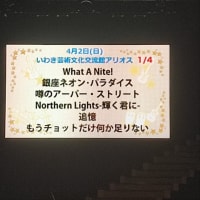仕事が非常勤時間講師のため、この非常事態宣言で4月後半の仕事がなくなった(当然そこは無給)。
かといって、この自粛(騒ぎ)では出歩くこともできない。
(「騒ぎ」などと書くとお叱りを受けそうだが、自粛はちゃんとやってます。でも、納得はしてないよ、という程度の意味です。)
というわけで不本意ながら超暇になったので、以前からやろうやろうと思いながら果たせていなかった、母親の家系と人物の説明図の作成をようやく実行に移した。
不本意といいつつ、仕事が休みになるのはちょっとワクワクする面もある。
仕事は社会貢献でもあり、自分にとって大切な経験の場でもあるのだが、結局お金のための我慢しているという側面もゼロではないから、4月から働き出したはかりだというのに仕事がなくなってホッとしている自分もあって、それもなんだか「ヤレヤレ」なのだけれど、それはさておき。
母親は現在88才。
福島県いわき市で生まれた。
父親(つまり私の祖父)は炭坑の街湯本の、母親(祖母)は勿来の出身だ。
私の母親が知っている範囲で、片方半日ずつ時間をかけて聞き取り「調査」を実施した(笑)
出てきたのは、私を含めて5五世代の話だ。
第一世代→昭和30年代の私。
第二世代→昭和初年代の母親
第三世代→明治末期の祖父母
この三世代までは私が知っている範囲だ。祖父母の兄弟は見たことがあるし、その子まではなんとかわかる。分からないまでも、いわゆる福島あたりでいう「マケ」つまり一族の範囲ぐらいは一応なんとなくきいたことがある。
つまり、第四世代、私にとっての曾祖父母(母の祖父母)までは、私にとっての「血の意識」が、届く範囲といっていいだろう。その上の第五世代(私にとっての高祖父母)までは名前は分かるが、その親戚とか一族のことは分からない。どこの「安島」という「マケ」から(第五世代の)お嫁さんが来たのか、という話になる。
第四世代→明治中期
第五世代→明治政府ができて以後
第六世代→明治初期に戸籍を買って長男となった、などの「言い伝え」のみ残る
といったところか。もはや第六世代になると実態は分からない。
ちなみに法律上の「親等」という概念は、自分を0と数えるので両親が一親等、祖父母が二親等、曾祖父母が三親等、したがって高祖父母は四親等。
他方、世代という横の帯の区切りで考えると、自分を一世代とと捉えれば、全部で5つの世代ということになる。
そしてこの系図聞き書きが、意外なことに、抜群の面白さだった。
今、抜群の面白さだったと書いたが、私の中ではその面白さが今回書こうとする『ホハレ峠』の面白さに繋がっているので、もう少しお付き合いいただければありがたい。
かつてアメリカで『Roots』という小説が爆発的に話題となった。そのTVドラマは日本でも高視聴率だったと聞く。自分のルーツを知りたいという思いは分かる。ましてアフリカ系アメリカ人の作者にとって、当時それを掘り起こして形にすることは、強いモチベーションに支えられた仕事だったと想像できる。
だが、私が面白かったのはそういった祖先探し、ルーツ探しの魅力ではない。
ポイントは「語り」だ。今まで、母親・父親・祖父母が繰り返し断片的に語ってきた「マケ」の話、どの世代どこに住む親戚だかも分からない人の名前が次々に出てきて、そういう人がいたということだけは印象にのこっているものの、いわゆる分家の「マケ」が字(あざな)の名で呼ばれたり、通称で言われたり、襲名された本家(父方は商家だったので、嫡男は同じ名前も継いだのだ。そりゃわからなくなるよね)は違う人が同じ名前で呼ばれていたり、もはや『百年の孤独』かってカオス状態だった。
おそらく皆さんの多くも、お年寄りの話を若者が「傾聴」する習慣が最近出来てきて(いいことです)、いろいろな昔話を聴く体験をしていると思う。
で、これが再構成困難なのだ(笑)
母親が生きているうちに系図とヒモづけて話を聞くことができた結果、五世代にわたる「マケ」の全貌が母親の父方、母方2系列に渡って再構成することができた。
ああ、あの身代を潰したといわれる「細めのコウゾウ」さんは、そういう人(商才がなくて、お店を預けられたのに、イケメンでモテて、お店の売り物の高級たばこに手を着けるひとで、結果身代を潰した人)だったのか、とか、街の世話役をやっていた三代前の当主はお目かけさんと正妻の間でだいぶ「苦労」したとか、「行かず後家」の人たちは、「マケ」の中の繁盛していた家が引き取って「お二階姉さん」としてその家の切り盛りを奥さまに代わってマネージメントし、みんなに一目置かれていたとか、様々な人の生きている様子が、極めてリアルに立ち上がってくることになったのである。
それはいわゆる自分のルーツを辿る「旅」とはちょっと違う悦びだった。
ルーツを辿るとは、たった一つの、もしくは少数の、自分の血筋の原点にむけて遡行(ソコウ:さかのぼること)する「旅」がメインになる行為、とみていいだろう。
私(ブログ子)が驚いたのは、そういうことではない。
まあ、面倒臭い話をちょっとすると、わたしの祖先はたった一つの血統に収斂するはずがないものだ。遡れば遡るほど、祖先は広がっていく。当然至極だ。父母は2人、祖父母は4人、曾祖父母は8人と、さかのぼれば遡るほど広がっていくではないか。そしてそこから改めて下の世代をみれば、あたかも扇状地のように人々の血筋は広がっていく。
つまり、ルーツが一つというのはほぼまちがいなく都合の良いフィクションにすぎない。
「万世一系」のくだらなさは言うに及ばず、だが、そういう話は今はどうでもよい。
語り始めたのは良いけれど、まだ『ホハレ峠』にたどり着く気配がないのには正直困るが、もう少しお付き合いいただきたい。
まとめて言えば、あまりにも多様な「生きること」の集積に、驚いた、ということになるだろうか。
そんなことは当たり前のこと、かもしれない。まあ、そうだろう。親戚を辿れば人間の数が増えていくことは、小学生でもわかる。たが、これはそういうことで「も」ない。
たった1人のルーツ探しが特権的な系図を称揚する(ほめたたえる)ためのフィクションであるとするなら、他方で親戚を辿ってカウントしていけばいろんな人がいるという話は、結局のところいろいろあるよね、という数に解消された抽象にすぎなくなってしまいかねない。
かつて年寄りの話を聞いていたときには、意味が分からず退屈で、ただ祖父母に付き合うためにだけ聴いていたような断片が、お話の総体に適切に配置されることによって、生き生きとした相貌(かおかたち)を獲得していく過程がそこにあったからだ。
いや、もう少し正確に言おう。
断片だけの話は正直聴くのがツラい。
ちょうどガルシア・マルケスの小説『百年の孤独』の最初の100 ページを読んでいるときの気分のようだ(笑)
だが、丁寧にメモをとって話をきいていくと、その断片が次第につながり出し、最後には全体像を結び、かつそれが大きな100年の流れとして把握できるようになっていくのだ。そこに立ち現れる悦びは、語りを聴く体験におけるレイヤーというか、次元というか、そういうものもまた多層的なのだと気づかされ、そのことにも感動を覚えてしまった、のだろう。
やれやれ、いくら書いても『ホハレ峠』に辿り着かない。
ここはさらにゴールデンウィーク後半に読了した
『百年の孤独』ガルシア・マルケス
を迂回して騙らなければならない。読んでくれる奇特な人がいる、と仮定しての話ですが。