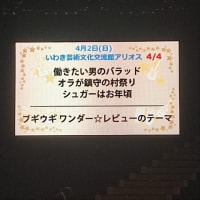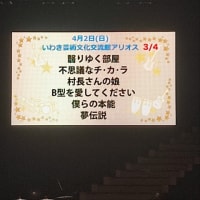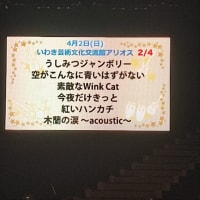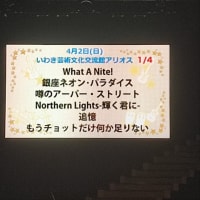なかなか大西暢夫さんの『ホハレ峠』にたどり着かない。
そんな中、エチカ福島の仲間の一人が幻の第14回(イベント中止が決まった後の大西監督との飲み会)での監督の言葉をピックアップしていた。
大西監督曰く
「今の時代の価値観はたかだか100年程度、人間の歴史から見ると一瞬に過ぎない。
今の価値観が見直されるときがきっとくる、自分の仕事がその時の資料になればと思っている。」
100年、か。なるほど。
というわけでたどり着かない大西暢夫論の第2回は、最近読んだばかりの『100年の孤独』との関わりについて書く。
100年といえば、その1で書いた母親の聞き書きの範囲もまた、おおよそその程度の長さになる。
30年一世代とよくいうが、当時は10代で子供を産むこともめずらしくなかったし、100年程度のうちに5世代が重なりながら広がっていて、二つ上の世代(祖父母)までは直接話が聞けることも多いということもあり、ざっと100年程度が私たちの生きた言葉の語りが届く範囲、と考えても良さそうだ。
祖父母の祖父母まで、自分を含めて5世代。
これはそのまま『百年の孤独』の世代とぴったり対応している。
ガルシア・マルケスの小説『百年の孤独』には、コロンビアとおぼしき未開の土地にマコンドという町を開拓し、その中心にあった一族とマコンドという町の盛衰記が描かれているのだが、ほぼ要約は不可能だし、大河ドラマのようなたった一人の主人公がいるわけでもない。語りの中心には一族のグレイトマザー的なその100年を見つめていく第一世代の長寿な女性と、その女性よりもさらに長生きする陰の語りの担い手であるもう一人の女性が二つの視点人物になっているとも見える。ふたりの女性は「語り手」ではないが、明らかな視点人物であり、日本の小説でいえば中上健次の「オリュウノオバ」(『千年の愉楽』)に比することもできそうだ。当然、中上健次が影響を受けている、というべきなのだろうが。
ここでは、千年ではなく百年、というところにこだわっておきたい。
千年は無時間的な語りの時間という喩えを感じるが、百年は、その一でも書いたように、顔の見える人の営みの広がりの限界とでもいえる長さだ。高祖父母も曾祖父母も見たことはないが、祖父母の話なら直接聞いたことがある。その祖父母が直接出会っていたのが私の祖父母にとっての祖父母、(つまり私にとっての曾祖父母)だ。
写真があったかなかったぐらいの世代、でもあろう。
その長さを大西暢夫監督は「一瞬」と語る。私の中ではその『ホハレ峠』における一瞬が『百年の孤独』の百年と重なって見えるのだ。
『百年の孤独』の「孤独」の意味、ということについて考えをめぐらす、ということにもなるだろう。
一読しただけの素人の管見だが、この「孤独」は、間違っても「近代的個人」の孤独ではない。
中南米の奥地に花開き、そこに川の治水がなされ鉄道が敷設され、バナナ農園が作られ、そして衰退していくマコンドに存在する「孤独」があるとするなら、それはそういう近代化とは全く別のものだろう。
『地球の長い午後』ブライアン・オールディス
に描かれている圧倒的な生命力に満ちあふれた植物やアリが全盛の世界にむしろ近い、といったらそれはそれでミスリードかもしれないが、少なくても、北アメリカ主導で展開され、中南米に押しつけられるインチキくさい「近代化」とは全く別の豊穣なエネルギーの充溢が抱える「孤独」として読まねばなるまい。
個人個人の「孤独」に苦悩する「近代」とかいうものとは対極の、オルタナティブとしての「孤独」。
大西監督の「百年は一瞬」という時間認識は、その「孤独」と通底している。
『ホハレ峠』のことばたちは、ダム工事が究極の無駄だということを声高に語ることをしない。
ひたすら廣瀨ゆきえさんの人生を丁寧に取材していくだけだ。
しかし、
「現金化したら、何もかもおしまいやな」
「国の話を聞いてやろうと思った瞬間に、国は金を持って村民の心の中に入り込んでくるのだ。……集団移転などというのはわるで筋違いのことで、そこには村や家族の形はない。すべてがそれに似せたもの」
というところにも、「似せたもの」ではない「村や家族の形」を生きてきた廣瀨ゆきえさんの傍らに立ち続ける大西監督の姿勢が見える。
近代的個人の孤独に対置された村や血や家族の物語の称揚、ということではない。
そんなものがあるとすれば近代個人のノスタルジーにすぎまい。
もう一つの姿が私たちに迫ってくるのは、その生きることそのものの峻厳さと向き合うという意味での「孤独」がそこに表現されているからだろう。たかだか100年は一瞬だということの意味は、そこにあるのではないか。
母親が語る私(たち)の上の世代の人々の栄枯盛衰の様子ともそれはズレながら重なりあう。
母親の父(私の祖父)は炭鉱の糧食(生協のようなものか?)の仕事から、無尽講の開拓(後の相互銀行)に身を転じた男だが炭鉱の盛衰と相互銀行の盛衰は、私の周辺における語りの広がりの限界に近いといっていいものだが、その百年とも重なる。生きるということそのものの姿が持つエネルギーの豊かさ。
そういうものを感じたということだ。
さて、まとまらないままだが、もう一回だけ大西暢夫監督のいる場所にもう少し近づいてから終わりたい。
もしもメモにもならないメモにもう少しつきあっていただけるなら、の話だが。
そんな中、エチカ福島の仲間の一人が幻の第14回(イベント中止が決まった後の大西監督との飲み会)での監督の言葉をピックアップしていた。
大西監督曰く
「今の時代の価値観はたかだか100年程度、人間の歴史から見ると一瞬に過ぎない。
今の価値観が見直されるときがきっとくる、自分の仕事がその時の資料になればと思っている。」
100年、か。なるほど。
というわけでたどり着かない大西暢夫論の第2回は、最近読んだばかりの『100年の孤独』との関わりについて書く。
100年といえば、その1で書いた母親の聞き書きの範囲もまた、おおよそその程度の長さになる。
30年一世代とよくいうが、当時は10代で子供を産むこともめずらしくなかったし、100年程度のうちに5世代が重なりながら広がっていて、二つ上の世代(祖父母)までは直接話が聞けることも多いということもあり、ざっと100年程度が私たちの生きた言葉の語りが届く範囲、と考えても良さそうだ。
祖父母の祖父母まで、自分を含めて5世代。
これはそのまま『百年の孤独』の世代とぴったり対応している。
ガルシア・マルケスの小説『百年の孤独』には、コロンビアとおぼしき未開の土地にマコンドという町を開拓し、その中心にあった一族とマコンドという町の盛衰記が描かれているのだが、ほぼ要約は不可能だし、大河ドラマのようなたった一人の主人公がいるわけでもない。語りの中心には一族のグレイトマザー的なその100年を見つめていく第一世代の長寿な女性と、その女性よりもさらに長生きする陰の語りの担い手であるもう一人の女性が二つの視点人物になっているとも見える。ふたりの女性は「語り手」ではないが、明らかな視点人物であり、日本の小説でいえば中上健次の「オリュウノオバ」(『千年の愉楽』)に比することもできそうだ。当然、中上健次が影響を受けている、というべきなのだろうが。
ここでは、千年ではなく百年、というところにこだわっておきたい。
千年は無時間的な語りの時間という喩えを感じるが、百年は、その一でも書いたように、顔の見える人の営みの広がりの限界とでもいえる長さだ。高祖父母も曾祖父母も見たことはないが、祖父母の話なら直接聞いたことがある。その祖父母が直接出会っていたのが私の祖父母にとっての祖父母、(つまり私にとっての曾祖父母)だ。
写真があったかなかったぐらいの世代、でもあろう。
その長さを大西暢夫監督は「一瞬」と語る。私の中ではその『ホハレ峠』における一瞬が『百年の孤独』の百年と重なって見えるのだ。
『百年の孤独』の「孤独」の意味、ということについて考えをめぐらす、ということにもなるだろう。
一読しただけの素人の管見だが、この「孤独」は、間違っても「近代的個人」の孤独ではない。
中南米の奥地に花開き、そこに川の治水がなされ鉄道が敷設され、バナナ農園が作られ、そして衰退していくマコンドに存在する「孤独」があるとするなら、それはそういう近代化とは全く別のものだろう。
『地球の長い午後』ブライアン・オールディス
に描かれている圧倒的な生命力に満ちあふれた植物やアリが全盛の世界にむしろ近い、といったらそれはそれでミスリードかもしれないが、少なくても、北アメリカ主導で展開され、中南米に押しつけられるインチキくさい「近代化」とは全く別の豊穣なエネルギーの充溢が抱える「孤独」として読まねばなるまい。
個人個人の「孤独」に苦悩する「近代」とかいうものとは対極の、オルタナティブとしての「孤独」。
大西監督の「百年は一瞬」という時間認識は、その「孤独」と通底している。
『ホハレ峠』のことばたちは、ダム工事が究極の無駄だということを声高に語ることをしない。
ひたすら廣瀨ゆきえさんの人生を丁寧に取材していくだけだ。
しかし、
「現金化したら、何もかもおしまいやな」
「国の話を聞いてやろうと思った瞬間に、国は金を持って村民の心の中に入り込んでくるのだ。……集団移転などというのはわるで筋違いのことで、そこには村や家族の形はない。すべてがそれに似せたもの」
というところにも、「似せたもの」ではない「村や家族の形」を生きてきた廣瀨ゆきえさんの傍らに立ち続ける大西監督の姿勢が見える。
近代的個人の孤独に対置された村や血や家族の物語の称揚、ということではない。
そんなものがあるとすれば近代個人のノスタルジーにすぎまい。
もう一つの姿が私たちに迫ってくるのは、その生きることそのものの峻厳さと向き合うという意味での「孤独」がそこに表現されているからだろう。たかだか100年は一瞬だということの意味は、そこにあるのではないか。
母親が語る私(たち)の上の世代の人々の栄枯盛衰の様子ともそれはズレながら重なりあう。
母親の父(私の祖父)は炭鉱の糧食(生協のようなものか?)の仕事から、無尽講の開拓(後の相互銀行)に身を転じた男だが炭鉱の盛衰と相互銀行の盛衰は、私の周辺における語りの広がりの限界に近いといっていいものだが、その百年とも重なる。生きるということそのものの姿が持つエネルギーの豊かさ。
そういうものを感じたということだ。
さて、まとまらないままだが、もう一回だけ大西暢夫監督のいる場所にもう少し近づいてから終わりたい。
もしもメモにもならないメモにもう少しつきあっていただけるなら、の話だが。